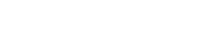味、色、香り、お茶をおいしく味わう
ご存知ですか?愛媛って実は「お茶どころ」

緊張を緩め、疲れた心を癒し、冷えた体にぬくもりを与える。一服のお茶には、決して栄養だけでは表現できない成分が含まれている。社交の場においては、最近ではコーヒーや紅茶、ジュースなどと多彩ではあるが、「やっぱりお茶がいい」と思うのは、昔から慣れ親しんだせいだろう。
日本茶の生産地といえば静岡、鹿児島、三重、京都などが有名。寒冷地の北海道を除く日本全国で栽培され、製茶されている。もちろん愛媛にも、おいしいお茶がある。寒暖の差が激しく朝霧がかかるような厳しい自然条件の中で、伝統的な製法を継承しながら茶葉を生産している。その愛媛のお茶のいくつかを味わってみよう。
霧深い山あいの里を思い味わう
西日本最高峰の石鎚山のある四国産地は、味のいいお茶づくりに適したエリアだ。愛媛のお茶で有名なのは「新宮茶」、「久万茶」、「宇和茶」など。いずれも昼夜の寒暖差が大きい山あいの里で昔ながらの製法で作られている。
新宮茶は昭和20年代から本格的に取り組んだのが始まりとされ、現在は徹底した無農薬で、こだわりの製法のお茶作りとしても知られている。
「久万茶」は、澄んだ空気や水で育った上浮穴郡久万高原町のお茶。また郡内の面河、美川、柳谷エリアを車で走っていると、あちこちで茶畑の風景に出会う。道の駅や直売所でよく目にする「美川茶」などもあり、霧深い高原は味のいいお茶の産地であることを教えてくれる。
山に囲まれた盆地が多い南予も茶どころとして多くの産地を持つ。西予市の「宇和茶」、松野町や鬼北町で作られる「鬼北(きほく)茶」などがそれだ。松野町、鬼北町あたりでは昭和中期から本格栽培が始まり、現在に至るという歴史文化も持っている。
 茶の木
茶の木
独特の色と香り
「石鎚黒茶」や「びわ葉茶」も話題
「石鎚黒茶」はその名の通り、石鎚山の標高600mの山間地区に古くから伝わる製法を受け継いだ西条市のお茶。茶葉を二度発酵させることにより、強い酸味と渋みを楽しめるお茶だ。独特の香りと発酵茶ゆえの黒い茶葉も珍しい。
 黒茶
黒茶
「びわ葉茶」は200年前からビワの産地として有名な伊予市唐川地区で作られている。そこで栽培されるびわ葉茶用の木は、果実を収穫せず葉に十分な栄養が行き渡るように育てているもの。煮出したびわ葉茶は、美しいワインレッドの色をしている。ほのかな甘みも感じる「伊予唐川特産びわ葉茶」は、愛媛県の「愛」あるブランド産品にも認定されている。
いずれも自分流で、ウィスキーやハチミツを加えたりと楽しむこともできそうだ。
 びわ葉茶
びわ葉茶
おいしいお茶をいれるために
お茶本来の香りを十分引き出すためには、お湯の温度がとても大切。100℃の熱湯を使うと良いのが「玄米茶」「ほうじ茶」。煎茶は旨み成分を引き出すため70℃~80℃、旨み成分をじっくり引き出したい「玉露」は50℃位の低温でゆっくりいれるのが基本。
「ゴールデンドロップ」と呼ばれる最後の一滴は、お茶の旨みや渋みが一番濃く出る大切な雫。最後の一滴まで絞り切って飲んでみると良い。
また、器もお茶の味を左右する大切な存在。あらたまったお客さまにはふた付き茶碗と茶托、お友達などの集まりには、茶托やコースターをカジュアルにして気楽に楽しんでもOK。
 あらたまったお客さまにはふた付き茶碗と茶托で
あらたまったお客さまにはふた付き茶碗と茶托で
家庭での保存方法
茶葉は開封後、いたみやすいので早めに使い切るように少量買いがおすすめ。どうしても保存する場合は、未開封であれば、そのまま冷蔵庫(もしくは冷凍庫)で。但し冷蔵庫から取り出した茶葉は常温に戻してから使うとよい。
開封後は密封容器に入れて冷暗所で保存する。冷蔵庫内の臭いを茶葉が吸収したり、湿気を吸収したりするので、冷蔵庫での保存は控えた方がいい。
また、古くなったお茶はフライパンに紙を敷いて茶葉を乗せ、弱火でゆっくりと煎ったり、電子レンジで温めると自家製ほうじ茶ができ上がる。香りを楽しむなら、1回ごとに煎って使うのがおすすめ。いい香りが家の中にも漂うので、気になる匂いを消す時にすれば一石二鳥。ぜひ、お試しを。
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう