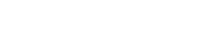伊予路に春をつげる
椿まつり

日本三古湯である松山の道後温泉は、古代、椿の樹が茂って温泉を取り囲んでいたと言われ、椿は道後温泉を象徴する花であり、松山市の市花にもなっている。椿は、伊予の人にとって身近な花として愛されており、椿と言えば、やっぱり「椿まつり」。伊予の人にとって「椿まつり」は切っても切れない特別な春の行事として敬愛され続けている。今回は、その「椿神社」の歴史やご利益などを紹介しよう。
「愛媛県」の県名の由来となった
愛比売命(えひめのみこと)も祀られる「伊予豆比古命神社」
「椿さん」「椿神社」の正式名称は、伊豫豆比古命神社(いよずひこのみことじんじゃ)。松山だけでなく多くの地域の人々から「椿さん」の愛称で親しまれている。
この伊豫豆比古命神社は、「縁起開運、商売繁昌」などの御利益があるとされ、創建から2300年ともいわれる歴史ある神社。椿神社と言われる名前の由来には諸説あるが、もともとこの近辺は、大昔は海で、「津(港)の脇」にあったことから「つわき」がなまりいつの間にか椿になった。あるいは、境内に生えている椿から椿神社として名付けられたという説もある。今でも境内には、椿が生い茂っており、季節によっては美しい姿で彩られる。
また伊豫豆比古命神社には、現在の愛媛県名の由来となった愛比売命(えひめのみこと)も祀られている。県名の由来となる神様が祀られているとなると、やはり愛媛県人には切っても切れない神社なのだ。

椿まつりでは3日間で数十万人も参拝。四国一の大祭り
伊豫豆比古命神社の春祭は、「椿まつり」「お椿さん」「お八日(おようか)」と親しみを込めて呼ばれ、「立春に近い上弦の月の初期」と月齢が定められている。この頃は、冬の厳しい寒さも峠を越し、芽吹きの頃で、農閑期も終りを告げ、椿まつりの終了後には田起し、種まきを始めることから「伊予路に春を呼ぶまつり」として、昔も今も、伊予の人は「椿まつり」を愛しく待ち焦がれているという由縁がある。
現在では、全国各地から毎年約50万人の参詣者で境内は3日間賑わい、参道には約800店もの露店が立ち並び圧巻だ。「椿まつり」は、初日の午前0時に大太鼓で開始を告げられて以来、最終日の24時迄72時間昼夜を徹する比類のないおまつりで、生活時間が多岐に亘る現在、参拝者が年々増加傾向にある。

商売繁盛の熊手などの縁起物も買い求めるのも楽しい
「椿まつり」期間中は、「縁起開運」「商売繁昌」「大漁満足」を祈る人々が数多く訪れ、境内の縁起物の露店に足をとめ、思い思いの縁起物を買い求めるのも参詣者の楽しみのひとつ。縁起物は、熊手、ざる、俵、宝船、扇の5つだが、買う順番がある。まずは熊手でお金をかき集め、次にザルで掬う。そして、俵に詰め、宝船に乗せ、扇で扇いで船を出すという順番。理にかなった理由があるのだ。宝船まで買ったら、次も熊手から同じ順番で少しずつ大きなものを選んで買う。くれぐれも初めから大きなものを買わないように。
もう一つ、椿さん名物は、おたやんあめ。金太郎飴のような形で、椿さんの顔がどこを切っても出てくる。お参りに行った方は必ず買う縁起物だ。
平成30年 椿まつり 2月22、23、24日
平成30年の椿まつりは2月22日(木)、23日(金)、24日(土)。平成31年は、2月11日(月)、12日(火)、13日(水)だそうだ。松山の春の訪れを知らせる椿さん。とはいえ、まだまだ寒い時期なので、参拝は暖かくして出かけたい。
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう