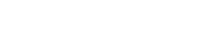俳句にチャレンジ
今の気持ちを五・七・五に
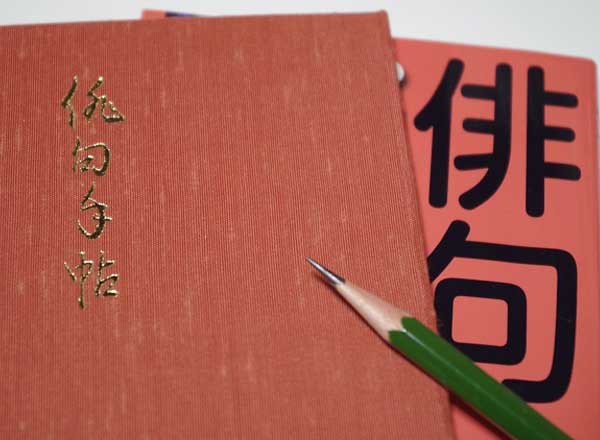
俳聖・正岡子規を輩出した、ここ愛媛県は俳句に親しむ人が多く、最近では若い年齢層にも人気が広まっている。俳句の魅力は、何と言ってもペンと紙さえあれば、誰でも作ることができる手軽さと、自分の身の周りに広がる自然や出来事すべてが題材になること。リビングカルチャー教室・俳句講座講師・俳誌「花」主宰の有光令子先生に、初心者向けの楽しみ方をお聞きした。
感動を文字にしてメモする
とっかかりは出来映えにこだわらず、自分が感動したことを素直に詠んでみること。
考えるのではなく、見たこと、感じたことを忘れないうちに、形(文字)にすることから始めよう。
朝夕の通勤途中や、家事の合間でも「わあ、きれい」「あれ、今日はなにか違う」と、気づいたことを、単語でいいので、書き残しておく。普段からメモ帳と鉛筆を持ち歩くようにしよう。

歳時記を友達にする
俳句の約束事は、基本的には五・七・五の定型詩に、季節の言葉『季語』が入ること。季語の数は五千を超えるといわれ、例えば『春の雪』ひとつを見ても。春雪、淡雪、綿雪、春吹雪、牡丹雪などいろいろある。
俳句を始めるなら、まずは『歳時記』という季語を集めた本を手元に用意して、自分の感動を託せる季語を選んでみよう。
歳時記には季節を表す言葉があふれていて、日本語の持つ美しい響きや、豊かさ、奥深さも楽しめる。
歳時記
★春(2・3・4月)
春浅し、余寒、猫の恋、霞、猫柳、梅見、闘牛、雛祭り、山笑ふ、啓蟄、椿、水温む、蜆、杉の花、花曇、磯遊び、バレンタインデー、囀(さえず)り、春の海、汐干狩、風光る、蝶、風船、遍路、春惜しむ

★夏(5・6・7月)
牡丹、更衣、新緑、若葉、紫陽花、薔薇、花水木、薪能、祭、風薫る、新茶、黴(かび)、玉葱、琵琶、昼寝、燕の子、蛍、麦の秋、蝉、花火、金魚草、夏木立、網戸、半夏生、噴水、ラムネ
★秋(8・9・10月)
桐一葉、月、星月夜、盆の月、十三夜、十六夜、流星、蜩(ひぐらし)、鳳仙花、花野、法師蝉、西瓜、新涼、芒(すすき)、桔梗、萩、蟋蟀、芋、鰯雲、秋高し、爽やか、肌寒、初紅葉、茸、新米、新酒、案山子、運動会、秋祭、在祭

★冬(11・12・1月)
初旅、新年、初日、初霜、鷹、初時雨、山茶花、七五三、小春、冬日和、枯葉、短日、水鳥、初氷、息白し、梟、枯木立、冬ざれ、冬芽、風呂吹、葱、白菜、熱燗、咳、去年今年、凩、風邪
五・七・五に季語を入れて作ってみる
「こんにちは」「さようなら」「おやすみなさい」など五音と七音は日本人が慣れ親しんでいるリズム。感動した時の言葉を、リズムにあてはめてみよう。1音・2音少なくても多くても大丈夫。
この時に、景色が見えてくるような言葉を選ぶことがポイント。最初は五音の季語を選んでから、詠んでみるのもいい。
例)秋の季語 いわし雲(いわしぐも)で
(添削前)あと2日宿題せかすいわし雲
※「せかす」という言葉では情景が浮かびにくい
(添削後)宿題の写生仕上がるいわし雲
※夏休みの終わりに間に合った宿題の絵が思い浮かぶ句に

投句に挑戦する
俳句を楽しみ始めたら、自分の作品がどんなものか腕試しをしたくなるもの。思いきって投句してみるのもおすすめ。
松山市には、昭和41年の「子規・漱石・極堂生誕百年祭」の記念事業をきっかけに、観光俳句ポストが約90カ所に設置されている。散歩やお出かけの途中に、一句ひねって投句してみよう。
また、インターネットで俳句を投稿できるサイトもある。隔週で新しいお題が出て、選者が優秀句を選んで紹介している。
 花園町にある松山市観光俳句ポストと正岡子規誕生邸址
花園町にある松山市観光俳句ポストと正岡子規誕生邸址
出会いが広がる句会
俳句は一人で楽しむのも良いが、仲間がいると更に楽しくなる。自分の作品を他の人にも共感してもらいたいと思ったら、『句会』に参加してみては。
句会では最初に、集まった人たちが書いてきた句を無記名で短冊に書いて提出する。次に参加者の俳句を手分けして清書し、回し読みし、気に入った句をそれぞれが選句用紙に書き写す。その後、和気あいあいとした講評タイムで楽しく交流を深めよう。俳句は句会で学び、句会で育つと言われる。
俳句で心にゆとりを
俳句を始めると、今まで何気なく見ていた風景が、生き生きとして映り、新鮮な発見が増える。
時間に追われる毎日も、たった5分間でもノートに思いつく言葉を書くことで自分の時間が持て、自然や植物に眼差しを注ぐ心のゆとりができる。旅先で見た風景や料理の感激を、その時の気持ちまで残すことができる。病気や別れなど辛い出来事も、俳句にすると、客観的に自分を見つめ直すことができ、心が楽になる。などなど…。
俳句の楽しみ方は人それぞれ。さあ、あなたも早速、今の気持ちを五・七・五にしてみてはいかがだろうか。
関連リンク
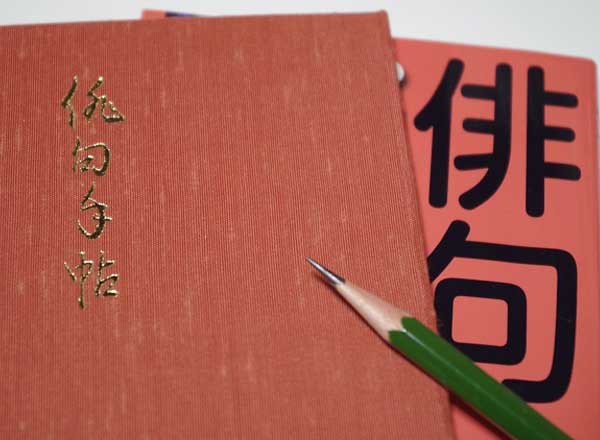
この記事が気にいったら
シェアしよう