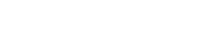“和の花”にこだわった
道後公園の花トリビア
道後公園をゆっくり散策すると、日本古来の草花が多いことに気がつきます。道後公園管理事務所事務長の田中哲也さんによると、道後公園の南側は、河野氏の居城・湯築城があった時代(14世紀~16世紀)の植生を復元しているとのこと。時代考証し、中世から存在していたと思われる植物だけが植えられています。
平成14年に国史跡に指定されてからは、北側のエリアも草花の植栽に配慮しています。また、外来種の伐採や眺望に配慮した剪定を行っています。
展望台がある丘陵の西側には、藪椿(ヤブツバキ)を中心に数種の椿が点在しています。ここに「椿の小径」を作ろうと、伊予つばき協会が接ぎ木を進めています。椿の花を愛でながら、のんびり散策できる日が楽しみですね。
●春

雪柳(ユキヤナギ) 3月中旬~4月中旬
柳に似た葉、雪を思わせるような小さな白い花から名前がついたとされる。

染井吉野(ソメイヨシノ) 3月下旬~4月中旬
道後公園には、松山地方の染井吉野の開花宣言や開花状態の観測に使われる標本樹がある。

源平花桃(ゲンペイハナモモ) 3月下旬~4月上旬
1本の木に、紅・白・絞り模様の花が咲く様子を、源平合戦に見立てて名付けられた。

躑躅(ツツジ) 4月中旬~5月上旬
『万葉集』にも登場。江戸時代に盛んに品種改良され「本霧島」「大紫」など多くの園芸品種が誕生した。
●夏

睡蓮(スイレン) 5月上旬~10月上旬
道後公園の内堀に、黄色と白色の2種が咲く。鑑賞は午前中がおすすめ。

紫陽花(アジサイ) 5月中旬~6月下旬
梅雨といえばこの花。色は土壌の酸性度で変わる。酸性では青く、アルカリ性になるほど赤くなる。

桔梗(キキョウ) 6月下旬~10月中旬
「秋の七草」のひとつ。『万葉集』の中では「あさがお」の名前で歌われる。

女郎花(オミナエシ) 7月下旬~10月中旬
「秋の七草」のひとつ。別名「オミナメシ」は、女郎花に似た黄粒の粟飯を“女飯(おみなめし)”と呼ぶことから。
●秋

玉簾(タマスダレ) 9月上旬~10月中旬
小さな花を「玉」にたとえ、密集して生える円柱状の細長い葉を「スダレ」に見立てて命名されたとか。

金木犀(キンモクセイ) 10月上旬~下旬
松山の秋祭りが始まる頃に、甘く良い香りを漂わせる、秋の花の代表格。

藤袴(フジバカマ) 10月上旬~11月上旬
川岸などで見られる「秋の七草」のひとつ。自生できる環境が激減しており、いまや貴重な植物だ。

紅葉(モミジ) 11月上旬~下旬
「いろは紅葉」のほか、葉が似た「台湾楓(かえで)」「紅葉葉(もみじば)カエデ」も紅葉する。
●冬

南天(ナンテン) ※実の色づき 10月下旬~1月下旬
「難を転じる」ことから、厄除けや魔除けとして昔からよく庭木にされてきた。

椿(ツバキ) 11月下旬~4月中旬
松山市の市花。光沢と厚みのある葉が名前の由来という説が多い。写真は乙女椿。

沈丁花(ジンチョウゲ) 2月中旬~3月下旬
芳香が春の訪れを告げる常緑樹。室町時代以前に中国から伝わったとされる。

梅(ウメ)
新元号・令和は、『万葉集』巻5、大伴旅人の「梅花歌三十二首」序文から選ばれた。
えひめリビング新聞社発行「リビングまつやま」抜粋
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう