イデコプラスはどんな制度?
仕組みや導入のメリットを知って福利厚生を充実させよう
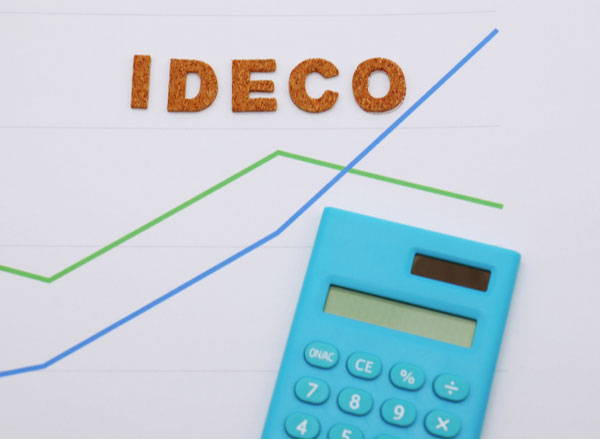
老後資金対策として、個人で行うiDeCoが有効であることは随分浸透してきました。では、iDeCo+(イデコプラス)という制度はご存じでしょうか?イデコプラスは、事業主が主に福利厚生の一環として導入する制度であり、節税対策としても注目されています。今回は、このイデコプラスの概要やメリットについてまとめていきます。
iDeCo+(イデコプラス)とは

iDeCo+(イデコプラス)とは、正式名称を「中小企業主掛金納付制度」といいます。従来のiDeCoは個人が対象で、自分の老後資金のために自分で掛金を支払います。この点、イデコプラスは事業主(会社)が掛金を拠出します。
イデコプラスの概要(制度・対象など)
まずはイデコプラスの概要について、制度の内容および制度の対象を解説します。
制度の内容
イデコプラスとは、福利厚生の一環として活用できる制度です。これまで個人で加入していたiDeCoに、事業主(会社)が掛金を上乗せする仕組みです。イデコプラスのメリットについて詳細は後述しますが、事業主にとっても従業員にとっても、どちらにもメリットがあります。
イデコプラスの対象
イデコプラスは、確定給付企業年金などの企業年金を実施していない、従業員数300名以下の中小企業の事業主が対象です。また、制度の実施については、労働組合や従業員の過半数の同意を得ることも前提となります。
掛金の設定
イデコプラスの掛金は、加入者掛金(従業員が負担する掛け金)と事業主掛金の合計額が月額5,000円から23,000円の間で、1,000円単位で設定できます。
事業主が負担する掛け金は、従業員の掛け金より多くても少なくても問題ありません。ただし、従業員の掛け金が0円で、事業主だけが掛け金を拠出することはできません。
iDeCoはあくまで任意加入
イデコプラスを導入している会社でも、iDeCoを利用していない従業員は強制加入とはなりません。勤務している全従業員が対象にはなりますが、個人でiDeCoに加入するかどうかはあくまでも任意です。つまり、イデコプラスを導入している会社に勤務し、iDeCoを利用している人が対象者ということになります。
企業年金との違い
イデコプラスと企業年金(企業型確定拠出年金)は、どちらも会社と従業員が掛金を拠出するという点では同じです。決定的な違いは、運用管理手数料等の諸経費をだれが負担するかという点と、運用結果の責任をだれが負うのかという点です。
運用管理手数料の違い
企業年金では、運用管理手数料は会社負担です。つまり、企業年金では事業主が主体となり、従業員の福利厚生のために運用しているようなイメージです。
一方、イデコプラスの主体は従業員です。会社は掛金を上乗せしたり、上乗せ分も含めた掛金を給与天引きで納めたりしますが、運用管理手数料等の諸経費は全て従業員が負担します。
運用結果の責任の違い
企業年金では、掛け金の拠出および運用について会社が責任をもって行います。もし運用結果が悪ければ、会社が不足分を穴埋めするということもあります。
一方、イデコプラスでの会社の役割は掛金を上乗せすることのみであり、大元となるiDeCoの運用結果は従業員本人の責任になります。つまり、会社は運用結果までは責任を負わないということです。
イデコプラスを導入するメリットとは?

イデコプラスを導入すると、従業員側、事業主(会社)側双方にとってメリットがあります。それぞれどのようなメリットがあるのかをまとめていきます。
従業員側のメリット
給与天引きで便利に拠出できる
個人で運用する場合は、従業員自らがiDeCoの掛金を金融機関に納めなければなりません。しかし、事業主がイデコプラスを導入している場合は、原則として給与天引きで自動的に拠出されます。つまり、個人単位で掛金を納める手間が省け、効率よく老後資金を形成できます。
事業主側のメリット
掛金は全額損金算入できる
事業主が負担するイデコプラスの掛金は全額を損金算入できるため、事業主にとっては大きな節税効果が得られるでしょう。また、企業年金を自社で運用するよりも手数料などのコスト面を低く抑えられるため、経費削減という面でも大きなメリットがあります。
福利厚生を拡充でき、人材確保につながる
福利厚生が充実している会社かどうかは、就職や転職の際に会社を選ぶポイントの一つです。イデコプラスを導入すれば、福利厚生が充実していることを求人票や広告で対外的にアピールでき、新たな人材の確保につながります。
また、すでに勤務している従業員のモチベーション向上も期待できるため、退職者を減らす手助けにもなると推測されます。
イデコプラスを導入するための手続き

イデコプラスを導入するためには、事業主が行わなければならない手続きがいくつかあります。
イデコプラス開始の届出
まず、イデコプラスを開始するためには関係先に届出が必要です。「中小事業主掛金納付開始・終了届」を国民年金基金連合会に提出します。
また、地方厚生局への届出も行わなければなりません。これは、新規加入の従業員が発生した場合や従業員が退職した場合などに、その都度届出が必要です。
登録事業所番号の付与
イデコプラスでは、個人のiDeCoの掛金と、事業主が負担する上乗せ分の掛金をまとめて事業主が納付します。そのためには「登録事業所番号」が必要です。事業主が国民年金基金連合会へ「登録事業所届」を提出することで、番号が発行されます。これをもって、毎月事業主の口座から掛金を納付することができます。
イデコプラスに関するまとめ
イデコプラスは事業主と従業員どちらにとってもメリットが大きい制度です。自社がイデコプラスを導入した場合、どれくらいメリットがあるのか検討してみてはいかがでしょうか。導入する際は、労働組合や従業員の過半数の同意を得ることが前提です。イデコプラスの制度の概要をあらかじめ把握し、スムーズに導入できる下準備をしておきましょう。

金融業界歴10年目、お金と不動産の専門家。生命保険、損害保険、各種金融商品の販売を一切行わない「完全独立系FP」として、プロの立場から公平かつ根拠のしっかりしたコンサルティングを開催している。







