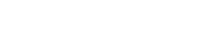これで分かる!遺産相続
手続きとスケジュールを徹底解説

相続はそう何度も経験することではありません。大切な方を失った悲しみが冷めないうちから着手しなければならない手続きが多く、時間的余裕もないため、何かと不安を感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、できるだけ遺産相続をスムーズに進められるよう、手続きの流れやポイント、延納や物納の条件、生前贈与との違いについて解説します。
目次
■遺産相続の手続きの流れ
・公的年金
・健康保険・運転免許証・パスポートの返納
・死亡保険金の請求
・公共料金等の引き落とし口座の変更など
・遺言書の有無を確認する
・相続人の調査・確認
・相続財産の調査
・単純承認・相続放棄・限定承認の選択
・準確定申告
・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記や各種解約・名義変更
・相続税申告書の作成、相続税の申告・納付
■相続税の「延納」と「物納」について
・「延納」の条件
・「物納」の条件
■生前贈与と相続はどちらが得になる?
■専門家へ依頼する際の注意点
■「備え」を万全にするとスムーズな相続ができる
遺産相続の手続きの流れ
遺産相続の手続きは、お亡くなりになった時点で速やかに対応しなければならないものから、比較的猶予のあるものまで多岐に渡ります。相続の手続きは煩雑で、悲しみから立ち直る暇もないほど忙しくなり、遺産相続の流れを知らなければ焦りが募るもの。以下に相続の流れを紹介しますので、いざというときのためにお役立てください。
なお、ここでは遺産を相続する方を「被相続人」、遺産を受け取る方を「相続人」と呼んでいます。
| 手続きの目安・期限 | 手続きの詳細 |
|---|---|
| 7日以内 |
|
| 厚生年金:10日以内 |
|
| 国民年金:14日以内 |
|
| 年金支払い日の翌月(初日)から5年以内 |
|
| 速やかに(1ヶ月以内を目安に) |
|
| 3ヶ月以内 |
|
| 4ヶ月以内 |
|
| 速やかに |
|
| 10ヶ月以内 |
|
| 1年以内 |
|
| 2年以内 |
|
| 5年以内 |
|
公的年金
厚生年金の場合はお亡くなりになってから10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所へ連絡し、年金給付停止の手続きを行います。
健康保険・運転免許証・パスポートの返納
健康保険は、もし国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合には、お亡くなりになってから14日以内に市区町村に保険証を返納します。故人が会社の健康保険に加入されていた場合は、勤務先に連絡し、手続き方法を確認してください。運転免許証とパスポートの返納も忘れないようにしましょう。
死亡保険金の請求
故人が生命保険に加入されていた場合には、保険会社に連絡を取って死亡保険金を受け取ります。連絡の際には、証券番号がわかるものを用意しておくと手続きがスムーズです。
公共料金等の引き落とし口座の変更など
もし故人の口座で公共料金の引き落としなどを行っている場合は、口座の変更が必要です。電気、ガス、水道、インターネットなどの通信費については、契約の変更か解約手続きを行います。
遺言書の有無を確認する
まずは、できるだけ速やかに遺言書の有無を確認しましょう。もし有効な遺言書があった場合は、遺言書に則って相続の手続きを進めなければならなりません。なお、遺言書がなくても進められる手続きはありますので、公的年金・保険証・口座の対応を進めながら、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言
被相続人が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が作成・管理を行うため、遺言に効力を持たせることもできますし、偽造される心配もありません。
もし相続が発生したら、公証役場で公正証書遺言の原本閲覧や正本・謄本(写し)の交付を請求可能です。遺産相続が発生した場合は、公証役場で遺言の有無・内容を速やかに確認できるという利点があります。なお、被相続人の生前は、遺言の内容はもちろん遺言の有無さえ確認はできません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、紙とペンで気軽に作成できる遺言書です。ただし、印鑑または拇印や指印による捺印が必要で、パソコンやタイプライターでの作成は無効になります。法務局に預ける場合は1件3,900円と公正証書遺言より安いという利点があります。ただし、相続人が発見した遺言書が「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所を通して「検認」の手続きが必要です。検認前に開封しても効力に影響はありませんが、家庭裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料(刑罰ではない金銭罰)に処されることもありますのでご注意ください。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にして、存在だけ公証役場で証明してもらった遺言書のことです。公証役場で保管せず、自身で管理する必要があります。現在では公正証書遺言でも内容を秘密にするため、ほとんど用いられなくなった遺言方法です。自筆証書遺言と同様に「検認」の手続きが必要となるため、秘密証書遺言を見つけても開封してはいけません。申立書・相続人全員の戸籍謄本を用意し、家庭裁判所を通して遺言書を閲覧してください。
相続人の調査・確認
遺言書が存在しないか、遺言書があっても遺産分割の方法が決まらない財産がある場合は、相続人同士で協議をして分割方法を決定しなければなりません。そのためには、まず相続権のある人物の調査を行う必要があります。法定相続人が揃わないまま協議を行った場合、そこで合意したことは無効になるからです。
相続人の確定方法は、被相続人の戸籍謄本をすべて集めて、両親・子ども・兄弟など相続人になりうる人物を絞ります。ここで、もし相続人が亡くなっている場合は、その方の相続者が誰かを特定します。戸籍を取得するのはかなり時間がかかりますので、調査を専門家に依頼するのも一つの手段です。自分で行うにしても依頼するにしても、相続人が決まらないと協議が進められないので、できるだけ早めに相続人を確定させておきましょう。
相続財産の調査
相続人を確定させることも大切ですが、相続財産を確定させることも同じくらい大切です。相続人の調査と並行して、相続財産の調査も行います。相続財産には、預貯金、不動産、金銭債権などプラスになるもの以外にも、借金・住宅ローン・未納分の税金といったマイナスの財産も存在するからです。マイナスの財産が多くて負担しきれない場合には、「相続放棄」を選ぶこともできます。なお、財産は以下のような書類で確認可能です。
- 貯金:銀行で残高証明書を発行してもらう
- 不動産:権利書・登記識別情報・固定資産税の納付書
- 有価証券:評価証明書を発行してもらう(証券会社)
- 自動車:車検証
- 借金:金融機関でローンの明細書・契約書
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
財産を相続するかどうかの決定は相続人に一任されており、権利・義務を引き継ぐかどうかについては以下の3つの選択肢が用意されています。
- 単純承認:すべての権利・義務を引き継ぐ
- 相続破棄:相続可能な権利・義務のすべてを放棄する
- 限定承認:プラスの財産によってマイナスの財産を精算し、余った分があれば引き継ぐ
もし被相続人の抱えている借金や住宅ローンの債務といったマイナスの財産が多い場合は、早めに「相続放棄」や「限定承認」を選ぶほうがよいでしょう。なぜなら「相続放棄」や「限定承認」を選択する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行わなくてはならないからです。そうしなければ、自動的にすべてを相続するとみなされてしまいます。
準確定申告
被相続人が個人事業主や一定以上の副収入があるといった理由で「確定申告」を行っていた場合に発生する手続きです。ご本人が亡くなると確定申告ができなくなるため、代わりに相続人が確定申告をしなくてはなりません。これを「準確定申告」と言います。
準確定申告は、相続が発生した次の日から4ヶ月以内に申請および納税をする必要があります。確定申告をしなくてもよい方もいらっしゃいますが、申請することで所得税の還付があるかもしれません。他の手続きよりも煩雑な処理が必要であるため、早めに税理士に相談しておくとよいでしょう。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
もし遺言書がない場合は、どのように相続を行うかを記載した「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。相続人と相続財産が確定したら、速やかに遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。遺産分割協議はすべての相続人から合意がないと成立しません。後回しにすると相続財産に変動があったり相続人が増えたりと思いもよらない事態に陥りやすいため、速やかに対応することをおすすめします。
不動産の相続登記や各種解約・名義変更
遺産分割協議が成立したら、次は解約・名義変更を行います。解約・名義変更が必要なものは、不動産や各種権利、預貯金や有価証券などです。遺産分割協議書がないと不動産の相続登記や金融機関で行う解約・名義変更ができません。また、金融機関については財産の引き継ぎ時に相続人全員の著名・押印が必要になるので、遺産分割協議が成立したら相続人全員でスケジュールの調整を行いましょう。
相続税の申告・納付
相続する財産が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも上回るようであれば、相続税の納付手続きが発生します。納付の期日は相続が発生した翌日から10ヶ月以内と決まっているので、それまでに法定相続人と相続財産を決め、相続方法について合意を取り、相続額を算出しておかなくてはなりません。専門家の力も借りながら、早めに相続の手続きを進めておくことが大切です。
相続税の「延納」と「物納」について
相続税は、原則として期限までに現金で一括納付しなければなりません。しかし、期限までに現金を用意できないと認められた場合には、特別措置として「延納」か「物納」を選択できます。ただし、「延納」や「物納」を選ぶには、相応の条件があります。一括納付をしても生活や事業に差し障りがないとみなされた場合は延納が認められず、一括納付しなくてはなりません。
「延納」の条件
「延納」とは、相続税を分割払いする方法で、以下の4つの条件を満たせば認められます。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません)
- 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納を検討される場合は、延納期限(相続税発生を知った日の翌日から10ヶ月後)を過ぎないよう注意しましょう。担保は相続人の財産に限らず、第三者が所有する財産であっても問題ありません。
「物納」の条件
手持ちの現金が少なく、相続税を収めると生活に支障が出かねない場合は、土地・建物の不動産や株式など現金以外の財産で納付をする「物納」の申請が可能です。物納を選ぶには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
- 延納をしても現金で納付が難しい理由があり、納付困難な金額のみ物納ができます。
- 物納を申請できる財産は、納付するべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、下記の順位(①~⑤の順)で、その所在が日本国内にあるものに限ります。
① 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等② 不動産・上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの③ 非上場株式等④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの⑤ 動産
- 「管理処分不適格財産(管理・処分に向かない財産)」に該当しないものが物納として認められます。また、「物納劣後財産(物納に向かない財産)」である場合は、他に適当な財産がない場合に認められます。
- 物納する場合は、相続税の納期限または納付すべき日までに「物納申請書」に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出しなければなりません。
物納財産には順位が決められており、例えば土地を持っているのに株式から先に物納することはできません。担保権がついている・争いが発生している・境界があきらかではないなど、管理・処分に向かない財産は「管理処分不適格財産」として物納が認められないので、物納を検討される際には改めて物納財産の条件を確認しておきましょう。
生前贈与と相続はどちらが得になる?
次の世代へ財産を残す方法は、本人が亡くなった後で行う「相続」と、本人が存命のうちに行う「生前贈与」があります。それぞれに税がかかるので、できればより税金が少ない方法を採用したいものです。税率だけを見ると、「相続」のほうが「生前贈与」よりも低いため、「相続」のほうが支払う税金が低く見えます。しかし、単純に税率だけで比べることはできません。なぜなら、「相続」は亡くなったときにすべての財産を一度に渡しますが、「生前贈与」では、すべての財産を一度に渡すことはほとんどないからです。
| 【贈与】課税価格 | 贈与税の税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 25万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 125万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 250万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 250万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 400万円 |
| 【相続】取得金額 | 相続税の税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率が高く設定されている「生前贈与」には非課税枠があります。年間110万円以内の贈与については贈与税が課税されません。つまり、毎年110万円ずつを贈与すれば、10年後には1,100万円分の財産を非課税で次の世代へ引き渡せるということです。この方法には時間がかかるという点で、相続税対策として検討される場合は、早めに贈与をスタートさせたほうがよいでしょう。
ただし、生前贈与が得になるとは限りません。もし不動産を贈与する場合は、贈与税に加えて不動産取得税や登録免許税が課税されるため、負担が大きくなってしまうこともあります。また、相続税では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が適用され、戸建て住宅やマンションの一室を相続する場合は非課税枠に収まる可能性が高くなるため、わざわざ贈与を選ぶメリットは薄いでしょう。
もし将来的に評価額の上がる見込みがある不動産をお持ちであれば、生前贈与を検討してもよいかもしれません。しかし、生前贈与する財産によっては損をしてしまうことも考慮したうえで、譲渡方法を選ぶ必要があります。
なお、令和3年税制改正大綱にて、贈与税等の制度の見直しについて検討を進めていく旨の言及がされております。将来的に相続税・贈与税の考え方が変更となる可能性がありますので、実際に検討する際にはその時点の状況を確認のうえ、検討するようにしてください。
専門家へ依頼する際の注意点
相続の際は複雑な手続きが多いので、相続が発生したら専門家に依頼することをおすすめします。専門家を選ぶ際には、以下の2点に注意することが大切です。
- 相続を一括対応してくれるか
- 相続の知識・経験が豊富か
1つ目の「相続を一括対応してくれるか」を考慮していないと、司法書士・行政書士・土地家屋調査士など個別に専門家の元へ自ら足を運び、同じ話を何度も繰り返さなくてはなりません。そのため、各専門家と提携していて、相続をワンストップで対応してくれる専門家もしくは会社や機関を選ぶことでスムーズな相続手続きができます。
2つ目の「相続の知識・経験が豊富か」については、税理士・弁護士・司法書士だからといって相続を頻繁に扱っているとは限らないためです。特に相続税は税理士によって相続額が千差万別になると言われるほど手続きが複雑であるため、慣れていない専門家に依頼すると節税のチャンスを逃すことになりかねません。その専門家が相続を得意としているかどうかは必ずチェックしてください。
相続登記だけお願いする場合は司法書士、相続税の申告まで依頼するなら税理士、もし遺産相続をめぐって争いが起こりそうなら弁護士に依頼するとスムーズに相続手続きが進められます。専門家に依頼する金額は決して安いとは言えないので、上記のポイントを鑑みながら慎重に選びましょう。
「備え」を万全にするとスムーズな相続ができる
ご自身で相続手続きのやり方やスケジュールを把握しておくことも大切ですが、相続手続きは専門的な知識を有していないと判断が難しいものも多く、手間と時間もかかります。手続きを行うために連絡を取る機関は市区町村の役場、税務署、法務局、年金事務所、金融機関など多岐に渡るうえ、亡くなって10ヶ月後にはほとんどの対応を済ませておかなくてはなりません。
大切な方が亡くなった状況で、急を要する複雑な手続きを進めると、抜けや漏れが発生する可能性もあります。そのため、相続が発生した場合は、相続の専門家へ依頼するのが安心です。もしもの時のために、相続が発生する前に専門家と相談しておくことで「生前贈与」という選択肢も増えるので、節税の幅も広がります。
伊予銀行では、「まごころレター」という遺言代用信託をご用意しています。こちらは遺言の代わりに用いる信託で、誰にどれくらいのお金を残すのかをあらかじめ指定できる仕組みです。もし被相続人の体力が衰えて自身で現金を引き出すことが難しくなっても、ご家族が医療費や介護施設の入居費支払いのために信託を引き出せますし、もし相続が発生しても、スムーズに財産をお受け取りできます。
また、伊予銀行では「遺言書」、「遺産分割協議書」、「調停調書」、「審判書」で相続を行う場合の相談も受け付けておりますので、相続の手続きにお困りの方、遺産相続に備えておきたい方は、お取引店までお気軽にお問い合せください。
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう