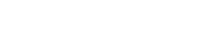妊娠・出産・子育て支援の基礎知識
各フェーズで受けられる支援を解説

国や自治体では、妊娠・出産・子育てのためのさまざまな支援制度を設けています。その内容は、経済的支援策だけではなく、労働の場における子育て支援や母子保健・学校保健など多岐に渡っています。しかし、その存在を知らずに支援の手からこぼれおちている家庭も少なくありません。この記事では、公的な妊娠・出産・子育て支援策について紹介します。これから子育てに臨まれる方も、すでに子育て中の世帯も、ぜひ参考にしてください。
目次
妊娠・出産時の支援
妊娠・出産は家族の一大イベント。初めて妊娠・出産を経験する家族もそうでない家族も、安心して赤ちゃんを迎えるために、健診や必要な準備、金銭面での不安を解消しておきたいところです。ここでは、妊娠・出産で役に立つ公的支援についてご紹介します。
妊婦検診の助成
妊婦は疾病ではないため、妊婦検診も基本的に保険適用外ですが、国からの助成制度があります。安心・安全な出産のために必要な検診は14回。すべての市区町村では、必要最低限の妊娠検診14回分についてはどこでも助成が受けられます。それ以上の助成については自治体によって差があるため、各自治体の公式ホームページに記載があるので確認してみましょう。
出産手当金
出産手当金とは、妊娠した女性が出産のために勤め先を休む場合に支給される手当です。健康保険の加入者である被保険者のみとなりますが、妊娠・出産によって会社を休み、事業者から給与の支払いを受けなかった場合には、申請によって出産手当が支給されます。
支給額は月給・日給の3分の2相当額です。もし妊娠中に仕事をしていて給与を受け取っていたとしても、従来の3分の2に満たない場合は差額が支払われます。期間は98~154日間。「出産日(出産が遅れた場合は出産予定日)」以前42日(双子以上は98日)から、出産日の翌日以降56日の範囲内です。
出産育児一時金
出産は病気やケガにはあたらないため、基本的に健康保険を使えず自己負担となります。ただし、出産については健康保険から助成金が支給され、これを「出産育児一時金」といいます。妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産したとき、健康保険加入者か配偶者の健康保険の被扶養者であれば、子ども1人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。
妊娠・出産包括支援事業
妊娠・出産から子育てまでワンストップで行う「子育て世代包括支援センター」は、全体の7割を超える自治体が整備を進めている支援施策です。家庭や地域内での孤立感を解消するため、助産師などの専門職による相談支援を行う「産前・産後サポート」や、退院直後の母子のケア・育児サポートなどの支援を行う「産後ケア」の支援も提供しています。
確定申告による医療費控除
1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超える場合は確定申告で医療費控除ができますが、妊娠・出産も医療費控除に該当します。確定申告を行うことで、納税額を下げることはもちろん、場合によっては過払い金を還付してもらうことも可能です。
申告できるのは妊婦健診や出産費用だけに限らず、通院・入院時に利用するタクシー代も含まれます。通院費は家計簿に記録したり領収書や明細を取っておいたりして、かかった費用についてしっかり説明できるようにしておきましょう。
ただし、対象となるのは自費で支払った金額と、やむなく利用した費用だけです。入院時の日用品や外食費、実家で出産するための帰省にかかった費用などは医療費控除の対象になりません。詳しくはこちらの国税庁の公式ホームページ「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」をご確認ください。
参考:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
子育て中の支援
子どもが生まれてからしばらくすると、仕事と育児の両立に悩んだり、子どもの教育費の工面に頭を抱えたり、しつけのやり方に迷ったりと悩みが尽きないものです。ここでは、そんな子育て中に使える公的支援についてご紹介します。
育児休業給付金
「育児休業給付金」とは、育児休業中に国から支給される給付金のことを指します。育児休業・介護休業法では子どもの養育義務を持つ労働者に育児休業の権利が保障されており、母親だけではなく父親も休業を取得できます。ただし、母親と父親で育児休業期間が異なります。
母親の場合は、産後休業期間(産後8週間以内)が終了した翌日から、子どもが満1歳になる前日までが該当します。父親の場合は産後休業期間がないので、子どもの出生当日から満1歳の前日までが育児休業期間です。夫婦が同時に取得した場合は、それぞれに給付金が支給されます。子どもを預ける保育所が見つからないなどの理由で仕事への復帰が困難な場合は、1歳6ヶ月の時点で最大2歳まで延長可能です。
育児休業給付金は、育児休業開始から180日間は月給相当額の67%を支給し、181日目からは月給相当額の50%が支給されます。限度額は毎年8月1日に見直されており、令和3年8月1日時点では、180日間の限度額は30万1,902円、181日以降の限度額は22万5,300円です。
育休は原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までしか取得できませんが、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用することで育休期間を延長できます。2010年に制定されたパパ・ママ育休プラスは、共働きの夫婦がともに育休を取得することを条件に、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる制度です。ただし、育休期間が延長されるのは後から育休を取得した配偶者のみ。母親が先に育休を取得した場合、1歳2ヶ月まで育休を延長できるのは父親です。父親が先に育休を取得することで、母親の育休を1歳2ヶ月まで延長することも可能です。
社会保険料の免除
育児休業中には、勤め先の会社申請により社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除が認められ、この期間中は健康保険料を納付したものとして扱われます。
また、産休・育休を取得していなくても、子育てのために時短勤務を選ぶなどの理由で養育前より月給が下がってしまったという方もいらっしゃるでしょう。納付する社会保険料は給料に合わせて決まるので支払額は減少しますが、支払う厚生年金の額が低いと将来受け取る年金額が減ってしまうこともあります。そのため、3歳未満の子どもを育てている労働者は、「養育期間の従前標準月額のみなし措置」を適用できます。これは、社会保険加入者である被保険者本人が事前に申請することで、子どもが3歳になるまで「減給前の給与水準に応じた年金給付が保証される」という特例です。
共働きで父親・母親ともに条件を満たしている場合は、それぞれが措置を申し出ることも可能です。詳しくは、こちらの日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご覧ください。
参考:厚生労働省リーフレット
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
国民年金保険料の免除
2019年4月から、国民年金だけに加入している方やその家族など第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されることになりました。所得制限はなく、出産予定日の6ヶ月前から免除の届出が可能です。免除期間は国民年金の保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。なお、出産とは妊娠85日(4ヶ月以上)の出産を指し、死産・流産なども含みます。
児童手当
児童手当は、0歳から15歳までの子どもを養育している世帯に支給される手当です。子どもの人数に応じて支給され、支給額は以下の通りです。児童手当は毎月支給されるわけではなく、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給する仕組みです。例えば、6月時点で中学生1年生の子ども(第1子)がいる場合は、小学校修了前の2~3月分、中学生の4~5月分の合計5万円が支給されます。
| 児童の年齢 | 児童手当の金額(1人あたり) |
|---|---|
| 3歳未満 | 1万5,000円/月 |
| 3歳から小学校修了前 | 1万円(第1子・第2子)/月、1万5,000円(第3子以降) |
| 中学生 | 1万円/月 |
児童扶養手当
離婚・死別などの理由で父親や母親と生活をともにできなくなった児童を養育する世帯に支給される手当です。ここでいう「児童」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある子どもが該当します。児童本人が心身に中程度の障害を持つ場合は支給期間が延長され、20歳になるまで手当が受けられます。
外国人にも支給されますが、その場合は養育者・児童ともに日本国内に住所を持っている必要があります。また、遺族年金・労災年金など労働基準法の規定による遺族補償を受け取っている場合は支給されませんが、公的年金の年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の手当を受け取れます。
児童扶養手当には所得制限があり、子どもの数や扶養義務者の所得金額によって受給金額が異なりますので、受給可能額を知りたい方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
育児の悩みを相談できる窓口
子育ての悩みを受け止めてくれる窓口はいくつか存在します。代表的なところでは、各自治体の「地域子育て支援センター」や「児童相談所」、「子育て・女性健康センター」などがあげられます。
育児の悩みを受け入れてくれる相談先は何か所もありますが、あまり助けにならないというケースもあるかもしれません。アドバイスを受けても安心できなかったり、時には不愉快な思いをしてしまったりする可能性もあります。勇気を振り絞って相談しても悩みがまったく解消されない場合は八方ふさがりに感じられるかもしれませんが、相談員も1人の人間であり、時には相談員との相性が合わないこともあります。相談先は1つではありません。悩みが解決できなかったら「こことは相性が悪かった」と割り切り、もう一度ほかの窓口にも相談を持ち掛けてみてください。
不妊対策の支援
不妊対策の支援については、令和3年1月1日より、「不妊治療」に対する助成の対象範囲が広がりました。対象者については、原則として法的な婚姻関係にある夫婦が対象ですが、生まれてくる子どもの福祉に十分配慮しているとみなされれば、事実婚関係にある方も対象となります。
| 項目 | 令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 |
|---|---|---|
| 所得制限 | 730万円未満 (夫婦合算) |
なし |
| 助成額 | 1回15万円 (初回のみ30万円) |
1回30万円 |
| 助成回数 | 生涯で通算6回まで | 1子ごとに6回まで (40歳以上は3回まで) |
| 対象年齢 | 妻の年齢が43歳未満 | |
海外の子育て支援との比較
これまで妊娠・出産・子育て支援について解説してきましたが、これがどれほど家庭の助けとなる支援であるのか、なかなかピンとこないかもしれません。日本の子育て制度は、ほかの先進国と比較してどのような立ち位置にあるのでしょうか。この問いには、2019年に発表された「先進国における家族に優しい政策(ユニセフ)」が1つの答えになります。このレポートでは、一般的に先進国と呼ばれる41ヶ国を「家族に優しい政策」による順位付けを行っています。
日本では十分なデータが揃っていないため総合順位は付けられていませんが、特筆するべきは、日本では母親のための育児休業制度が16位と比較的充実していること、父親を対象とする「有給育児休業制度」に至っては先進国内で1位という手厚い政策が実施されているという点です。
日本は父親の有給育児休業期間を6ヶ月以上設けている唯一の国です。一方で、「キャリアが絶たれるかもしれない」や「取得できる雰囲気ではない」、「仕事量が多すぎる」などの理由で制度を活用できず、実際に育児休業を取得した父親はほとんどいないという問題点も明らかにされています。
海外と比較されて「遅れている」という印象が残りやすいのが日本の子育て制度です。もちろん課題はまだまだ山のようにありますが、少なくとも有給育児休業期間に関しては世界的に見ても手厚い部類に入っているといえます。
四国のユニークな子育て支援
都市部への人口集中が苛烈を極める中、人口流出を課題とする地方の自治体では、政府が掲げる「地方創生」に取り組み、現地企業との提携やさまざまな支援サービスを提供して地域の魅力を高めています。こちらでは、高知県と愛媛県が取り組むユニークな子育て支援をご紹介します。
高知県の取り組み
高知県全体の取り組みとしてユニークなのは、「こうちプレマnet」という出産・育児応援サイトの運営に力を入れている点です。妊娠・子育てに関する情報が網羅されている「こうちプレマnet」では、保育サービスやよくある相談事例、一般社団法人高知県助産師会宛てのメッセージフォームまで設置されており、高知全体が子育て支援に力を入れている様子が伺えます。
室戸市では、安心して出産や子育てができるように「室戸の赤ちゃんスターターキット事業」を実施中。妊娠後期にはご自宅へ訪問してアドバイスを行い、「妊娠期・子育て期応援ケアプラン」の作成や子育てグッズのプレゼントを行っています。
また、須崎市では母体や子どもの健康状態を管理するのに役立つ「母子手帳」のアプリを配信しています。母子手帳アプリは今でこそ多くの自治体に導入されていますが、全国でもいち早く導入したのが東京都町田市と須崎市でした。さらに、須崎市では、妊娠中・出産後に家事や育児を行なうのが難しい家庭をサポートする「産前産後ヘルパー」の派遣事業も実施しています。
愛媛県の取り組み
愛媛県では、「結婚や子育ての希望が叶い、すべての子どもが夢を持って、自分らしく成長できる愛媛づくり」をテーマに掲げ、令和2年~6年の5年間に及ぶ「第3期えひめ・未来・子育てプラン(後期計画)」を実施しています。このプランでは、結婚前後から子育て全盛期まで、地域が一体となって子どもを見守り、子どもが心身共に健やかに成長できる環境づくりに注力しています。
また、愛媛にある花王、大王製紙、ユニ・チャームと提携し、紙おむつの交換チケット交付サービスがスタートしました。紙製品の出荷額が全国1位であり「紙のまち」として知られる四国中央市では1歳になる子どもがいる家庭に紙おむつを無償で提供しており、他の県には見られない愛媛ならではのユニークな取り組みが見られます。
子育てを楽しむための「支援」を活用しよう
慣れない子育てに直面すると、時に「きちんと育てられるだろうか」という不安に駆られる日もあるかと思います。国や自治体の経済的支援制度を知っておくだけでも次にやるべきことが明確になり、お金の不安も軽くなるでしょう。子育ては1人で行うのでなく、社会全体で行わなければならないものです。
家族・友人に話を聞いてもらうことも大切ですが、時にはお金や育児の専門家の助けも積極的に借りることも必要です。子育て・女性センターや地域保健センターといった相談のための窓口も用意されています。育児の悩みを相談できる子育て支援を活用して、子どもと向き合う楽しい日々を過ごすための糧にしてください。
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう