健康診断結果の数値の見方
各項目の基準値を知って生活習慣病を予防しよう
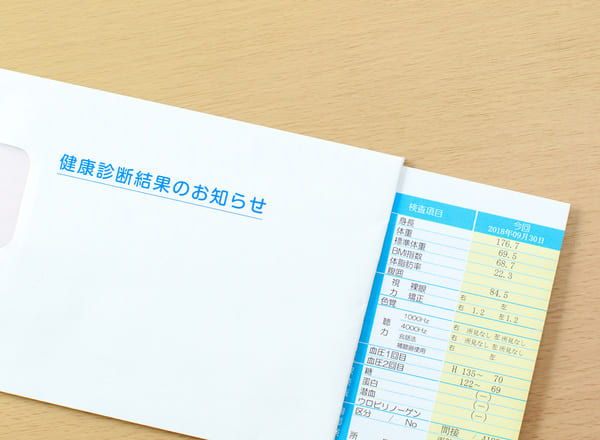
健康診断結果が届いたけれど、数値の見方がわかりにくいと感じることが多くあります。各項目の数値の見方がわかれば、日々の健康作りにも活かしやすくなるでしょう。そこで今回は、項目ごとの基準範囲と要注意点を紹介します。
健康診断が必要な理由とは?

健康診断の目的
健康診断は生活習慣病の該当者や予備軍を減少させるため、保健指導を必要とする人を的確に抽出することを目的としています。特に、メタボリックシンドロームと呼ばれる内臓脂肪症候群に着目した検査です。
メタボリックシンドロームに着目する意義
メタボリックシンドロームは、高血糖や脂質異常、高血圧などの症状があります。これらが重複した場合には、重大な病気の発症の可能性が高くなるとされるため注意が必要です。
ただし、糖尿病や高脂血症、高血圧などは予防可能です。血糖や血圧をコントロールすることにより、病気の予防にもつながる効果が期待できます。
出典:厚生労働省「第2編 健診」
診察|健康診断の結果の見方を項目ごとに基準範囲や要注意点を紹介

身体計測は身長や体重、腹囲から「肥満」や「やせ」の程度を調べる項目です。肥満は生活習慣病をはじめとして、多くの疾患のもととなります。また、やせも健康問題のリスクを高めるといわれているため、注意が必要です。
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・BMI」
BMIは22kg/m²が標準体重
BMIは肥満度を表す指標として用いられ、「体重(kg)」÷「身長(m)の2乗」で算出される値です。日本肥満学会が定めた基準ではBMIが22kg/m²のときの体重が標準体重とされ、最も病気になりにくい状態といわれています。
25kg/m²を超えると生活習慣病のリスクが2倍以上になるとされ、30kg/m²を超えると高度な肥満となり積極的な減量治療が必要です。
| 単位:kg/m² | |
|---|---|
| 低体重/要注意 | 18.4以下 |
| 基準範囲 | 18.5~24.9 |
| 肥満/要注意 | 25.0以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・肥満と健康」
腹囲の異常数値は病気につながる
肥満度の判定はBMIだけでなく、脂肪がどこについているかも重要です。お腹周りに脂肪が多く蓄積している内蔵脂肪型肥満(リンゴ型肥満)の場合、生活習慣病を発症する確率が高くなるといわれています。内臓脂肪面積は、男女とも100cm²以上に相当する腹囲が異常値です。
一方で、腰回りや太ももなどの下半身に皮下脂肪が多くたまり、内臓脂肪が少ないものは皮下脂肪型(洋ナシ型肥満)です。内臓脂肪型肥満と比較して、生活習慣病の症状はあまりみられないとされています。
| 男性(単位:cm) | 女性(単位:cm) | |
|---|---|---|
| 基準範囲 | 84.9以下 | 89.9以下 |
| 異常 | 85.0以上 | 90.0以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・肥満と健康」
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・メタボリックシンドロームの診断基準」
血圧は正常値を保つことが大切
血圧は、メタボリックシンドロームを診断する際の項目の一つです。血圧が異常値になると動脈硬化になる可能性があり、脳や心臓の病気につながるといわれています。
メタボリックシンドロームの基準には当てはまらなくても、高血圧だけで多くの病気を引き起こすこともあるため注意が必要です。
| 収縮期血圧(単位:mmHg) | 拡張期血圧(単位:mmHg) | |
|---|---|---|
| 基準範囲 | 129以下 | 84以下 |
| 要注意 | 130~159 | 85~99 |
| 異常 | 160以上 | 100以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・高血圧」
血液検査|健康診断の結果の見方を項目ごとに基準範囲や要注意点を紹介

血液検査は、自分では気づかない体の状態を知れる重要な検査です。病気の早期発見や早期治療につながる効果や、生活習慣を見直すためのよい機会といえます。検査の項目は多岐にわたるため、主なものを解説します。
脂質系検査で脂質異常症を診断
脂質系検査では、コレステロールや中性脂肪の値から脂質異常症を診断します。生活習慣の乱れや先天的要因のほか、甲状腺機能低下症や神経性食思不振症などの病気が原因になっていることもあります。
HDLコレステロール
善玉コレステロールと呼ばれ、血液中の悪玉コレステロールを回収します。数値が低いほど脂質代謝異常や動脈硬化の可能性があるので、注意が必要です。
| 単位:mg/dL | |
|---|---|
| 異常 | 34以下 |
| 要注意 | 35~39 |
| 基準範囲 | 40以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・HDLコレステロール」
LDLコレステロール
コレステロールは肝臓で作られ、LDLコレステロールによって全身に運ばれます。悪玉コレステロールとも呼ばれ、増えすぎると動脈硬化を起こして重大な病気を発症させる可能性があるので注意しましょう。
| 単位:mg/dL | |
|---|---|
| 異常 | 59以下 |
| 基準範囲 | 60~119 |
| 要注意 | 120~179 |
| 異常 | 180以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・LDLコレステロール」
中性脂肪
体を作るための重要なエネルギー源ですが、摂りすぎると脂肪として体に蓄積されます。肥満につながり、生活習慣病を引き起こす可能性があるでしょう。
| 単位:mg/dL | |
|---|---|
| 異常 | 29以下 |
| 基準範囲 | 30~149 |
| 要注意 | 150~499 |
| 異常 | 500以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・中性脂肪/トリグリセリド」
肝臓系検査は肝機能低下の疑い
肝臓系検査はAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの酵素の値によって、肝臓の疾患を診断する項目です。検査値が高い場合、肝機能異常の疑いがあります。
AST(GOT)・ALT(GPT)
ASTは心臓や筋肉、肝臓などに、ALTは肝臓に多く存在する酵素をいいます。数値が高いと急性肝炎や脂肪肝などの肝疾患が疑われるため、注意が必要です。また、ASTのみが高い場合、心臓や筋肉などの疾患も考えられます。
| AST(単位:U/L) | ALT(単位:U/L) | |
|---|---|---|
| 基準範囲 | 30以下 | 30以下 |
| 要注意 | 31~50 | 31~50 |
| 異常 | 51以上 | 51以上 |
出典:公益社団法人日本人間ドック学会「検査票の見方」
γ-GTP
γ-GTPは、肝臓や胆道に異常がある場合に数値が上昇するため、肝機能の指標になる項目です。検査することで、肝疾患の早期発見にもつながります。
| 単位:U/L | |
|---|---|
| 基準範囲 | 50以下 |
| 要注意 | 51~100 |
| 異常 | 101以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・γ-GTP」
糖代謝系検査は糖尿病予防に役立つ
糖代謝系検査は、血糖値(FPG)やHbA1c(NGSP)などで糖代謝異常を判断する項目です。血糖値は採血時の数値ですが食事や運動により変動するため、ヘモグロビンA1cで平均的な状態を測定します。
血糖値(FPG)
血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。数値によってブドウ糖がエネルギー源として、きちんと利用されているのか判断します。数値が高いと糖尿病やホルモン異常が疑われ、低いと脳へのエネルギー不足により意識低下することがあるとされています。
| 単位:mg/dL | |
|---|---|
| 基準範囲 | 99以下 |
| 要注意 | 100~125 |
| 異常 | 126以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・血糖値」
HbA1c(NGSP)
食事内容や運動量などの、生理的因子による変動がありません。そのため、過去1~3か月の血糖コントロール状態を評価するうえで、重要な指標となる項目です。数値を低く保つことで、糖尿病の合併症のリスクを低減する効果が期待できます。
| 単位:% | |
|---|---|
| 基準範囲 | 5.5以下 |
| 要注意 | 5.6~6.4 |
| 異常 | 6.5以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・糖化ヘモグロビン」
血球系検査は血液にかかわる病気の早期発見につながる
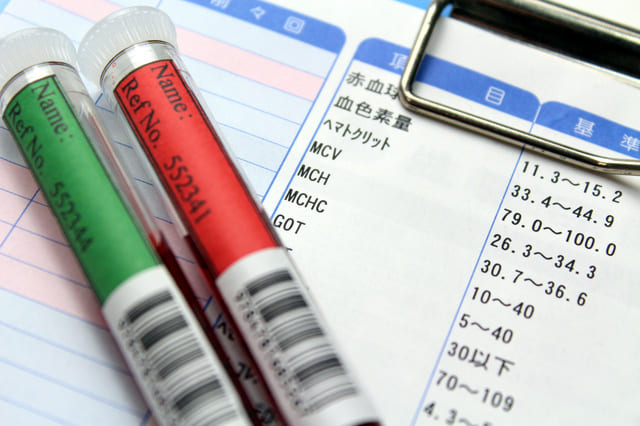
血球は貧血や多血症にかかわる赤血球系検査と、免疫や感染症にかかわる白血球、出血や止血にかかわる血小板数に大別されます。
赤血球(RBC)
肺から取り入れた酸素を全身に運んだり、不要になった二酸化炭素を回収し肺へ送ったりする働きをします。数が多いと多血症、少なすぎると貧血の疑いがある項目です。
| 男性(単位:10⁴/μL) | 女性(単位:10⁴/μL) | |
|---|---|---|
| 異常 | 359以下 | 329以下 |
| 要注意 | 360~399 | 330~359 |
| 基準範囲 | 400~539 | 360~489 |
| 要注意 | 540~599 | 490~549 |
| 異常 | 600以上 | 550以上 |
出典:一般社団法人日本健康倶楽部「健康診断結果の見方」
血色素(Hb)
赤血球に含まれる、赤色素たんぱく質です。ヘム鉄とたんぱく質が結びついたもので、酸素と結びついて体全体に酸素を運ぶ役割があります。鉄分が不足すると鉄欠乏性貧血になる可能性があるため、注意しなければなりません。
| 男性(単位:g/dL) | 女性(単位:g/dL) | |
|---|---|---|
| 異常 | 12.0以下 | 11.0以下 |
| 要注意 | 12.1~13.0 | 11.1~12.0 |
| 基準範囲 | 13.1~16.3 | 12.1~14.5 |
| 要注意 | 16.4~18.0 | 14.6~16.0 |
| 異常 | 18.1以上 | 16.1以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・Hb/血色素量」
ヘマトクリット(Ht)
血液中の赤血球の割合をいい、貧血を判断するために用いられる項目です。数値が高いと多血症や脱水が、低いと鉄欠乏性貧血が疑われます。
| 男性(単位:%) | 女性(単位:%) | |
|---|---|---|
| 異常 | 35.3以下 | 32.3以下 |
| 要注意 | 35.4~38.4 | 32.4~35.4 |
| 基準範囲 | 38.5~48.9 | 35.5~43.9 |
| 要注意 | 49.0~50.9 | 44.0~47.9 |
| 異常 | 51.0以上 | 48.0以上 |
出典:厚生労働省「e-ヘルスネット・Ht/ヘマトクリット値」
白血球(WBC)
白血球は、細菌から体を守る働きをする血液成分の一つです。数値が高いと細菌感染症や炎症、少ないとウイルス感染症や薬物アレルギーなどの可能性があります。
| 単位:10³/μL | |
|---|---|
| 異常 | 3.0以下 |
| 基準範囲 | 3.1~8.4 |
| 要注意 | 8.5~9.9 |
| 異常 | 10.0以上 |
出典:公益社団法人日本人間ドック学会「検査表の見方」
血小板数(PLT)
出血したときに粘着して止める役割をする、血液成分の一つです。数値が高いと血小板血症や鉄欠乏性貧血が疑われ、低いと肝障害が考えられるため注意が必要です。
| 単位:10⁴/μL | |
|---|---|
| 異常 | 9.9以下 |
| 要注意 | 10.0~14.4 |
| 基準範囲 | 14.5~32.9 |
| 要注意 | 33.0~39.9 |
| 異常 | 40.0以上 |
出典:公益社団法人日本人間ドック学会「検査表の見方」
出典:一般社団法人日本健康倶楽部「健康診断結果の見方」
まとめ
健康診断は、生活習慣病を予防する効果や病気の早期発見が期待できます。健康診断結果の数値の見方がわからないときは、この記事を是非参考にしてください。基準範囲の数値をきちんと確認し、健康維持に努めましょう。
ファッションやライフスタイルなどの記事を中心に、ライター活動を行っています。しっかりと下調べをし、暮らしに役立つ情報をお届けします。







