世帯ごとの家計簿を公開!
節約できるポイントとは?
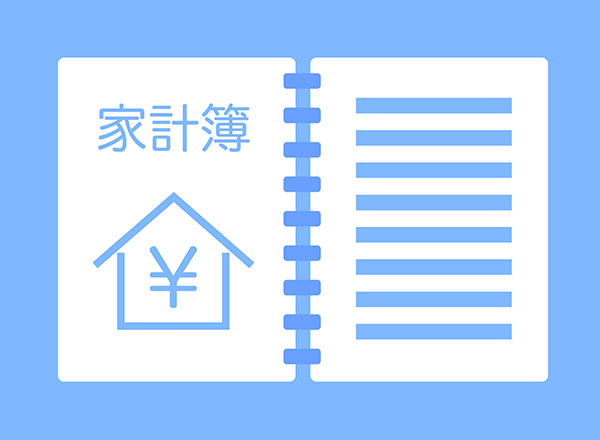
一言で家計簿といっても、その内容は年齢や収入の状況、家族構成などにより大きく異なります。「同じくらいの収入の人はどんなやりくりをしているのか」「一般的な家族の家計簿が気になる」という方もいるのではないでしょうか。今回は総務省統計局の「家計調査」をもとに「一人暮らしの家計簿」「夫婦二人暮らしの家計簿」など、世帯別の家計簿の一例を紹介します。
目次
一人暮らしの家計簿
「一人暮らしの家計簿」に始まり、世帯人数別の家計簿を公開します。家計を見直す際は、自身と近い条件の世帯の家計簿を参考にしてみてください。最初に公開するのは、一人暮らしの方の例です。働いている35歳以下の男性と女性でみてみましょう。
| 項目 | 働いている34歳以下男性 金額 |
働いている34歳以下女性 金額 |
|---|---|---|
| 手取り収入 | 300,377円 | 279,622円 |
| 住居費(家賃・維持費) | 33,033円 | 45,968円 |
| 水道光熱費 | 7,463円 | 8,086円 |
| 交通費・通信費 | 20,834円 | 16,465円 |
| 教育費 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 40,310円 | 30,779円 |
| 家具・家事用品費 | 3,358円 | 6,224円 |
| 被服・履物費 | 4,295円 | 7,257円 |
| 医療費 | 2,699円 | 4,124円 |
| 娯楽費 | 23,254円 | 12,059円 |
| その他(理美容・嗜好品・交際費等) | 17,079円 | 21,670円 |
| 消費支出合計 | 152,325円 | 152,633円 |
| 黒字(手取り収入-消費支出) | +148,052円 | +126,989円 |
手取り収入は男女で2万円ほどの違いがあることがわかります。住居費や被服費、医療費などは男性のほうが抑えられている一方、交通費・通品費や食費、娯楽費は女性のほうが安く抑えられています。
夫婦二人暮らしの家計簿
続いて、賃貸住宅住まいの共働き夫婦の家計簿の事例をご紹介します。独身・一人暮らしとどのような違いがあるのか、読み解いてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 手取り収入 | 478,725円 |
| 住居費(家賃・維持費) | 27,528円 |
| 水道光熱費 | 17,724円 |
| 交通費・通信費 | 47,297円 |
| 教育費 | 1,564円 |
| 食費 | 64,439円 |
| 家具・家事用品費 | 11,250円 |
| 被服・履物費 | 8,767円 |
| 医療費 | 12,749円 |
| 娯楽費 | 24,483円 |
| その他(理美容・嗜好品・交際費等) | 65,847円 |
| 消費支出合計 | 281,647円 |
| 黒字(手取り収入-消費支出) | +197,078円 |
2人分の収入にはなっているものの、一人暮らし世帯と比べ食費や交通費・通信費、水道光熱費といった費目も倍近く増えています。共働き夫婦の場合、各種生活費を折半して、後は各々で自由にお金を使える「別財布」で家計管理をしているケースも少なくありません。別財布は「稼いだお金を比較的自由に使える」という魅力がありますが、一方で「家計管理が不透明になりやすい」、「いざというときお互いの貯金が心許ないと焦る」といった注意点もあります。
参考:2020年 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 表番号 3-1
夫婦と子ども2人の4人家族の家計簿
次に、夫婦と子ども2人の4人家族の家計簿をみていきましょう。なお、ここでは働いている人(有業者)が1人の片働き世帯を例にあげています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 手取り収入 | 498,178円 |
| 住居費(家賃・維持費) | 18,552円 |
| 水道光熱費 | 22,443円 |
| 交通費・通信費 | 45,628円 |
| 教育費 | 25,354円 |
| 食費 | 84,430円 |
| 家具・家事用品費 | 13,469円 |
| 被服・履物費 | 12,157円 |
| 医療費 | 12,500円 |
| 娯楽費 | 31,912円 |
| その他(理美容・嗜好品・交際費等) | 41,956円 |
| 消費支出合計 | 308,402円 |
| 黒字(手取り収入-消費支出) | +189,776円 |
独身や夫婦二人暮らしの家計簿と比べると、とくに大きな変化をみせたのが「教育費」です。夫婦二人暮らしの家計簿の金額と比較すると、実に2万円以上も増えています。子どもの有無や人数により、大きな差が出る費目だということが改めてわかります。水道光熱費や交通費、通信料、家具・家事用品費などほかの費目も上昇をみせています。
参考:2020年 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 第2-7表
老夫婦の二人暮らしの家計簿
最後に、65歳以上の夫婦で二人暮らしの家計簿例を紹介します。仕事や子育てが落ち着いたリタイア世帯の家計簿は、どのようなものなのかみてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 手取り収入 | 222,501円 |
| 住居費(家賃・維持費) | 14,518円 |
| 水道光熱費 | 19,845円 |
| 交通費・通信費 | 26,795円 |
| 教育費 | 4円 |
| 食費 | 65,804円 |
| 家具・家事用品費 | 10,258円 |
| 被服・履物費 | 4,699円 |
| 医療費 | 16,057円 |
| 娯楽費 | 19,658円 |
| その他(理美容・嗜好品・交際費等) | 46,753円 |
| 消費支出合計 | 224,390円 |
| 黒字(手取り収入-消費支出) | +1,111円 |
子育てがひと段落し、子どもが独立した後の世帯の例です。教育費や食費が少なくなっていることが読み取れます。一方で、手取り収入から消費支出を引いた黒字は、ほかの世帯と比べるとかなり低い数値になっています。特別な副収入がない限り、リタイア世代の主な収入源は年金です。「老後2,000万円問題」のニュースなどから、老後の生活に漠然とした不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。よりゆとりのある老後生活を送るためには、年金に加えてさらなる副収入が必要だといえます。早い時期から各種投資信託による資産形成や、個人型確定拠出年金(iDeCo)をはじめとする制度による私的年金の確保が有効です。
参考:家計調査報告(家計収支編)2020年(令和2年)平均結果の概要
地方の家計簿事例は?
上記でご紹介したのは、都心や地方も含む全国を対象とした事例です。ここでは、地方在住・二人以上世帯のうち勤労世帯を対象にした月の収入と支出を解説します。なお、具体的な対象地域は高知市在住の世帯としています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 手取り収入 | 496,598円 |
| 住居費(家賃・維持費) | 20,107円 |
| 水道光熱費 | 20,886円 |
| 交通費・通信費 | 39,341円 |
| 教育費 | 14,444円 |
| 食費 | 77,643円 |
| 家具・家事用品費 | 11,417円 |
| 被服・履物費 | 10,422円 |
| 医療費 | 10,960円 |
| 娯楽費 | 24,578円 |
| その他(理美容・嗜好品・交際費等) | 67,779円 |
| 消費支出合計 | 297,577円 |
| 黒字(手取り収入-消費支出) | +199,021円 |
令和2年平均 家計調査報告によると、高知市在住で二人以上世帯のうち勤労世帯の手取り収入は令和元年と比べて10.3%の増加がみられたと報告されています。同時に、全体の消費支出は減少傾向にあることがわかっています。令和元年の消費支出が30万8,179円であったのに対し、令和2年の調査では29万7,577円という結果となっていて、この減少の要因は、新型コロナウイルスの影響により、外出自粛や巣ごもり需要が高まったことが要因と考えられます。
そもそも家計簿は何のために必要?
家計簿を続けるうち、「惰性で家計簿をつけているけどゴールがわからなくなってきた」と悩む方は少なくないはずです。そんなときこそ、家計簿の必要性や家計簿をつけることで得られるメリットを再認識し、初心へ帰ることが大切です。
メリット①無駄な支出を把握できる
家計簿をつけることで、収入に対する支出額が一目でわかるようになります。その結果「どの費目にどれだけのお金を使ったのか」という情報を知ることができます。加えて「思ったよりも無駄遣いをしていた」という気づきにつながり、その後の家計管理にも役立ちます。
メリット②使途不明金を把握できる・なくせる
「使途不明金」とは、何に使ったのかがハッキリとわからないお金のことです。「毎月ギリギリでやりくりしているのに、何にお金を使ったのか具体的に把握できていない」という方は、この使途不明金が多い傾向にあります。とくに、「毎日何となく缶コーヒーを買ってしまう」、「用もないのにコンビニに立ち寄ってしまう」という方は要注意です。
家計簿をつけることで使途不明金の正体に気づくことができ、「ならば来月は外食を減らそう」、「交遊費を少し削ろう」という改善のアクションへつなげられるのです。
メリット③固定費の定期的な見直しにつながる
「契約して以来、スマホやPCなどの通信費を見直していない」、「毎月何となく光熱費を払っている」という方は多いのではないでしょうか。通信費や光熱費などの固定費を見直すことで大幅な節約効果を期待できます。
家計簿をつけると「別のプランに変えたほうが良い」、「この月額をもっと安くできそう」という気づきにつながり、固定費の節約になります。たとえば電気代・ガス代などの固定費は、自身に合ったプランに切り替えることで出費を抑えられる可能性があるのです。固定費は、毎月の支出額でも大きなウエイトを占める費目といえます。家計簿をつけて、見直しの機会を毎月作りましょう。
メリット④物価の推移を読み取れる
家計簿をつけることは、食品や日用品などの価格を記録することでもあります。過去の記録と照らし合わせれば物価の推移を読み取れるようになり、結果的に値段を意識した効率的な節約・買い物もできるようになります。
メリット⑤家族の協力も得られやすくなる
どの費目にどれだけ使っているかわかりにくいと、家族も実感がわきにくく「どう協力すればいいのか」と困惑してしまうかもしれません。家計簿があれば、やりくりの内容を家族やパートナーへ説明しやすくなります。「先月はこれだけ臨時の出費があったから、今月はこの費目の節約に協力してほしい」、「この節約が成功できれば、次のレジャー費にかなり余裕ができる」など具体的に説明することで、家族やパートナーの協力も得られやすくなるでしょう。
家計簿をつけるうえでの注意点
ただ何となく家計簿をつけている、自分に合っていないつけ方を参考にしている方は要注意です。家計簿の目的は、「お金の使い方を振り返り、節約や貯金につなげること」にあるため、自分に合う家計簿のつけ方で行いましょう。以下の点を参考にして、ぜひ家計簿をつけてみてください。
自分に合った家計簿のつけ方を選ぶ
一言で家計簿といっても、使うツールや頻度、つけ方は人によりさまざまです。「市販のノートが一番使いやすい」という方もいれば、「スマホで管理できる家計簿アプリのほうが続けやすい」という方もいるでしょう。まめに記録するのが苦にならないという方は手書き、スピーディーに記録したいという方はアプリと、自分に合った家計簿のつけ方・ツールを選ぶことが大切です。
また、費目の分け方や細かさ、家計簿を記録する頻度(日・週・月)も、自分にとっての続けやすさを意識すると良いでしょう。加えて公開されている家計簿を参考にする際は、自分に近い条件(収入・世帯人数など)のものを参考にするのが鉄則です。
「記録するだけ」で終わらせない
家計簿のゴールは記録することではありません。お金の使い方を記録するだけでなく、その結果から「使途不明金はどれだけあるのか」、「どうやって節約して改善するか」を考えることが大切といえます。
費目を細分化しすぎない
費目が細かすぎると家計簿をつけるのが面倒になってしまい、うまく続けられなくなります。家計簿の目的は、あくまでお金の使い方を見直したり節約したりすることにあります。少し大雑把なつけ方でも、これらの目的がしっかりと果たせていれば問題ありません。
とくに家計簿初心者のうちは、ざっくりとした費目をもとに記録をつけていくと良いでしょう。たとえば「特別費」、「交際費」、「レジャー費」などは、「諸雑費」にまとめて計算してもかまいません。「食費」、「家賃」、「通信費」、「交通費」、「光熱費」、「各種税金」という大まかな費目以外は、思い切って「諸雑費」でまとめてしまっても良いでしょう。
自分に合った頻度で家計簿をつける
家計簿をつける頻度は、人によって異なります。毎日コツコツと記録するのが向いている方もいれば、週ごと、月ごとにまとめて記録するのが合っている方もいます。「毎日記録すると挫折しやすい」という方は、週ごと・月ごとの記録に変更してみるのも手です。どの頻度が自身に合っているかを考えたうえで、無理のないよう家計簿をつけることが重要です。







