円安と円高どっちがいい?
メリットとデメリット、自身でできる対策について解説

「円安」「円高」という言葉をニュースでよく聞くものの、実際にはなにが起きているのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。円安、円高は私たちの日々の生活にも直結する問題です。 本記事では、円安と円高について解説するとともに、どちらがいいのかも解説します。
円安・円高とは?

円安とは、外国通貨に対する日本円の価値が下がることです。円安になると輸出企業は利益が増えますが、輸入品の価格が上がるため国内の物価が高くなる可能性があります。
一方、円高は日本円の価値が上がることで、輸入品が安くなる一方、輸出企業の利益が減少する傾向があります。
円安・円高は金利差、経済状況、政治的要因などに影響され、私たちの生活や企業の経営に大きな影響を与えるのです。
どっちがいい?円安・円高のメリットとデメリット
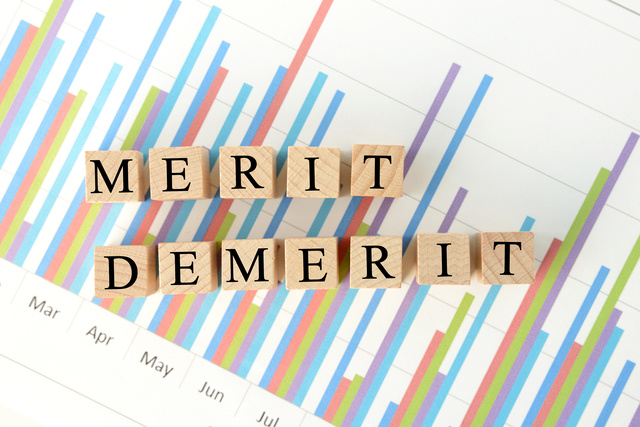
円安と円高はどっちがいいのかを考えるために、それぞれのメリット、デメリットを解説します。どの視点から見るかによってどっちがいいかは大きく変わるため、まずは基本的な点を理解していきましょう。
円安のメリット
円安のメリットは、おもに日本製品を輸出しやすくなることと外貨建て資産の利益が増えやすいことがあります。
それぞれの詳細を詳しく見ていきましょう。
日本製品を輸出しやすくなる
円安になると日本の製品が海外の製品と比較して安くなるため、海外での競争力が高まります。これにより、日本の輸出企業は売上を伸ばしやすくなります。
とくに自動車や電化製品など、価格競争が激しい分野では大きな利点です。さらに海外からの旅行客も増え、インバウンドによる大きな恩恵を受けられます。
外貨建て資産の利益が増える
円安時には外貨建て資産を日本円に換算した場合の金額が増えるため、外国資産を持つ投資家や企業の資産が増えるというメリットがあります。
近年はNISAなどでも気軽に外貨建ての資産を個人が保有できるので、円の価値が下がる前に外貨建ての資産を保有しておけば、大きな利益を得られるでしょう。
円安のデメリット
円安のデメリットとしては、輸入品の値段が高くなる、賃金が上がりにくくなるといった点があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
輸入製品の価格が高騰する
円安になると、輸入品の価格が高くなります。とくにエネルギーや原材料などの必需品の価格が上がると、企業のコストが増加し値上げが続くことになります。
インフレが進むと生活コストが上がり、日々の生活が苦しくなってしまうのです。エネルギーのほとんどを輸入に頼っている日本では、円安は深刻な問題となる可能性があります。
賃金が上がらず支出が増える
円安で物価が上がり続けても賃金が上がらないと、生活コストが増えて日々の生活に余裕がなくなってしまいます。円安が進むと、以前は同じ金額で購入できたものが、今では倍の金額を出しても手に入らないという事態もありえます。
商品の金額が上がってもエネルギーや原材料のコストが賄われるだけで、その企業で働いている人の賃金が上がるわけではない点が円安の大きな問題です。
円高のメリット
円高になるとどのようなメリットがあるのか、海外製品や輸入産業の観点からチェックしてみましょう。
海外製品を安く購入できる
円高になると海外からの輸入品の価格が下がるため、海外製品を安く購入できます。
生活費が節約できるだけでなく、海外旅行や留学へのハードルも低くなります。同じ金額でも、円高のほうがより安く、お得に海外での観光や食事、買い物などを楽しめるのです。
人々の購買力が高まるとさらに景気もよくなり、好循環が続くでしょう。
輸入産業の業績がよくなる
輸入業がメインの企業は円高になると原材料や製品を安価に仕入れられるため、コストを削減できます。これによって輸入産業の利益が高まり、国内市場での価格競争力も強化されます。
利益を分配金などで株主に還元する、給与や賞与アップで従業員に還元するなども可能になり、人々の生活が潤う点も円高の魅力です。
円高のデメリット
メリットが多く見える円高ですが、視点を変えるとデメリットにもなりえます。円高が続くとどのようなデメリットがあるのかを見てみましょう。
日本製品が海外で売れにくくなる
円高が進むと日本製品の価格が海外製品と比べて高くなるため、海外市場で売れにくくなります。輸出メインの企業の売上が減少し、国内の経済にも影響を及ぼす可能性があります。
自動車や電化製品などの単価が高い製品の売上が落ちると、結果として株価が下がる、給与が上がらないなど、人々の収入が下がる可能性も考えられます。
インバウンド事業の業績が悪くなる
円高になると、外国人観光客にとって日本はお金がかかる国になってしまいます。観光客の数が減ると、ホテルや旅館、レストラン、観光施設などの売上が減少します。
インバウンド、観光がメインの収入源となっているエリアには、大きな打撃となるでしょう。街全体が衰退する、お店が次々と閉店してしまうなどの可能性も考えられます。
円安・円高はどっちがいい?

円安と円高は結局どっちがいいのか、さまざまな視点から考えてみましょう。
円安がいい場合
輸出の面から考えると、円安のほうがいいといえます。円の価値が下がると日本製品が海外で安くなり、輸出量が増えやすくなります。輸出をメインとする企業の売上や利益が向上し、雇用の増加や賃金の上昇にもつながる可能性があるでしょう。
円安になると海外からの観光客が増えてインバウンド消費が活性化するため、観光業や小売業も恩恵を受けます。さらに、外貨資産を持つ人にとっては資産が増えるという魅力もあります。
円高がいい場合
消費者の視点から考えると、円高のほうがいいといえます。円の価値が高くなると輸入品や原材料の価格が下がり、エネルギーや食料品などの生活必需品が安くなります。
安く輸入品が買えるのでちょっとした贅沢や気晴らしもしやすくなり、経済活動も活発になるでしょう。
生活費の負担が減って生活に余裕が出るだけでなく、日本から海外旅行や留学をする際の費用が減ってハードルが低くなるという魅力もあります。
自分でできる円安対策

円安と円高は一概にどっちがいいとは言い切れませんが、円安になると輸入品が高くなる、賃金が上がりにくくなるといったデメリットがあります。
為替は世界情勢などの影響を大きく受けますが、個人でも円安のリスクに備えることは可能です。どんな方法があるのかを見てみましょう。
外貨建ての預金をする
円安時に、外貨建ての金融資産の価値が高まるため、外貨建ての預金をしておくことがおすすめです。たとえば米ドルやユーロなどの強い通貨で預金をしておくと、円安が進むほど日本円に換算した際の預金額が増えます。
外貨建ての預金や保険、金融商品などにも目を向けてみましょう。
外貨建ての投資をする
外貨建ての投資も円安対策として有効です。株式や債券など、外国の資産に投資することで、円安が進むほど資産価値が高まります。
為替による利益は短期的に狙うこともできますが、変動が激しい通貨を所持するとリスクも大きくなってしまいます。不安な方は低リターンでも低リスクでの運用が可能な、米ドルやユーロなどでの資産運用がおすすめです。
国内製品を購入する
円安になると輸入品の価格が高くなるため、国内製品を購入することが節約につながります。国内製品は輸入品に比べて円安の影響を受けにくく、価格が安定しやすいです。
また、国内製品を購入することで国内産業の活性化につながり、国内企業を支援することができます。家計の負担も抑えつつ、日本企業を応援する意味でも国内製品を選ぶといいでしょう。
まとめ
円高と円安はどっちがいいのか、それぞれのメリットとデメリットを紹介しました。為替は日々の生活に大きな影響を与えます。
いつ円安、円高になるかは予想がつきにくいですが、日ごろから円安対策を意識しておくことがおすすめです。外貨建ての資産を持つ、日本製品を購入するなど、個人でできる円安対策も意識してみてください。

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。







