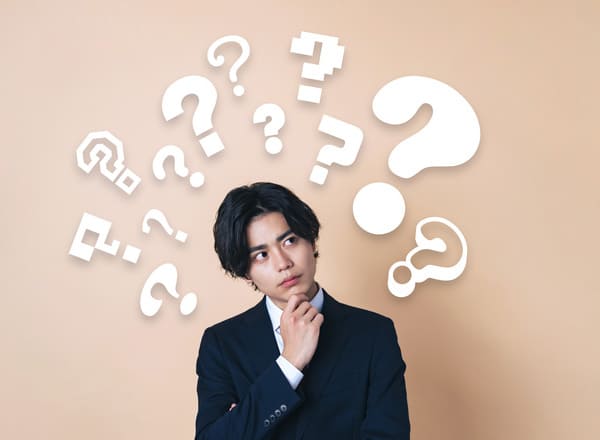出産したらやることって?
必要書類や期間をチェックしてスムーズな申請手続きを!

妊娠してから出産するまでは、赤ちゃんに会うのが楽しみな期間になります。一方で、出産したら必要な書類を準備したり役所で手続きしたり、やることがたくさんあって不安になりやすいものです。この記事では出産したらやることについて必要書類や期間に触れながら、スムーズな手続きができるように解説します。
出産後の手続きに向けて準備する

赤ちゃんが産まれると常に目が離せず、育児で忙しくなります。出産後の手続きをスムーズに進めるために、赤ちゃんが産まれる前にできる準備を進めておきましょう。
出産したらやることを期間ごとに整理
赤ちゃんが産まれたら、役所や会社で手続きをします。出産したらやることについて期間ごとにまとめたのが、以下の表です。
| 内容 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険への加入 | 出産後速やかに行う | 加入中の健康保険の担当窓口 |
| 出生届 | 出産日を含む14日以内 | 市町村役場 |
| 児童手当 | 出産日を含め15日以内が推奨 | 移住地の市町村役場 |
| 出産育児一時金 | 受取方法により異なる | 病院または加入中の健康保険の担当窓口 |
| 高額療養費制度の利用 | 診察日の翌日~2年以内 | 加入中の健康保険の担当窓口 |
| 出産手当金 | 出産後57日目以降 | 勤務先の担当部署 |
| 育児休業給付金 | 育児休業開始から4ヶ月以内 | 勤務先の担当部署 |
パートナーと協力してやること
出産したら、お母さんは赤ちゃんにつきっきりとなります。炊飯や掃除などの家事、必要書類の取り寄せや記入などやることがたくさんあるため、パートナーと協力することが大切です。必要な手続きが漏れていないか確認し、期限までに完了できるよう力を合わせて進めましょう。
出産後の必要書類と申請方法
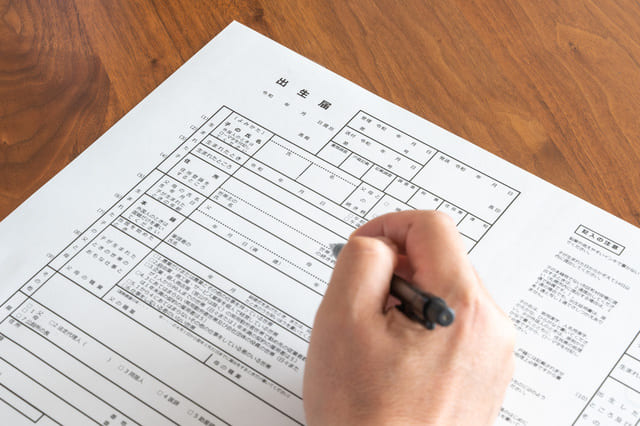
役所や会社など手続きする先に分けて、出産したらやることを詳しく解説します。
自治体での手続き
役所では、出生届と児童手当金の手続きをします。
出生届
提出期限は出産日を含めた14日以内です。提出先は子どもの出生地か本籍地、または届出人(父、母)の移住地の市町村役場になります。
出生届は、子どもの戸籍を登録するために必須な手続きです。出生届の用紙は役所に置いてありますが、出産した病院や産院で用意してもらえることもあります。提出するときは、母子手帳を持参しましょう。里帰り出産の場合、現地の役場での手続きも可能です。
児童手当金
出産日の翌日から15日以内に手続きをしましょう。育児手当金は申請した翌月分から支給されるため、手続きが遅くなるともらえる金額が少なくなる点に注意が必要です。期間をさかのぼって受け取ることは不可能なため、先延ばしにしないよう優先順位を高くしておきましょう。
勤務先での手続き
会社では、健康保険への加入、出産手当金、育児休業給付金の手続きをします。
健康保険への加入
会社勤めの場合は、担当部署に問い合わせて健康保険への加入手続きを進めます。国民健康保険の場合は、自治体の窓口が手続き先です。健康保険は子どもが医療費助成を受けるのに必要なため、出産したら速やかに手続きしましょう。
出産手当金
出産後57日目以降から2年以内に手続きをすると、産休開始前の給料の約3分の2に相当する手当が受け取れます。通常は、出産前42日と出産後56日を合わせた98日分です。手続きが完了してから1~2ヶ月後に支給されます。
育児休業給付金
産休後そのまま育児休業に入ってから、4ヶ月以内に申請します。産休前と初回の申請時の2回、勤務先へ育児休業給付の書類提出が必要です。
産院での手続き
入院した産院や病院では、出産育児一時金の手続きをします。
出産育児一時金
産院や病院が直接支払制度を採用していれば、健康保険組合から医療機関へそのまま支払われるのが出産育児一時金です。退院時には出産育児一時金(一律で42万円)との差額を支払いますが、余剰がある場合は返金されます。
直接支払制度を採用していない場合でも健康保険組合に申請すると、受取代理制度によって直接医療機関への支払いが可能です。これらの制度を利用せずに自分で医療機関へ支払い、健康保険組合に申請して受け取る方法もあります。
出産後の医療費と保険への加入

赤ちゃんが産まれた後でやることには、医療費の支払いや保険への加入があります。社会保険の適用範囲や必要な保険の種類は個人によって違うため、自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
出産したら直接支払う医療費
妊娠から出産にかけての検診や入院にかかる費用は、医療費ではありません。そのため、医療保険が適用されず、全額自己負担となるのです。出産育児一時金や出産手当金などは、こういった負担を軽減する仕組みになります。
しかし、帝王切開などの医療行為は医療費となり、自己負担限度額を超えた分は高額療養費で払い戻されるのです。帝王切開が決まっている場合、事前に認定を受けると支払いは自己負担分のみとなります。自己負担限度額は本人の年齢や所得によって異なるため、自身の該当する内容を確認しておきましょう。
医療費助成を受ける
赤ちゃんの健康保険加入後には、子どもの医療費助成が受けられます。子どもが医療機関で診察や治療をしたときの費用の一部、または全部を自治体が助成してくれる制度です。自治体によって名称や対象年齢、助成金額が異なるため、自身の該当する制度について調べておきましょう。
親が加入する保険
子どもが産まれたらその後の生活はもちろんですが、将来の教育費までお金が必要です。親が十分に養っていける状態を保っていても、万が一のことがあると家族と子どもの生活が不安定になってしまいます。家計や親の働き方、収入によって最適な保険の種類が異なるため、自身の状況に見合う商品を調べておきましょう。
子どもが加入する保険
教育資金にあてたり万が一に備えたりできる、子ども向けの保険があります。学資保険は子どもが被保険者となり、親が保険料を支払う商品です。子どもの進学や年齢ごとに一時金が受け取れたり、親に万が一のことがあれば保険料の支払いを免除されたりします。
親が入る保険について検討するときに、一緒に調べてみると選択肢が広がりやすいです。
出産後に考えておきたいこと

役所や会社で必要書類を集めたり申請したりする作業が終わると、一息つけるタイミングです。手続き以外にも出産後に考えておきたいことについて解説します。
出産の報告や内祝い
親戚や友人、職場の人に出産の報告をしましょう。仕事で産休を取っている場合は、休ませてもらっている感謝の気持ちも一緒に伝えると丁寧です。普段から連絡を取る機会が少ない人へは、年賀状などで報告する方法もあります。
出産祝いをもらった場合は、産後1ヶ月頃に内祝いとしてお返しを贈るのがマナーです。出産後の忙しいタイミングですが、内祝いの準備も進めておきましょう。
ライフプランの作成
子どもが自立するまでお金のやりくりをしていくために、ライフプランを作成するのが効果的です。子どもが産まれて家族の一員が増えると、生活費や教育費など必要になるお金が具体的になります。毎月の家計管理だけでなく、数10年先まで想定したライフプランで資金計画を考えることも大切です。
教育方針や進学先を考える
子どもをどのような環境で育てたいか、どのような教育を受けて欲しいかについて、出産後から考えておくとじっくり検討できます。地域によって生活環境や子育て支援策が違うため、小学校に入学する頃までに大まかな教育方針が立てられていると安心です。
まとめ
出産後にやることは役所や会社での手続きだけでなく、将来に向けての計画を考えるなど多岐に渡ります。子どもと一緒に過ごす新生活を楽しみながら、必要な手続きを漏れなく進めていくことが大切です。出産後にスムーズな申請手続きをするための参考にしてみてください。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。