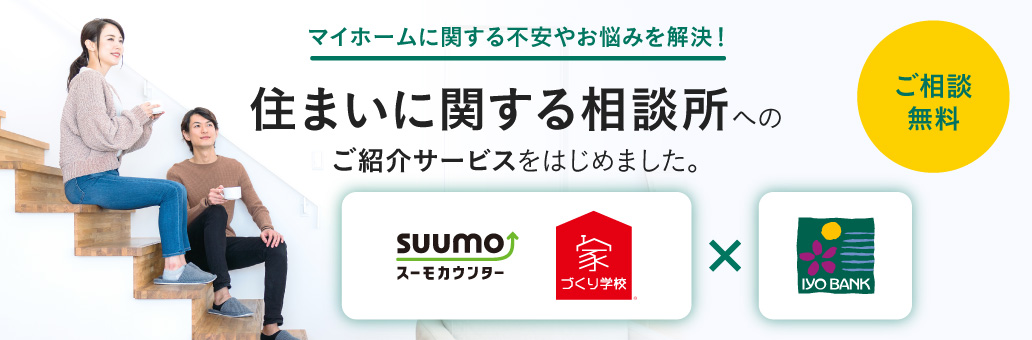家の構造・工法や建材の種類について解説
選び方のポイントとは?

家を建てるときは建物の構造や工法を決めなければなりません。構造・工法によって建築費用や性能が大きく変わってくるため、違いを正しく理解してから選択することが重要です。今回は家の構造・工法や建材の種類について解説します。構造・工法の選び方がわからず悩んでいる方は必見です。
なぜ家の構造を知る必要があるの?

なぜ家の構造を知る必要があるのかというと、家の建築費や性能に影響を及ぼすためです。同じ規模の建物でも構造が違うと、建築費は大きく変わります。耐震性・省エネ性能などの性能にも大きな違いがあるため、家に何を求めるかで選ぶべき構造は異なるのです。
家づくりを依頼するハウスメーカーを選ぶ際も、家の構造について知っておくことは重要です。ハウスメーカーは各社採用している構造が異なります。どの構造にするか決めておけば、ハウスメーカーの選択肢を絞ることができるでしょう。
家の構造・工法4種類

家の構造は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種類があります。代表的な工法は、以下の4種類です。
- 木造軸組工法
- 2×4(ツーバイフォー)工法
- 鉄骨軸組工法
- 鉄筋コンクリート工法
次の項目からは、各構造・工法の特徴について解説します。
木造軸組工法
木造軸組工法は木材を使い、主要構造となる柱と梁を組み上げた工法です。日本では昔から存在する伝統的な工法で、今も多くの住宅で採用されています。筋交いや耐力壁をプラスして、さらに頑丈なつくりにすることもできます。
木造軸組工法の大きなメリットは、間取りの自由度が高い点とリフォームに対応しやすい点です。柱と梁を組み合わせて空間をつくるため、比較的間取りを自由に組めます。梁の高さや柱の位置、間隔のバランスを取り荷重についてきちんと計画することで広いリビングや大きな窓も設置することができるでしょう。間取り変更や増築などのリフォームにも備えられます。
デメリットは鉄やコンクリートに比べて強度が劣る点です。木材は水分や湿気が大敵で、雨漏りや結露によって家全体が傷んでしまうリスクがあります。シロアリ被害にも注意しなければなりません。防音性・断熱性・気密性も劣ります。手作業で組み立ていく特性上、施工する職人の技術によって品質に差が出やすいこともデメリットです。
木造軸組工法のメリット |
木造軸組工法のデメリット |
設計の自由度が高い リフォームに対応しやすい |
鉄やコンクリートより強度が劣る 防音性・断熱性・気密性が劣る 職人の技術によって品質に差が出やすい |
2×4(ツーバイフォー)工法
木の角材と合板で構成されたパネルを使って、箱型に組み立てる工法です。パネルの枠組みとなる角材の断面サイズが厚さ2インチ×幅4インチであることから、2×4(ツーバイフォー)工法と呼ばれています。木造軸組工法と比べると歴史は浅いですが、アメリカやカナダを中心に世界各国で普及している工法です。日本では高度経済成長期頃から、2×4工法による住宅が大量供給されました。
2×4工法は部材がほぼ規格化されているため、職人の技術に左右されることなく品質が安定しているのがメリットです。部材は工場でつくられ、現場で組み立てられます。職人による手作業が少ないため、工期が短いです。パネルが柱と耐震壁の役割を果たすことから、耐震性や耐風性に優れているメリットもあります。
デメリットはパネルの位置や量について制約を受けるため、間取りの自由度が低い点です。大きな窓を設けるのは難しい可能性があります。将来、間取り変更をともなうリフォームをおこなう場合も、制約がある点に注意しなければなりません。
2×4(ツーバイフォー)工法のメリット |
2×4(ツーバイフォー)工法のデメリット |
品質が安定している 工期が短い 耐震性・耐風性に優れている |
設計の自由度が低い リフォームに制約がある |
鉄骨軸組工法
鉄骨軸組工法は、鉄骨の柱と梁を骨組みとして使用します。木造軸組工法の木材を、鉄骨に置き換えた構造とイメージしていただくとわかりやすいでしょう。鉄骨の厚さが6mm未満の場合は軽量鉄骨造、6mm以上の場合は重量鉄骨造といいます。柱と梁を縦横に組み、ブレースと呼ばれる斜めの鉄筋を入れることで、横からの力に抵抗できる仕組みです。鉄骨軸組工法は一戸建て住宅のほか、3階建て以上のアパートやマンション、ビルなどでも採用されています。
部材が工場で生産されるため、品質が安定している点が鉄骨軸組工法のメリットです。しなやかさや粘り強さも持ち合わせていることから、耐震性も優れています。木材のようにシロアリ被害にあう心配も少ないでしょう。重量鉄骨造は鉄骨の本数が少ないため、自由で開放的な間取り設計ができます。大空間や大きな窓も設けられるほか、個性的なデザインも実現しやすいです。
ただし鉄は熱を通しやすい特性があるため、結露による耐久性低下に注意しなければなりません。火災による熱にも弱く、500℃では50%に、1,000℃以上になると強度がゼロになるといわれています。鉄骨軸組工法で家を建てる場合は、結露対策や耐火被覆などが不可欠です。防音性も低いため、気になる場合は対策が必要になります。また軽量鉄骨造はたくさんの鉄骨を使うことから、間取り設計やリフォームの制限を受けることが多いです。
鉄骨軸組工法のメリット |
鉄骨軸組工法のデメリット |
品質が安定している 耐震性に優れている シロアリ被害の心配が少ない 設計の自由度が高い(重量鉄骨造) |
熱を通しやすく結露や火災のリスクがある 防音性が低い 設計の自由度が低い(軽量鉄骨造) リフォームに制約がある(軽量鉄骨造) |
鉄筋コンクリート工法
鉄筋コンクリート工法は、鉄筋とコンクリートを使って建物を支える構造です。「Reinforced Concrete(補強されたコンクリート)」を略して、RCとも呼ばれています。鉄筋とコンクリートという2種類の材料を使うことで、お互いの弱点を補っているのが特徴です。工事では網目状に鉄骨を組んで、型枠にコンクリートを流し込みます。
鉄筋コンクリート工法は耐震性、耐久性、遮音性、耐火性に優れています。法定耐用年数は47年で、鉄骨や木造よりも建物の寿命も長いです。ずっと快適に住み続けたいと考えている方に向いているでしょう。設計の自由度も高く、大空間や大きな窓もつくれます。型枠の組み方次第では、曲線を使ったデザイン性の高い家を実現できる点もメリットです。
建築費は4種類の構造・工法のなかで最も高額です。建物が重くなるため、地盤が弱い土地では改良工事が必要になる場合もあります。施工の難易度が高く、職人の技術力によって品質に差が出る点にも注意が必要です。また、気密性が高いゆえに結露が発生しやすくなります。
鉄筋コンクリート造のメリット |
鉄筋コンクリート造のデメリット |
耐震性、耐久性、遮音性、耐火性が高い 建物の寿命が長い 設計の自由度が高い |
費用が高い 地盤が弱いと改良工事が必要 品質に差が出やすい 結露が発生しやすい |
構造の選び方
4種類の構造には、それぞれメリット・デメリットがあります。自分に合った構造の選び方は、家づくりで重視するポイントを考えることです。
たとえば建築費用を抑えたい方は、木造軸組工法や2×4工法が向いています。3階建て以上の家を建てたい場合や地震に強い家に住みたい場合は、鉄骨軸組工法を検討するのが良いでしょう。建築性能の高さを重視する方は、建築費用が予算に収まれば鉄筋コンクリート工法を検討してみるのも手です。
家の建材の種類

家を建てる際は、場所によってさまざまな建材を使用します。建材とは建築工事の材料のことで、木材や金属、石など多種多様です。次の項目からは家の建築で使われる建材の種類について解説します。
床材
床材は家の床に使用する仕上げ材です。足が接する部分であり、広い面積を占めます。どんな建材を選ぶかによって、家の快適性や美観に大きな影響を及ぼします。
床材の種類はフローリング、クッションフロア、フロアタイル、カーペット、畳、コルク、モザイクタイル、石などの種類があります。床材を選ぶときは部屋によって使い分けが必要です。たとえば脱衣所で身体の熱を奪う床材を選ぶと、ヒートショックの危険性が高まります。タイルや石は避け、クッションフロアやコルクを選ぶのがおすすめです。
メリット |
デメリット |
|
フローリング |
温かみがある 強度がある 断熱性が高い 足触りがやわらか |
コストが高い メンテナンスに手間がかかる 無垢材は水に弱い |
クッションフロア |
コストが安い お手入れが簡単 色やデザインが豊富 |
凹みができやすい 安っぽく見える 熱に弱い |
フロアタイル |
強度がある お手入れが簡単 色やデザインが豊富 |
クッション性がない 熱に弱い 防音性が劣る |
カーペット |
肌触りが良い 防音性・クッション性が高い 温かい |
お手入れが大変 シミになりやすい ダニが発生しやすい |
畳 |
肌触りが良い 防音性・クッション性が高い 和の雰囲気を演出できる |
お手入れが大変 車椅子生活には不向き ダニが発生しやすい |
コルク |
クッション性が高い 吸湿性・保温性が高い 温かみがある |
日光で変色することがある |
タイル |
水に強い 耐久性が高い 汚れにくい |
種類によっては滑りやすい 素足では固く感じる |
石 |
高級感を演出できる |
固く冷たい |
屋根材
屋根材は、建物を守る屋根の仕上げに使われる建材です。雨風や紫外線といった過酷な環境にさらされるため、耐候性の高さが求められます。
屋根材はスレート系・金属系・粘土系の3種類に大別できます。スレート系は化粧スレート・天然スレート、金属系はアルミ・ステンレス・チタニウム・ガルバリウム鋼板、粘土系は和瓦、洋瓦などです。
近年屋根材のなかで人気を集めているのが、金属系のガルバリウム鋼板です。金属なのに錆びにくい性質を持っていて、断熱性にも優れています。さらにメンテナンスがほぼ不要という画期的な屋根材です。シャープでお洒落なデザインの家にすることができます。
メリット |
デメリット |
|
スレート系 ・化粧スレート ・天然スレート |
費用が安い 色やデザインが豊富 |
割れやすい コケや藻が生えやすい |
金属系 ・アルミ ・ステンレス ・チタニウム ・ガルバリウム鋼板 |
軽くて強度が高い 費用が安い 水に強い 加工しやすい |
遮音性・断熱性が低い 塩害に弱い |
粘土系 ・和瓦 ・洋瓦 |
遮音性・遮熱性が高い 重厚感を演出できる |
地震に弱い |
外壁材
外壁材は家の外側に取り付けられる仕上げ材です。紫外線や風雨、気温変動、騒音などから建物を保護する役割を果たします。種類によってメンテナンスの頻度が変わるため、ランニングコストに大きな影響を及ぼします。さらに家の第一印象を決める部分であることから、選んだ外壁材が理想の外観デザインに合っているかどうかも重要なポイントです。
外壁材の種類はモルタル、サイディング、ALC、タイル、レンガ、石材、羽目板などがあります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット |
デメリット |
|
モルタル |
自然の風合いを演出できる |
ひび割れが入りやすい 汚れが付きやすい 仕上がりに差がある |
サイディング ・窯業系サイディング ・金属系サイディング ・木質系サイディング ・樹脂系サイディング |
【窯業系サイディング】 耐震性・耐火性が高い 色やデザインが豊富 【金属系サイディング】 断熱性・遮音性が高い メンテナンスしやすい 【木質系サイディング】 温かみがある素材感 断熱性が高い 【樹脂系サイディング】 耐震性・施工性が高い メンテナンスしやすい |
【窯業系サイディング】 コーキング材が劣化しやすい 【金属系サイディング】 錆びる・凹むことがある 費用が割高 【木質系サイディング】 汚れやすい 防火性が劣る 【樹脂系サイディング】 防音性・遮音性・断熱性が劣る 費用が割高 |
ALC |
軽量 断熱性・耐衝撃性に優れる |
吸水性が高く耐候性に劣る 費用が割高 |
タイル |
高級感を演出できる 耐久性が高い メンテナンスが楽 |
費用が高い 剥離することがある |
レンガ |
耐久性が高い メンテナンスが楽 耐熱性・耐火性が高い |
リフォームが難しい 熱がこもりやすい 工期が長い |
石材 |
高級感を演出できる メンテナンスが楽 耐久性・耐火性・耐熱性が高い |
重みによる耐震性低下 費用が高い |
羽目板 |
温かみがある素材感 経年変化を楽しめる |
防火性が劣る |
内壁材
内壁材は壁や天井に使われる建材で、部屋の雰囲気を左右します。直接触れることが多いため、デザインだけでなくお手入れのしやすさや性能まで吟味して選んだほうが良いです。
内壁材にはクロス、漆喰、化粧板、タイルが使われることが多いです。クロスは壁紙のことで、多くの住宅で使われています。塗り壁は土などの自然素材を壁に塗るという日本古来の建材です。化粧板は合板や石膏ボードの表面に化粧加工を施した建材を指します。タイルの材質は陶器や磁器が使われており、部屋のアクセントにもなる建材です。木材は無垢板や合板で、幅広い樹種から選ぶことができます。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
クロス |
お手入れが簡単 色やデザインが豊富 費用が安い |
継ぎ目が目立つ 静電気が起きやすい 剥がれることがある 一定期間で張り替えが必要 |
塗り壁 |
質感を楽しめる 防音性・耐火性・耐熱性に優れる 調湿性が高い |
傷が付きやすい 汚れやすい お手入れが大変 |
化粧板 |
費用が安い 耐熱性・耐水性が高い 汚れにくい 色やデザインが豊富 |
仕上がりに差がある 作り物感がある 経年劣化が起きる |
タイル |
水に強い 耐久性が高い 汚れにくい |
費用が高い |
木材 |
質感・立体感を楽しめる 高級感・重厚感を演出できる 調湿性・吸音性が高い |
火に弱い 湿気が多いとダメージを受ける |
建具
建具とは、扉や窓といった開口部に取り付けられる建材です。建具には屋外と室内を仕切る外部建具と、室内同士を仕切る内部建具があります。外部建具は玄関の扉や窓、サッシなど、内部建具は部屋の扉やふすま、クローゼットの折れ戸など多種多様です。開閉形式による分類では、開き戸、引き戸、折れ戸などに分けられます。
材質による分類では、主に木製、アルミ製、樹脂製の3種類に分けられます。木製建具には無垢板や合板が使われ、木目の柄を印刷した化粧シート貼りの木製建具も多いです。アルミ製建具は耐久性があるため窓サッシや玄関などでよく使われています。樹脂製建具はプラスチックのことで、窓に使われる樹脂サッシなどが有名です。建具の材質は1つに統一するのではなく、用途によって使い分けることがポイントです。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
木製 ・無垢材 ・合板 ・化粧シート貼りなど |
お温かみのあるデザイン 加工しやすい 結露しにくい |
費用が高い メンテナンスが大変 |
アルミ製 |
費用が安い 耐久性がある 火災に強い |
結露しやすい |
樹脂製 |
結露しにくい |
費用が高い アルミ製より劣化しやすい |
防水材
防水材は建物を水から守るための建材です。雨漏りや漏水などによって、家の構造材が劣化するのを防ぎます。屋根や外壁、屋上、バルコニーなど、水の侵入が懸念される部分に使われます。
防水材の種類は、ウレタン防水、FRP防水、塩ビシート防水、アスファルト防水などです。ウレタン防水やアクリル防水は液状の防水材を流し込み、ゴム状の防水層を形成します。FRP防水はガラス繊維のマットを敷き、ポリエステル樹脂を塗って仕上げる方法です。塩ビシート防水は防水シートを貼る方法で、接着剤で貼り付ける密着工法と機械で固定していく機械固定工法があります。アスファルト防水は溶かしたアスファルトを使ってシートを貼っていく方法です。それぞれ以下のメリット・デメリットがあります。
ウレタン防水 アクリル防水 |
費用が安い ひび割れの心配が少ない 継ぎ目がない 複雑な形状でも施工しやすい |
均一な塗装が難しい |
FRP防水 |
ひび割れの心配が少ない 継ぎ目がない 軽量で強度がある 耐熱性・耐食性・耐候性が高い |
費用がやや高い |
塩ビシート防水 |
工期が短い 意匠性に優れる 耐久性・遮熱性が高い |
複雑な形状には不向き |
アスファルト防水 |
耐久性が高い |
施工できる業者が限られる 仕上がりに差がある |
建材の選び方
建材の選び方は、デザイン、費用、メンテナンスといった複数の視点で選ぶことが大切です。たくさんのデザインがあるため見た目で選ぶ方も多いですが、高額な建材やメンテナンスが大変な建材を選ぶと後で苦労する可能性があります。
建材は家の快適性も左右するため、ライフスタイルや家族構成まで考慮すると、自分に合ったものを見つけやすいでしょう。
まとめ
構造・工法や建材は種類が多くて選ぶのが大変ですが、費用や性能などの違いをしっかりと比較することが大切です。またハウスメーカーによって対応できる構造・工法が異なります。早めに希望の構造・工法を決めておくと、ハウスメーカー選びもスムーズに進められるでしょう。
住まいに関する研究所はハウスメーカーの選び方や予算の立て方など、家づくりに関するお悩みをサポート・解決します。家の構造・工法や建材についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

大手ゼネコンや大手ハウスメーカーを経て、木造の高級注文住宅を主とするビルダーを設立。土地の目利きや打合せ、プランニング、資金計画、詳細設計、工事統括監理など完成まで一貫した品質管理を遂行し、住まいづくりの経験は20年以上。法人の技術顧問アドバイザーとしても活動しながら、個人の住まいコンサルテイングサービスも行っている。