中学生のお小遣いは平均いくら?
渡すメリット・デメリットと一緒に解説

子どもが中学生になると、お小遣いの金額をいくらにすればいいのか迷ってしまうものです。 本記事では、中学生の子どもに渡すお小遣いの平均額や、お小遣いのメリット、デメリットを解説します。どのような方法でお小遣いを渡すか悩んでいる人も、ぜひ参考にしてみてください。
中学生のお小遣いの金額の平均は?
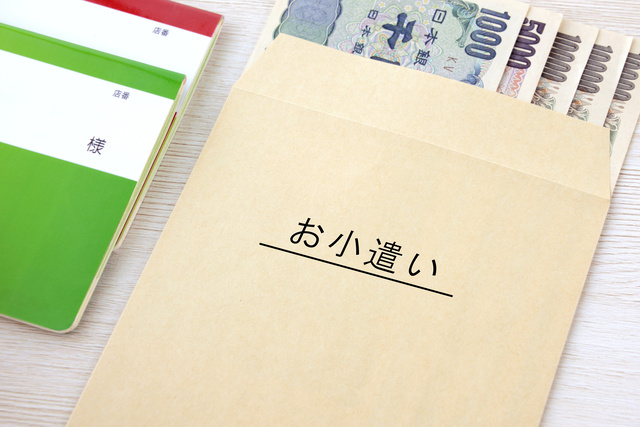
調査によると、中学生へのお小遣いの平均金額は2,536 円でした。
中央値は2,000円です。中央値とは、すべての数字を昇順に並べたときに真ん中になる数値のことで、平均値よりも正確な相場を把握することが可能です。
平均値と中央値の結果から、中学生の月のお小遣いの平均は2,000~2,500円前後であることがわかります。
参考サイト:金融広報中央委員会「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)
中学生にお小遣いを渡す頻度は?
同調査によると、お小遣いをもらっている中学生の割合は83.2%でした。内、無条件でお小遣いをもらえるのは74.2%、家事の手伝いなどでもらえるのが14.9%、いい成績を取ることが条件となっているのが5.8%、その他の条件が6.1%です。
多くの中学生が条件なしでお小遣いをもらっていることがわかりますが、なかには条件付きでお小遣いを受け取れるケースもあります。
中学生へお小遣いを渡すタイミングの平均は?

中学生の子どもには、どれくらいの頻度でお小遣いを渡すのが相場なのかを解説します。定期的に渡すべきか、必要なときだけ渡すべきか迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
定期的に渡す
定期的にお小遣いを渡すと、定められた期間で計画的にお金を使う習慣が身に付きます。毎月一定の金額と決めてしまえば、お小遣いの管理もしやすいでしょう。
ただし、お小遣いの金額が相場より低いと友達付き合いに支障が出たり、計画性が身に付くまではお小遣いが足りなくなったりする可能性もあります。お小遣いを渡す頻度は、家庭内で話し合って決めるといいでしょう。
必要なときに渡す
学校や塾などで何かを購入する必要があるときにだけ、渡すケースもあります。必要なときにだけ渡すと親が子のお金の使い方を把握しやすく、無駄がありません。
「このためにこれだけ必要だから」と、子どもがお小遣いの金額を交渉する力も身に付きます。ただし、必要になれば親に要求すればいいと考えてしまう可能性があり、計画性が育たないかもしれないことは理解しておきましょう。
中学生にお小遣いを渡すメリット

中学生にお小遣いを渡すメリットを3つ解説します。各家庭のお小遣いの金額や渡す頻度によってもメリットは異なるので、各家庭で最適な渡し方を考えましょう。
定期的に渡す場合
お金の大切さを理解できる
お小遣いを定期的に渡すことで、子どもは限られた予算のなかで生活することの大変さ、お金のありがたさを理解できるようになります。自分自身でお小遣いを管理させ、何にどれくらいのお金がかかるのか、今の自分に本当に必要な買い物なのかを考える機会を与えることが可能です。
子どものころからお金がいかに大切か、生活に結びついているかを理解できれば、お金に対する健全な考え方を持てるようになり、お金の使い方で失敗する可能性を低くできるでしょう。
お金を工夫して使う習慣がつく
定期的にお小遣いを渡すと、お金を工夫して使う習慣が身に付きます。このスキルは大人になってから一人暮らしをしたり、結婚して家計を切り盛りしたりする際にも役立つでしょう。
来月友達と遠くに遊びに行くから今月は節約して貯金しよう、新しいゲームがほしいから放課後の外食を控えようなど、計画的にお金を使える人間に育てることが可能です。
計画性が育つまでは、一緒にお小遣いの管理をしてあげてもいいでしょう。
必要なときに渡す場合
交渉するスキルが身に付く
定期的にではなく必要なときにだけお小遣いを渡す場合は、子どもの交渉力を養うことが可能です。交渉スキルは社会人になってからも、就職活動や営業職、サービス業などさまざまな仕事で役立ちます。
「この金額ではこのような理由で足りない」「今月テストでいい点を取ったからいつもより高い金額がほしい」など、明確な理由つきで交渉するようにすれば、論理的な思考も身に付くでしょう。
中学生にお小遣いを渡すデメリット
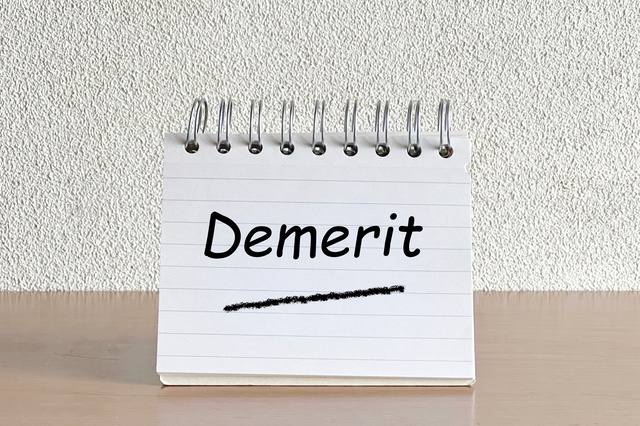
中学生にお小遣いを渡すデメリットも確認しておきましょう。子どもにお金の使い方を学ばせたい人は、お小遣いの渡し方によってはうまく育成できない可能性があることも理解しておかなければなりません。
定期的に渡す場合:親が子のお金の使い方を把握できない
一定のタイミングでお小遣いを渡すと、親が子どものお金の使い道を把握できないというデメリットがあります。一定金額を定期的に渡すのは親にとっては楽ですが、何にお金を使っているのかわかりません。
外食や遊びで無駄遣いをしている、友人にお金を貸しているなど、よくない使い方をしていても気づくのが遅くなってしまいます。子どものお金の使い方にどれくらい干渉すべきか、よく考えてお小遣いの渡し方を考えましょう。
必要なときに渡す場合:計画性が育たないケースもある
必要なときにだけお小遣いを渡す、お手伝いの報酬としてお小遣いを渡す方法では、お金の使い方に関する計画性が育たない可能性があります。必要なときに要求すればその分だけお金が手に入るため、お金のありがたみや限られた金額で上手にやりくりする力が育まれません。
必要な金額だけを渡すと貯金もしにくく、お金を貯める大切さや達成感などを経験できなくなるというデメリットもあります。
金額によってはトラブルに巻き込まれる可能性がある
与えるお小遣いの金額が周囲より高いと、子どもがトラブルに巻き込まれる可能性があります。友人にお金を取られたり、外食で支払わされたりするかもしれません。
反対にお小遣いの金額が少ないと、友人間の遊びの輪に入れず、交友関係をうまく築けない可能性もあります。上記で紹介した平均値も参考に、周囲の中学生の親は子どもにどれくらいお小遣いを渡しているのかを調査してみることもおすすめです。
まとめ
中学生のお小遣いの平均は2,000~2,500円前後ですが、実際の金額や渡す頻度、渡し方は各家庭によって違います。自分の家庭ではどれくらいの金額が相場なのか、どのようなスタイルで渡すべきかをよく考えることが大切です。
子どもにどのようなスキルを身につけさせたいか、どの方法が親と子にとってストレスや負担が少ないかなども話し合い、適切な金額、渡し方を決定しましょう。

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。







