扶養とは?
仕組みや対象となる範囲などをわかりやすく解説

扶養とは、収入が少ない家族を経済的に支えることを指します。扶養に入ると税金や保険料の負担が減るメリットがある一方、収入が制限されるなどのデメリットもあるのです。この記事では、扶養の仕組みや対象となる範囲、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
扶養とは?
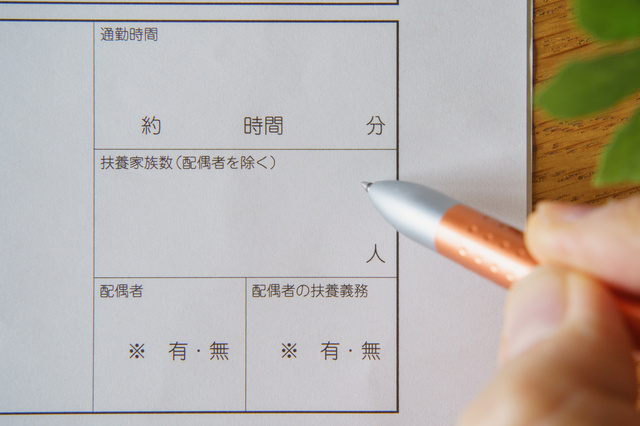
扶養とは、自分の収入だけでは生活できない家族や親族を、経済的に支援することを意味します。たとえば、世帯で収入が高い夫の扶養に、妻や子が入るケースです。支援する側(例:夫)を扶養者、支援される側(例:妻や子)を被扶養者といいます。
特に、税金や社会保険料において、扶養がポイントとなることがあります。その仕組みについて見ていきましょう。
扶養の仕組み
扶養には、所得税法上の扶養と社会保険法上の扶養があります。
所得税では、一定の要件を満たす親族を扶養していれば、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除などの所得控除を受けられます。控除が適用できれば税金の負担が軽減され、手取り額が増えます。
一方、健康保険料と厚生年金保険料において一定の要件を満たしていれば、社会保険料を上乗せせずに被扶養者も保険に加入できます。
扶養の対象となる範囲

扶養の対象となる範囲は、所得税と社会保険で異なります。所得税では扶養控除や配偶者控除などの対象となる要件を、社会保険では健康保険と厚生年金それぞれの被扶養者の要件を確認しましょう。
扶養控除(所得税)
扶養控除は、年間合計所得金額が38万円以下の子や親などと生計を一にしている場合に受けられる控除です。年齢と同居の有無によって控除額が決まっています。
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 老人扶養親族・同居老親等(70歳以上):58万円
- 老人扶養親族・同居老親等以外(70歳以上):48万円
なお、扶養控除には配偶者は含まれていません。配偶者がいる場合の納税者本人の控除は、次の配偶者控除か配偶者特別控除を確認します。
配偶者控除(所得税)
納税者(扶養者)に一定の配偶者がいる場合、控除を適用できます。控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者(控除対象配偶者)の年齢によって決まります。
一般の控除対象配偶者(70歳未満)の場合
- 納税者の合計所得金額:900万円以下→控除額38万円
- 納税者の合計所得金額:900万円超950万円以下→控除額26万円
- 納税者の合計所得金額:950万円超1,000万円以下→控除額13万円
一般の控除対象配偶者(70歳以上)の場合
- 納税者の合計所得金額:900万円以下→控除額48万円
- 納税者の合計所得金額:900万円超950万円以下→控除額32万円
- 納税者の合計所得金額:950万円超1,000万円以下→控除額16万円
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除の適用は受けられません。また、配偶者は次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと
青色申告者の事業専従者について、たとえば夫婦で店を営んでいて配偶者が従業員として給与を受け取る場合、事業専従者になれば一定の控除を受けられます。この事業専従者になっていると、配偶者控除を受けられません。
なお、配偶者控除の適用を受けられなくても、次の配偶者特別控除を適用できる場合があります。
出典元:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者特別控除(所得税)
「年間の合計所得金額48万円」を超えていると配偶者控除は対象外となりますが、配偶者特別控除の適用を受けられることがあります。配偶者特別控除の収入要件は、「年間の合計所得金額が48万円超133万円以下」であることです。
配偶者の所得要件として、48万円以下なら配偶者控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除に該当し、133万円超なら両方とも対象外となります。
出典元:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
なお、ここまで「所得」の要件を解説していますが、「収入」とは異なります。そのため、次に紹介する社会保険の収入要件と単純に比較できないため、注意してください。
たとえば、給与収入が130万円で、給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円の場合、所得金額は27万円です。基本的に給与収入から控除を差し引いて所得金額を求めますが、適用できる控除の額や種類は人によって異なり、所得金額も変わってきます。上記の例だと、ここまで解説した所得要件は27万円で判断し、次章で紹介する収入要件では130万円で判断することになります。
健康保険(社会保険)
健康保険では、本人(被保険者)の配偶者や子などについても、保障の対象になります。健康保険の被扶養者になるためには、次の要件を満たす必要があります。
被扶養者のおもな要件
- 被保険者と同一世帯に属していること
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円未満)であること
- 被保険者の年収の2分の1未満の収入であること
要件を満たさなければ各自で健康保険に加入しなければならず、保険料が発生します。収入基準を少しだけ上回る程度だと、支払う保険料の分の手取額が減るため、注意が必要です。
厚生年金(社会保険)
厚生年金保険も健康保険のように一定の条件を満たせば、保険料を追加しなくても扶養家族を加入させられます。
具体的には、会社員や公務員は第2号被保険者として厚生年金保険に加入しますが、その配偶者は、第3号被保険者として加入できます。第3号被保険者になるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 第2号被保険者の配偶者であること
- 20歳以上60歳未満であること
- 年収が130万円未満であること
ただし、60歳以上の配偶者や障害厚生年金を受給している配偶者の場合、年収が180万円未満であれば第3号被保険者になれます。さらに同居している場合は、配偶者の収入が被保険者の収入の半分未満という条件を満たす必要があります。これらの点は、健康保険と同じ条件です。
扶養のメリットとデメリット
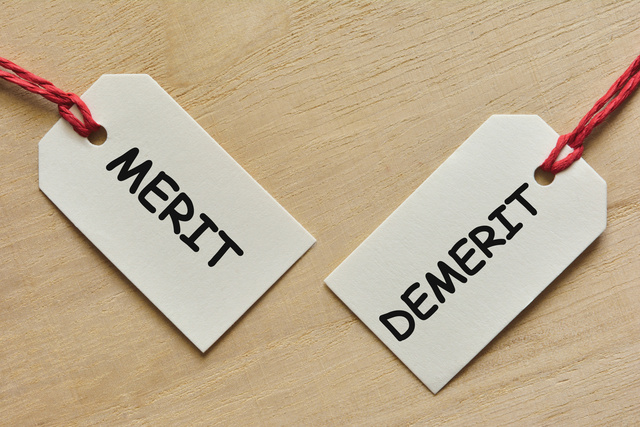
扶養には、税金や保険料の負担が減るなどのメリットがある一方、収入が制限されるなどのデメリットもあります。ここでは、扶養のメリット・デメリットをまとめます。
メリット
所得税において扶養に入るメリットは所得控除の適用を受けられるだけではなく、税金の負担が減り手取額が増えることも挙げられます。社会保険におけるメリットは、被扶養者にとって保険料の負担がなくても健康保険の保障を受けられ、厚生年金により将来受け取れる年金額が増える点です。
なお、扶養者が支払うのは厚生年金保険料ですが、被扶養者は第3号被保険者として国民年金保険に加入していることになります。
デメリット
扶養制度の存在により、収入を一定以下に抑えようとする心理が働くことがデメリットの1つです。特に、働ける時間と意欲があるにもかかわらず扶養の範囲内に収入を抑えなければならないため、本来の稼得能力(収入を得る力)を発揮できない可能性があります。
また、扶養から外れて社会保険料の負担が発生する場合、フルタイムで働くことで手取額を増やせる一方、時間的な制約からフルタイムで働けない場合は、扶養の範囲内で働くことを選択せざるを得ないケースもあります。
さらに、扶養にこだわってしまうと、将来の年金額が減少するリスクがあります。扶養を外れて厚生年金保険料を負担することで将来の年金額は増加しますが、扶養に入り続けることで老後の資金準備が不十分になる可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。扶養に入ることで税金や保険料の負担が減る一方、収入が制限されるなどのデメリットもあるため、自身のライフプランに合わせて慎重に判断することが大切です。

2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。







