投資と貯金の割合はいくらがよい?
運用にあたってのメリットと注意点をあわせて解説

「投資と貯金の割合はどのくらいがいいか」「どのくらいの資金を投資しているのか」気になっている人もいるでしょう。この記事では、投資と貯金の割合についての調査結果と、基本的な資産配分のパターンや運用のポイントについて解説します。
投資と貯金の割合は?
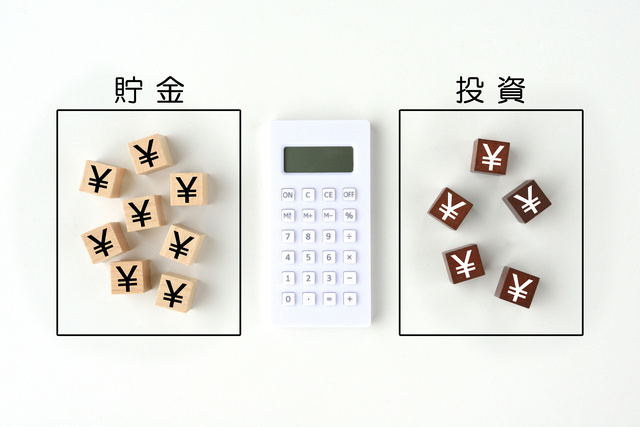
投資と貯金のバランスは、個人の財務状況や将来の目標によって異なります。各世帯がどのような割合で資産を配分しているか確認していきましょう。
二人以上世帯の金融資産の特徴
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、2023年における二人以上世帯の総金融資産額(平均)は1,307万円で、その内訳は以下のとおりです。
- 預貯金:563万円(43.1%)
- 有価証券:427万円(32.7%)
- 保険:257万円(19.7%)
- その他金融商品:59万円(4.5%)
参考元:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果」
預貯金が最も多いですが、有価証券も3分の1近くを占めており、比較的バランスの取れた資産配分となっています。保険への投資も約5分の1を占め、長期的な安全性にも配慮していることがわかります。
単身世帯の金融資産の特徴
同様に、2023年における単身世帯の総金融資産額(平均)は941万円で、その内訳は以下のとおりです。
- 預貯金:408万円(43.4%)
- 有価証券:372万円(39.5%)
- 保険:129万円(13.7%)
- その他金融商品:31万円(3.3%)
参考元:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和5年調査結果」
単身世帯は預貯金の割合が二人以上世帯とほぼ同じですが、有価証券の割合が高く、保険の割合が低い傾向があります。保険で補うリスクが少ない分、投資に資金を回していると考えられるでしょう。ただし、資産の順位は同じため、大きな差はありません。
投資と貯金の割合を考える

先ほどの調査結果をもとに、投資と貯金割合について考えてみます。投資といっても株式や投資信託、国債などさまざまありますが、ここでは単純に投資と貯金のみの割合で解説します。
以下で紹介するモデルは一般的な指針であり、財務状況やリスク許容度、投資目標に応じて調整が必要です。定期的に見直し、必要に応じてリバランス(資産の再配分)しましょう。
バランス型
預金と投資の割合がそれぞれ50%ずつの場合は、バランス型になります。現役世代が資産を形成し、中長期(5~10年)で資金を運用するのに適したモデルです。リスクと安全性のバランスを取りながら、成長の機会も得られます。余剰資金の半分を預金で運用すると、緊急時の資金需要に対応しやすくなります。
ただし、投資で大きな損失が出ると、預金だけでは補えない可能性もあるでしょう。前述の調査結果は、このバランス型に近いと考えられます。
安全性重視型
預金が70%で投資が30%の場合を、安全性重視型といいます。老後資金の運用や比較的短期(3~5年)の資金需要に適したモデルです。安全性を重視しながら、緩やかに資産を増やします。年金を中心に生活し、大きなリスクは避けながらインフレ対策として投資信託も活用します。
損失が生活に影響する場合は、安全性重視型をベースに資産を配分しましょう。
積極運用型
預金が30%で投資が70%の場合は、積極運用型になります。若年層の長期投資や、余裕資金の運用に適したモデルです。高いリターンを目指しながら、長期的に資産を増やします。
20代や30代は今後収入が増えるため、比較的リスクを取れるでしょう。緊急時に備えた資金は預金で管理し、余剰資金は投資に回します。
投資と貯金の割合を決めるポイント

ここからは、投資と貯金の割合を適切に保つために、生活防衛資金の確保、年代別の資産配分、定期的な見直しのポイントを解説します。
投資を始める前の資金計画
投資未経験者は、投資と貯金のバランスを考えながら準備を進めることが大切です。まず、生活防衛資金として最低限の預金を確保します。目安として3〜6ヶ月分の生活費を確保し、急な失業や収入減に備えましょう。
また、緊急時の医療費や住宅・自動車の修理費に備え、別途資金を確保することが大切です。金額は個人の状況によりますが、年間収入の5〜10%が目安です。
生活防衛資金と予期せぬ出費の備えを確保した後、残りの資金で投資額を決めます。このとき、自分の収入や支出、将来の計画などを考慮し、無理のない範囲で投資額を決めることが大切です。
年代・目的別の資産配分の考え方
資産配分を考える場合は、年齢や目的を考慮することが大切です。
年齢による考え方
資産形成期の若年層はリスク許容度が高いため、積極的な投資ができます。ただし、若年層は投資経験が浅く、一攫千金を狙う投資に注意が必要です。余剰資金の範囲内で投資をしましょう。
資産充実期の中年層は投資経験を生かし、積極的に資産を増やします。収入が安定し、若年層より資金に余裕が生まれやすい時期です。一方で、支出が増えるため、家計の管理も重要です。
退職準備期の高年層は、蓄えた資産を守ることが中心です。すべてを預金にせず、インフレリスクに備えて無理のない範囲で資産運用をすると安心です。
それぞれの年齢層による資産配分の例は以下のとおりです。
- 若年層:預金30%、投資70%(株式60%、債券10%)
- 中年層:預金50%、投資50%(株式30%、債券20%)
- 高齢層:預金70%、投資30%(株式10%、債券20%)
目的別の考え方
また、目的別に資産配分を考える方法もあります。5年後に住宅を購入する場合、安全性を重視し、預金比率を高めます。住宅の購入が10年後なら、収益性を高め、運用成果がよければオプションの追加が可能です。運用成果の影響で、住宅を購入できなくなることを防ぎます。
定期的な見直しの重要性
投資と貯金の割合を決めた後、運用しながら資産配分の変化を確認します。定期的に割合を確認して見直すことで、資産状況や市場環境の変化に対応し、計画通りの資産配分を維持できます。年1~2回の定期的な見直しに加え、結婚、転職、引越しなどのライフイベント前後も見直しのよいタイミングです。
長期投資では、リスク許容度をもとに資産配分を決め、定期的に見直してリスクが高くならないよう調整します。短期的な市場変動に左右されず、定期的な積立投資で平均取得単価を抑えましょう。投資対象を分散し、リスクを抑えながら資産を増やします。
リバランスとは
リバランスとは、定期的に運用状況を確認し、資産配分を元の状態に戻すことです。運用を続けると、投資と貯金の割合が変わることがあります。たとえば、投資信託の価値が上がると、投資の割合が増えます。投資の割合が増えると、リスク許容度を超える可能性があるため、リバランスで調整するのです。
まとめ
投資と貯金の割合は、収入、年齢、リスク許容度、目的などによって異なります。生活防衛資金を確保したうえで、バランス型、安全性重視型、積極運用型など、自分の状況に合った資産配分を選ぶことが大切です。定期的に見直しとリバランスを行い、長期的な資産形成を目指しましょう。

2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。








