より多くの子どもたちが
家庭の中で過ごせることを目指す里親制度

親の病気や貧困、育児放棄など、様々な理由で家族と離れて暮らす子どもたちは、全国で約4万2千人います。こうした子どもたちは、児童福祉法の規定に基づき、児童相談所は、乳児院・児童養護施設などへの入所や里親・ファミリーホームへの委託を推進しています。
今回はその中でも「里親」の重要性について、「えひめ里親サポートセンターコイノニア」の門屋成美センター長と、森下佳一郎さんにお話をお伺いしました。
「里親制度」とは

「里親制度」とは、子どもが一定期間、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境で育てられる、子どものための制度で、様々な事情で家族と離れて暮らす子どもを自分の家庭に迎え入れて養育するのが「里親家庭」です。
子どもが幸せに育つためには、安全で安心できる家庭環境の中で、特定の大人と安定した愛着関係を築くことが子どもの自己肯定感を育むために大切だと言われています。
また里親制度には、「季節里親」という場合もあり、例えば、毎年夏休みに1泊2日でもいいから、同じ里親さんに継続的に定期的に会うことで、子どもの自己肯定感に繋がることも。
現在日本には家族と離れて暮らしている子どもたちの多くが、乳児院や児童養護施設で生活をしています。
この数は先進諸国と比べても圧倒的に多く、日本全体でも里親家庭を増やしていく取り組みを行っています。
里親と養子縁組の違い

ところでみなさんは、里親と養子縁組が大きく違うことをご存じでしょうか。
恥ずかしながら筆者もこの2つを同じようなものだと捉えていましたが、じつは全く別物だということが今回の取材で分かりました。
養子縁組制度は民法に基づいて法的な親子関係を成立する制度で、子の親権者は養親となります。
一方里親には親権はなく、養育に必要な里親手当などが支給され、一定期間委託型で養育していくものとなります。
ここで里親の委託にもいろいろな種類がありますのでご紹介します。
①養育里親
様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親
②養子縁組里親
将来養子縁組によって養親になることを希望する里親
③専門里親
虐待・非行・障害などにより専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親
④親族里親
実親が死亡などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親
⑤週末里親
正月・長期休み・週末などに数日~1週間程子どもを家に迎え入れる里親
なかなか普及されない「里親制度」

ある研究結果によると、里親には国からの経済的な補助があることをほとんどの人が知らなかったことが明らかになりました。
里親を考えたことはあるけど経済的な不安から行動していない方が数多くいて、里親には手当が出るといった経済的サポートがあることや、短期間のみの里親委託があることなどをもっと多くの人に伝えることで、最終的に里親希望者はかなり増える可能性があると言われています。
また里親になるためには、養育に対する熱意があり、経済的に困窮していない人であれば特別な資格はいらないのも特長の一つ。独身の場合も条件によっては里親になることが可能なことから、人によっては思っているよりもハードルが高くないこともポイントです。
愛媛県の里親支援センターの設置について

愛媛県でも約500人の子どもたちが様々な事情で家族と離れて暮らしています。
令和2年3月に策定された愛媛県社会的養育推進計画では、社会的養護を必要とする子どもについては、家庭養育優先原則を念頭に、子ども一人ひとりの意向を踏まえた方針決定ができる体制を整備する方針の下、里親委託の推進に取り組むことが決められました。
そして、令和6年3月に愛媛県里親支援センター運営業務の公募(2団体)を行い、同年8月からセンター運営業務が開始。
愛媛からは「子どもリエゾン(NPO法人子どもリエゾンえひめ)」と今回取材に応じていただいた「えひめ里親サポートセンターコイノニア(社会福祉法人コイノニア協会)」の2団体が委託され、里親支援の運営を行っています。
現在愛媛の里親登録全体数は324人、社会的養護の子どもの人数は約500人。そのうち家庭(里親委託+ファミリーホーム)で養育されている子どもは、約30%にとどまっていて、他の子はまだ施設で生活している状況です。
里親と里子のマッチングが非常に難しく、里親の数をさらに増やしていくことが最優先課題とのことです。
「社会福祉法人コイノニア協会」の取り組み

今回愛媛県から里親支援事業の委託を受けた「社会福祉法人コイノニア協会」は、1945年戦災孤児の救済からスタートし、これまで児童福祉一筋で事業を展開してきました。
これまでに養子縁組を含む70件余りの里親委託を経験してきて、里親委託の必要性を現場感覚として感じている施設です。
現在、法人内に乳児院と児童養護施設が2つ、そして認定こども園と夜間保育所があり、グループ内には学校法人の幼稚園と認定こども園があります。
- 児童養護施設(松山信望愛の家・今治あすなろ学園)
- 松山乳児院
- 夜間保育所ふくろうの家
- 認定こども園コイノニア幼児園
- 愛媛里親サポートセンターコイノニア
今回発足した「えひめ里親サポートセンターコイノニア」Ehime Foster parents Support center Koinonia(EFSK/エフスク)では、社会福祉法人コイノニア協会の第6番目の児童福祉施設として、2024年8月より、松山乳児院の敷地内において事業をスタートしました。
里子・里親・実親の3者のニーズに応えることをコンセプトに、養育里親のところには定期的な訪問を行い、チーム(里親・児童相談所・施設・地域)養育を遂行しています。

また、未養育里親に関しては、施設内のマッチングルームで、里親と里子が一緒に過ごすことができる空間を提供。
以前養育里親が久しぶりに施設に来られ、マッチングルームを見ながら、「あの時この場所であの子と出会った」と言って涙を流されていた方もいたそうです。
また里親同士の交流イベント「里親カフェ」を実施したり、里親子交流などのイベントを充実させたりといろいろな活動を実施しています。
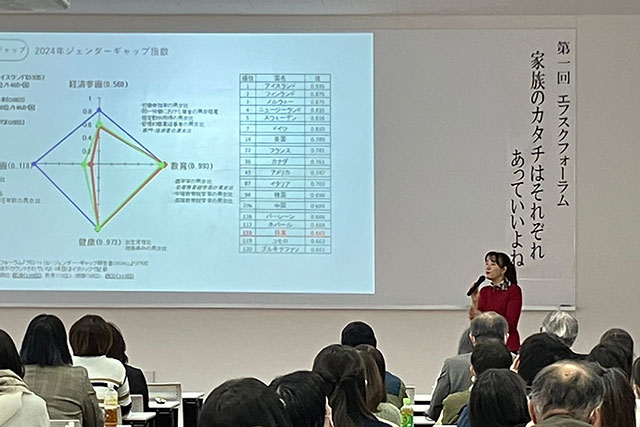
「EFSK」のオリジナルキャラクターとロゴマークについて

EFSK公式イメージキャラクターのイルカ「えふるかさん」。
イルカは他のグループの子どものイルカも大切に育てる里親行動をする動物です。
「EFSK」も里親さんや各関係機関と互いに助け合い、みんなで子育てをしていきたいと考えているそうです。

こちらは「EFSK」のロゴマーク。
赤丸は里子さんを、黒丸は里親さんを、その下の曲線は「EFSK」を表現しています。
里子を赤色で表現したのは、生命の輝きを表現し「かけがえのない命」であることを意味していて、里親さんとエフスクが同じ色なのは、里子の幸せを一緒に支えていきましょうという想いが込められています。
「EFSK」のこれまでの活動

2024年8月に発足してからチラシ・リーフレット・キャラクター・ロゴマークの自主作成や、市町の子育て支援課・社会福祉協議会窓口への広報活動、TVや広報誌の取材、里親月間普及啓発活動などを行い、広く里親制度について周知する取り組みを行ってきました。
また、里親登録される方向けに
- 里親制度相談会
- 電話やメールでの相談受付
- 里親登録に向けた研修
- イベント開催
などを実施。
特に「里親制度について知りたい」「子どものために何かしたい」など少しでも興味のある方のために「えふるかふぇ」を定期的に開催しています。
また里親になった人へのサポートとして、
- 電話や訪問による里子養育のサポート
- 里親のスキルアップ研修
などを行っています。
また里子への支援としては、
- 訪問によるサポート
- 自立へ向けた支援
を実施しています。
さて、実際に里親登録をした人の志望動機をお二人にお伺いしたところ、「社会貢献がしたい」「本当は養子縁組で子どもを育てたいが、年齢が高くなり体力的にも自信がないので里親として子どもを養育していきたい」という人が多いそうです。
ここで少しでも里親について気になる方、特に不妊治療をしている人は、並行して里親制度にも登録しておくことを強くお勧めしますとのことでした。
里親制度に登録してもすぐに子どもと暮らせるわけではなく、里親と里子がなかなかマッチせず、中には何年も話が来ない場合もあるという認識が大切ですとのこと。
そして養育里親になった場合、子育てに疲れたときや行き詰ったときにはレスパイトの仕組みで、一時的に別の里親や施設に預けることも可能。
また、毎月十分な手当てもあり、その子が自立するための支援も充実しているので、「里親制度」を正しく理解することが重要ですとおっしゃっていました。
里子を迎え入れたときの問題点とその対策について

養育里親になってからの悩みの声について、森下さんに伺いました。
生活のさまざまな場面において、育った環境やトラウマ的な経験が要因となり、大人からは「問題行動」と見えたり、適切な関係性を築くことに難しさを覚えたりする子もいます。
そのため養育がスタートすると、日々の生活に悩む里親も多いため、今後さらなる里親研修の充実をはかり、里親一人で育てていくのではなく、社会全体で育てていくよう児童相談所や施設との連携も強化していっています。
また、里親家庭の子どもの親権は生みの親なので、生みの親とも連絡が取れる状態にある子どもも少なくありません。親子としてのつながりを持ち続ける子どもや、生みの親や親族と交流しながら家庭復帰を目指す子どももいる現状の中で、里親の心理状態のケアにも努めています。
他にも、病院での受診券は、里親家庭は児童福祉法に基づき児童相談所が発行した「受診券」を持って医療機関を受診し、保険証がない場合でも本人負担はないのですが、まだ病院側に周知されていないことが多いのも現状です。
また、銀行口座を開設したり、各種サービスを契約するとき、里子の保護者を里親が担うことがありますが、保護者の苗字が異なることから何度も説明や書類提出を求められたりすることがあるそうです。
そうならないためにも、「えひめ里親サポートセンターコイノニア」では、公的機関などに実際に出向いて周知を行っているそうです。
「えひめ里親サポートセンターコイノニア」の今後の展望

「えひめ里親サポートセンターコイノニア」のこれからについてお二人に伺いました。
里親が地域でも意見表明ができやすい社会にするため、地域・施設などにも「里親制度」について周知徹底を行い、社会全体で里親を支援できる仕組みを作っていきたいです。
今後、里親は地域の資源として地域全体で守っていく仕組みを作るのと同時に、里親登録数の向上に向けた新たな里親開拓や、里親への研修・支援などを行い、スキルアップ研修・要保護児童の交流体験などを通じ、里親受託数の向上を目指したいです。
そして里親制度や特別養子縁組制度が普及しないのは、圧倒的な情報不足が一つの原因。
里親には経済的な支援があり短期委託も可能。
制度への理解が進めば、多くの子どもが家庭を得られる可能性があるので、個人宅や病院・銀行などの公的機関などにも直接訪問し説明をする「出前里親制度説明会」なども充実させていきたいと語っていました。
気軽に足を運んで!里親カフェ「えふるかふぇ」

「里親制度について知りたい」「子どものために何かしたい」など少しでも興味がある人や、話を聞いてみたい人を対象にしたイベントが月に2回実施されています。
場所や時間などはホームページを確認してくださいね。
- 参加費無料(1ドリンク付き)
- 各日定員10名程度
- 託児有(要予約)
みなさん、「里親制度」についてご理解いただけましたでしょうか。
十分な手当もあり、社会的なサポートも充実している「里親制度」。
これから過ごす人生の中に、子どもとの幸せな時間も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
「社会福祉法人コイノニア協会」の略歴

| 1945(昭和20)年7月20日 | 松山市街中心部が米軍爆撃機により空襲を受け、その大半が焼失した直後、その惨状の中で、聖書研究グループ「コイノニア」のメンバーたちは、祖国再建・戦災孤児救済に立ち上がることを決意。 |
| 1947(昭和22)年5月4日 | 「恩賜財団同胞援護会コイノニア弘済院」を国庫補助により建築し、事業開始。 |
| 1947(昭和22)年7月20日 | 松山市の要請により「コイノニア幼稚園」を弘済院に併設。 |
| 1948(昭和23)年4月1日 | 「コイノニア弘済院」を「コイノニア協会」に名称変更。児童の施設を「養護施設 松山信望愛の家」と命名。 |
| 1948(昭和23)年10月15日 | 「松山信望愛の家」は児童福祉法による児童福祉施設として認可を受ける。1953(昭和28)年12月1日定員数100名認可。 |
| 1953(昭和28)年3月31日 | 働く婦人の相談受付から「松山乳児預かり所」を松山市清水町に設立。同年12月1日施設名を「松山乳児院」に変更。定員45名。 |
| 1954(昭和29)年2月5日 | 「社会福祉法人コイノニア協会」として法人認可がなされる。 |
| 1956(昭和31)年6月1日 | 「松山信望愛の家」の処遇改善を目的として「養護施設あすなろ学園」を松山市平和通に設立、定員25名。松山信望愛の家は定員数75名に変更。 |
| 1959(昭和34)年1月30日 | 「松山信望愛の家」は借地契約が切れ、松山市久万ノ台251番地1(現在地)に用地購入移転新築。用地面積2221.48平方メートル。建築面積887平方メートル(木造平屋建て)。1968(昭和43)年隣接地にグラウンド用地の873平方メートルの土地取得。 |
| 1959(昭和34)年4月1日 | 「あすなろ学園」は今治市波止浜樋口に新築移転。同年6月1日、定員50名で認可される。 |
| 1966(昭和41)年11月30日 | 「松山乳児院」は松山市久万ノ台173番地に新築移転。同年12月1日定員40名に変更。 |
| 1984(昭和59)年3月20日 | 「松山信望愛の家」は本体施設の老朽化により、「民間老朽社会福祉施設整備補助事業」の国庫補助を受け、隣接グラウンドに新施設を建築竣工。鉄筋コンクリート造一部3階建て。建築面積936.9平方メートル。 |
| 1992(平成4)年9月25日 | 「松山信望愛の家」は競輪補助金と一寄付者による自己負担金充当により「地域交流ホーム愛の家」竣工。 |
| 2004(平成16)年3月18日 | 「松山乳児院」は地震対策として社会福祉施設等施設整備の補助金を得て、全体を改築し竣工。 同時に併設施設として、「コイノニア保育園」定員60名と「夜間保育所ふくろうの家」定員20名を建設同年4月1日開設した。 |
| 2006(平成18)年4月1日 | 「あすなろ学園」は敷地内に小規模グループケア施設「初穂の家」を建設し運営を開始。 |
| 2008(平成20)年2月28日 | 「松山信望愛の家」は競輪補助金により「小規模グループケア施設オレンジハウス」竣工。 |
| 2009(平成21)年4月1日 | 「松山信望愛の家」は「地域小規模児童養護施設 北さやハウス」を開設。2013(平成25)年10月28日、木屋町に移転「ラズリハウス」に改称。 |
| 2013(平成25)年4月1日 | 「あすなろ学園」は木造2階建て1326.2平米のユニット型施設に全面建て替え。 |
| 2015(平成27)年4月1日 | 保育所新制度に伴い「コイノニア保育園」は「認定こども園コイノニア保育園」に認定される。 |
| 2017(平成29)年4月1日 | 「松山信望愛の家」は「地域小規模児童養護施設 ラズリハウス」を閉鎖。<次世代育成支援対策施設整備交付金事業>により、施設を全面建て替え。隣接グラウンドに三棟からなる10ホームの小規模グループケア施設を建築使用開始。既存施設は、給食施設と食堂ホールを残すこととした。 「あすなろ学園」は今治市地掘に地域小規模児童養護施設「おおはしホーム」を開設。 |
| 2018(平成30)年4月1日 | 「松山乳児院」は、本体施設の南側隣接地(松山市久万ノ台171-1)に「小規模グループケア施設 はぐくみの家」を開設。 |
| 2021(令和3)年4月1日 | 保育所型認定こども園「コイノニア保育園」を廃止し、幼保連携型認定こども園「認定こども園コイノニア幼児園」に移行。 |
| 2023(令和5)年10月30日 | 「松山乳児院」は、小規模グループケア施設はぐくみの家を増改築竣工。11月1日から全入所児が「はぐくみの家」で生活することとなった。 |
| 2024(令和6)年4月1日 | 「松山信望愛の家」は一時保護専用施設(定員6名)を開設。 「あすなろ学園」は今治市高部に分園型小規模グループケア施設「旭方ホーム」を開設。 「松山乳児院」は定員30名に変更。一時保護専用施設(定員6名)を開設。 |
| 2024(令和6)年8月1日 | 「えひめ里親サポートセンターコイノニア」を開設。 |







