投資信託の「利回り」とは?
計算方法や選び方などをわかりやすく解説
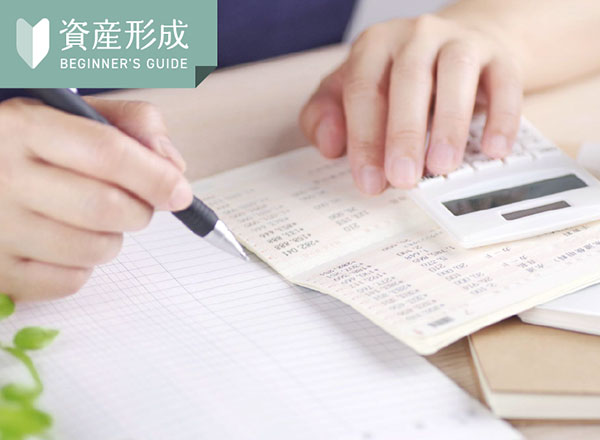
「利回り」は投資信託の成果を測る重要な指標ですが、その意味や計算方法を正しく理解することが大切です。本記事では、利回りの基本や計算方法、関連する指標との違いを初心者にもわかりやすく解説します。投資信託の選び方についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
投資信託の「利回り」とは

まずは、投資信託における利回りの意味や、ほかの指標との違いを解説します。
利回りとは?
利回りとは、投資した金額に対して得られる収益の割合を示す指標で、年率で表示されるのが一般的です。投資信託だけでなく、株式や債券、不動産投資などでも使われます。
利回りは投資額と収益額で計算されますが、次の要素によって意味が変わります。
利回りの要素
- 収益の種類:分配金、売却益(または両方)
- 期間:1年間、所有期間全体、任意の期間
- 費用の考慮:費用を含むか含まないか
利回りのうち、費用を含む場合は実質利回り、含まない場合は表面利回りと呼びます。計算期間が1年以上の場合、1年に換算して年平均利回りと記載されることがあります。
理解しておきたい投資信託の「利回り」
投資信託を購入した後に利回りを計算すれば、保有を続けるか売却するかの判断材料にできます。
しかし、投資信託を選ぶときは、利回りではなく、騰落率(とうらくりつ)やトータルリターンが指標として使われることが多いです。また、騰落率やトータルリターンの定義は金融機関によって異なり、わかりにくいことがあります。
投資信託の経験がない人には、少し難しく感じるかもしれません。指標を参考にするときは、「収益の種類」「期間」「費用が考慮されているか」を確認することが大切です。
騰落率とは
騰落率は、6ヶ月や1年、3年などの一定期間、基準価額がどれだけ上がったり下がったりしたかをパーセンテージで示したものです。比較やランキングでは、分配金を加えた基準価額をもとに計算されることがあります。売買手数料、信託財産留保額、運用管理費用(信託報酬)などの手数料は含まれません。
「騰落率10%」と記載されている場合、分配金が含まれているか、どの期間の数値か、年率換算か、費用が含まれているかを確認し、その意味を理解してから比較しましょう。
トータルリターンとは
トータルリターンは、購入日から算出基準日までの収益額を示したものです。投資信託では、一定期間の分配金を含めた基準価額の上げ下げをパーセンテージで表すのが一般的です。売買手数料に加え、信託財産留保額や運用管理費用(信託報酬)も含まれます。
投資信託で想定される利回りと計算方法
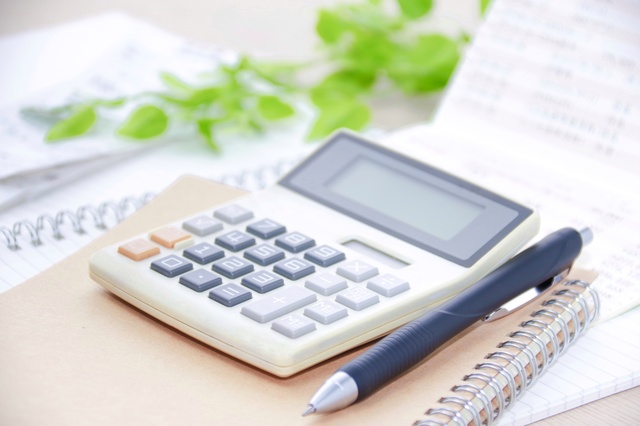
ここからは、想定される利回りと計算方法を紹介します。
投資信託で想定される利回り
金融庁の「NISA早わかりガイドブック」によると、1989年以降、毎月同額を国内外の株式と債券に積み立て、20年間運用すると、100万円が186万円~331万円になると試算されています。年平均利回りは4~6%程度(ガイドブックでは投資収益率や年間収益率と表記)を期待できる計算です。
利回りの計算方法
利回りは、以下の計算式で求めます。
| 利回り =(分配金 + 売却価格 - 購入価格)÷ 購入価格 × 100 |
さらに、具体例で理解を深めていきましょう。
1年間の分配金と売却益がある場合
購入価格が100万円で1年間の分配金合計は3万円、1年後の売却価格は105万円で計算してみましょう。
| (3万円 + 105万円 - 100万円)÷ 100万円 × 100 = 8% |
この場合、利回りは8%となります。
分配金のみを受け取る場合
購入価格が50万円で、1年間の分配金合計1.5万円のみを受け取る場合の計算は以下のとおりです。
| (1.5万円 + 0万円 - 0万円)÷ 50万円 × 100 = 3% |
この場合の利回りは、3%となります。
売却損が出た場合
購入価格が200万円で1年間の分配金合計は5万円、1年後の売却価格が190万円の場合の計算を見ていきましょう。
| (5万円 + 190万円 - 200万円)÷ 200万円 × 100 = -2.5% |
この場合の利回りは、-2.5%です。
投資信託の選び方

投資信託にはさまざまな種類があり、どれを選ぶか迷うことも多いでしょう。ここでは、投資信託を選ぶ際のポイントを3つに分けて解説します。商品の特徴を理解して目的を明確にし、リスクの許容範囲を把握することで、自分に合った投資信託を選びやすくなります。
投資信託の商品性の理解
投資信託を選ぶ際は、投資対象の資産クラス(株式、債券、不動産など)や投資地域(国内・海外、先進国・新興国など)を検討します。投資の目的やリスク許容度をもとに、「債券・国内外」といった基本となる投資対象を決めます。
投資対象が決まったら、利回り、騰落率、トータルリターンなどの指標を参考に、最終的な投資先を選びます。これらの指標を見るときは、「収益の種類」「期間」「費用が考慮されているか」を確認しましょう。投資信託を選ぶことで商品の特徴を理解し、自分の目的に合った投資先を見つけやすくなります。
目的の明確化とリスク許容度の把握
投資信託を選ぶ際は、投資の目的を明確にすることが大切です。老後資金や教育資金、住宅購入資金など、目的によって適した投資期間や商品が異なります。例えば、老後資金なら長期運用が可能ですが、数年後に必要な資金なら安全性を優先しましょう。
また、自分のリスク許容度を正しく把握することも重要です。リスク許容度とは、投資の値動きや一時的な損失をどの程度受け入れられるかを示す指標です。「安定志向」なら債券型ファンドなど値動きの小さい商品を、「積極志向」なら株式型ファンドなど値動きが大きくても長期で高いリターンを狙える商品を検討します。
分散投資とポートフォリオ
分散投資は、リスクを減らすための重要な戦略です。投資信託は多数の銘柄に分散されていますが、複数の投資信託を組み合わせると、さらにリスク分散の効果が高まります。
効果的な分散投資のポイントは、以下のとおりです。
効果的な分散投資のポイント
- 資産:株式・債券・不動産など
- 地域:国内・海外など
- 投資スタイル:バリュー投資・グロース投資など
また、一度に大きな金額を投資するのではなく、定期的に少額ずつ投資するとリスクを抑えられます。ポートフォリオは年齢や投資目的、リスク許容度に合わせて作り、定期的に見直すことが大切です。
まとめ
投資信託の利回りは、投資額に対する収益の割合を示す重要な指標です。騰落率やトータルリターンとの違いを理解し、投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことが大切です。また、分散投資を取り入れたポートフォリオを作り、長期で安定した資産形成を目指しましょう。

2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。








