給与所得控除とは?
対象者・計算方法・申告方法をわかりやすく解説
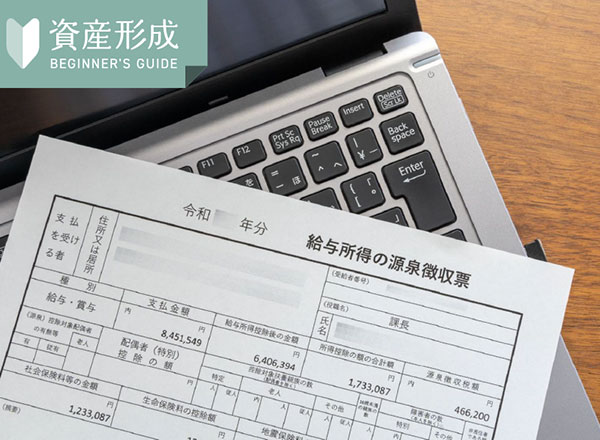
給与所得控除とは給与所得者が受けられる所得控除のことで、所得税の計算や申告に関わる制度です。税金についての用語や計算方法を理解したうえで、手続きすることが大切です。この記事では、給与所得控除の対象者や計算方法について解説し、申告のやり方まで紹介します。
給与所得控除とは

まずは、給与所得控除に関する仕組みについて解説します。
給与所得者が受けられる控除
給与所得控除は所得税の対象となる給与等から、年収に応じて一定額を控除するための制度です。個人事業主は事業にかかる費用を経費として計上し、確定申告で売上から差し引いて課税所得を計算します。
一方で、給与所得者は年末調整で年間の収入等を算出するため、経費という考え方がありません。給与所得者でも仕事をするうえで一定額の費用はかかっているとみなし、年収に応じて控除するのが給与所得控除の役割です。
基礎控除などの所得控除との違い
所得控除は所得税の計算に適用される制度です。全部で15種類あり、基礎控除はそのうちの1つです。給与所得控除は15種類の所得控除に含まれず、給与所得者のみに適用される制度です。
所得控除と似た名称の制度に、税額控除というものもあります。所得控除は、所得税がかかる対象となる課税所得の計算に用いられます。
一方で、税額控除は算出された所得税額から差し引くものです。控除という表現でイメージが似ているため混同しやすいですが、別の制度として理解しておきましょう。
所得控除一覧
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 雑損控除
支出額が一定を超えると特定支出控除の対象になる
給与所得者は給与所得控除が適用されますが、もしそれ以上の費用がかかった場合には特定支出控除の対象になります。給与所得控除は概算された必要経費として年収に応じて決まりますが、これを超えたときは条件を満たせば控除されるのです。
特定支出控除には8種類あり、給与所得控除の半分を超える支出額が対象です。特定支出が給与所得控除の半分を超えない場合は、特定支出控除の対象外です。
特定支出控除の計算方法
- 特定支出の金額-(給与所得控除の金額÷2)=特定支出控除の金額
| 特定支出の種類 | 内容 |
|---|---|
| 通勤費 | 一般的に通勤のために必要な交通機関や自動車の利用にかかる支出 |
| 職務上の旅費 | 勤務する場所を離れて職務するための出張や出向など、その旅行での交通機関や自動車の利用にかかる支出 |
| 転居費 | 転任による転居のための交通機関や自動車の利用、宿泊、家具等の運送にかかる支出 |
| 研修費 | 職務に直接必要な技術や知識を習得するための研修にかかる支出 |
| 資格取得費 | 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得のための支出であれば、取得の有無にかかわらず対象) |
| 帰宅旅費 | 単身赴任に伴う移動で交通機関や自動車の利用にかかる支出 |
| 勤務必要経費 | 勤務に必要となる図書費、衣服費、交際費等で65万円までの支出 |
給与所得控除の対象者は給与所得者

ここからは、給与所得控除の対象者について、雇用形態や収入の受取先の違いに分けて解説します。
会社員やパートなどで給与等を受け取る人
給与所得控除の対象者は、会社員やパートなどで給与等を受け取る人です。給与等は給料や賞与、役員報酬などを含む所得で、源泉徴収票で記載される支払金額のことを指します。給与として受け取っていれば、正社員や非正規雇用、パート、アルバイトなどすべての人が対象です。
副業で2社以上から給与を受け取る人
勤務先の会社以外での副業やアルバイトを含め、2か所以上で働いている場合、すべての給与の合計額に対して給与所得控除が適用されます。2か所以上から給与を受け取っている場合に給与所得控除を適用するには、原則として確定申告が必要です。
給与を受け取る会社から発行される源泉徴収票をもとに、合算した金額に対して給与所得控除を計算して申告します。年末調整をしていた場合でも確定申告が必要になる場合があるため注意が必要です。2か所以上から給与を受け取っていても、年間の合計給与が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
1年の途中で会社を辞めた人
ある年の1月~12月の途中で会社を辞めた人も、給与所得控除の対象です。具体的には、2025年8月に会社を辞めた場合、2025年分の確定申告で給与所得控除を受けられます。会社を辞めて個人事業主になったり、出産や子育てに専念したりする場合は、その年分の確定申告を行う必要があります。
給与所得控除の計算方法と申告のやり方
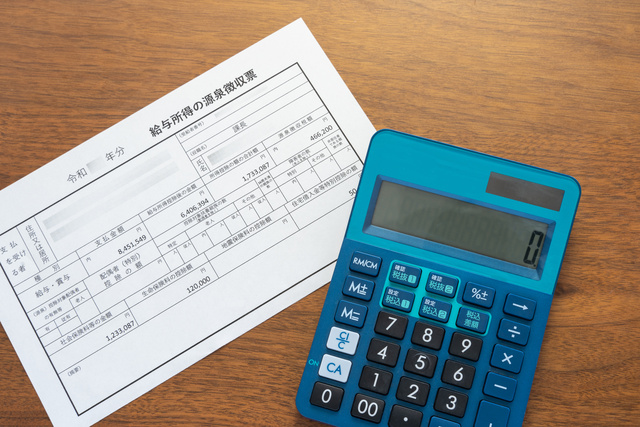
ここからは、表や計算式を用いて給与所得控除の計算方法と申告のやり方について解説します。
給与所得控除の計算方法
給与所得控除は給与等の収入金額の区分に応じて決まります。源泉徴収票の支払金額の欄に記載されている金額を表に当てはめて、給与所得控除を計算してみましょう。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%ー100,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与が400万円だった場合の給与所得控除は次のように計算されます。
給与所得控除の計算例
- 400万円×20%+44万円=124万円
ただし、給与が660万円未満では、「令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得が決まります。
令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
給与所得の税金の計算方法
給与所得に対する税金の計算方法は次の手順で計算します。所得税率は国税庁のHPに掲載されている所得金額の区分を参考にして計算します。所得控除や税額控除は自身の該当する種類と金額を当てはめて計算してみてください。
給与所得の税金の計算方法
- 給与収入ー給与所得控除=給与所得
- 給与所得ー所得控除=課税所得
- 課税所得×所得税率=所得税
- 所得税ー税額控除=納税額
年末調整で基礎控除申告書を提出する
給与所得控除は、会社から提示される書類の基礎控除申告書を提出することにより年末調整で手続きします。1年を通して給与から天引きされていた源泉徴収税と年収を再計算して、過不足を調整する手続きです。源泉徴収税で所得税を過剰に徴収されていた場合は還付されます。年末調整では扶養控除等申告書、保険料控除申告書などの書類を準備しておきましょう。
特定支出控除を受けるには確定申告が必要
特定支出控除を受けるための確定申告では必要書類を準備し、間違いや記入漏れがないように注意して申告しましょう。必要書類がすべてそろっているか確認し、申告するときまで管理しておくことが必要です。確定申告の提出期限は翌年の2月半ば~3月半ばとなっているため、事前に準備をしておきましょう。
特定支出控除の確定申告で必要な書類
- 給与所得者の特定支出に関する明細書
- 特定支出に関する証明書
- 支出の内容を確認できる領収書
- 給与所得の源泉徴収票
まとめ
給与所得控除は給与所得者が対象となる所得控除で、基本的には年末調整で手続きできます。年収に増減があったり、退職や転職で勤務状況が変わったりしたときには所得税に影響するため確認しておくことが大切です。給与所得控除の計算方法や申告のやり方について、ぜひご確認ください。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。







