住民税決定通知書は住宅ローンの手続きに必要!
記載内容や再発行の可否を解説

住宅ローンの手続きで「住民税決定通知書を提出してください」といわれ、慌てた経験はありませんか。毎年届く書類ですが、普段はあまり気にせず保管している方も多いでしょう。
本記事では住民税決定通知書とは何か、住宅ローンで提出しなければならない理由や紛失時の対処法を解説します。
住民税決定通知書とは
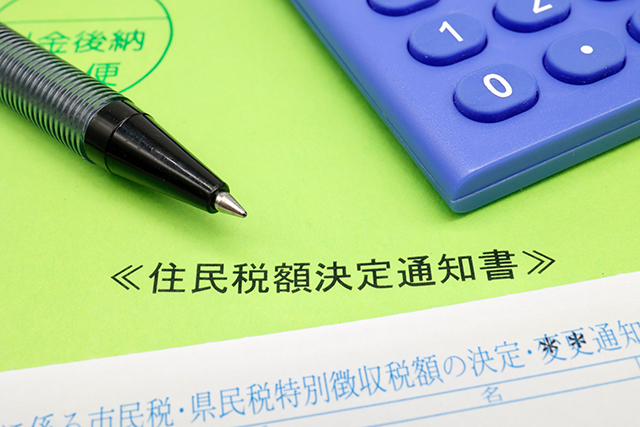
名前のとおり、住民税の税額を通知する公的な書類です。自治体が前年の所得をもとに算出・決定した税額が記されています。送り主はその年の1月1日時点に住所があった自治体です。
正式名称は以下のとおりで、納付方法によって異なります。
会社員や公務員など給与所得がある場合:市民税・県民税特別徴収税額決定通知書
個人事業主やフリーランス、その他の所得がある場合:市民税・県民税税額決定通知書
住民税とは
住民税は、市町村民税と道府県民税をあわせたものです。地方税の一種で、教育や福祉など身近な行政サービスの財源として使われています。個人向けと法人向けの住民税があり、この記事では個人の住民税について解説します。
住民税の課税対象となるのは、前年の1月から12月に一定の所得があった方です。扶養する親族がいない場合で前年の所得が45万円以下の場合は、課税の対象となる所得がありませんので非課税となります。また、生活保護法による生活扶助を受けている方なども非課税となります。
税額は、所得割と均等割の合計額で構成されており、下記のように計算されます。
所得割:前年の所得をもとに計算され、税率は一律10%で設定されている
均等割:所得に関わらず、地域社会の会費的なものとしてその住所地に住む住民が均等に負担する(市町村民税と道府県民税あわせて4,000円)
2024年度からは市町村民税と道府県民税とあわせて、森林環境税1,000円も課税されています。森林環境税は森林整備のために使われる税金です。
ちなみに2014年度から2023年度の10年間限定で、均等割の税額は引き上げられていました。東日本大震災復興基本法が制定され、防災減災事業の財源を確保しなければならなかったためです。2014~2023年度と2024年度以降の税額を比較してみましょう。
| 2014~2023年度 | 2024年度~ | |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 道府県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
| 森林環境税 | - | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 |
どちらも合計すると同じ5,000円ですが、内訳が異なります。
納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類です。給与所得がある方は特別徴収となり、毎月の給与から天引きされます。特別徴収の場合、納税手続きは会社が代行してくれるため、本人は通知書を受け取るだけです。
一方で個人事業主やフリーランスなどの方は普通徴収となり、自分で納付しなければなりません。6月~翌年5月分を一括払いする方法と、4回の納期に分けて納める方法があります。
住民税決定通知書はいつ届く
通知書が届くのは1年に1回で、時期は5~6月頃です。手元に到着するまでのプロセスを確認しましょう。
まず会社員の場合は前年12月末に1年分の給与が確定し、勤務先の会社が1月末までに自治体へ給与支払報告書を提出します。個人事業主やフリーランスの方で自分で税務署へ確定申告書を提出した場合は、税務署が地方自治体と申告内容を連携することになっています。
そして各地方自治体は給与支払報告書や確定申告の内容をもとに、税額を決定し通知書を作成・送付する流れです。
特別徴収の場合は勤務する会社を通して配布され、普通徴収の場合は直接自宅に届きます。遅くとも6月中には送付されるため、月末になっても届いていない場合は市町村に確認しましょう。
住民税決定通知書はいつ必要?

また、通知書は以下の場面などで必要になるため、大切に保管しておきましょう。
- 住宅ローンを申し込むとき
- ふるさと納税の控除額を確認するとき
住宅ローンを申し込むとき
住宅ローンを申し込むときの提出書類に、住民税決定通知書が含まれている場合があります。通知書を見ることで前年の所得がわかるため、金融機関が申込者の返済能力を審査する際の判断材料として所得金額を証明する書類の提出を求めます。
そのため、収入合算やペアローンの場合は、夫婦それぞれが通知書を用意しなければなりません。
ただ、住民税決定通知書は必須ではありません。要は年収を確認できればよいため、基本的には源泉徴収票や所得税確定申告書などの公的な書類でも代用可能です。
提出書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
ふるさと納税の控除額を確認するとき
ふるさと納税を利用した方は、通知書を見れば寄附金が正しく控除されているか確認することができます。ただしワンストップ特例と確定申告、どちらの方法で申請したかによって確認の仕方が異なる点に注意しなければなりません。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、確認の仕方はシンプルです。寄附金額から2,000円マイナスした金額が、通知書の税額控除欄と摘要欄に記されます。
一方、確定申告の場合は、住民税だけでなく所得税からも寄附金が控除される仕組みです。そのため、控除内容をチェックするには、通知書と確定申告書の両方を見て確認する必要があります。
住民税決定通知書の記載内容

どこに何が書かれているか把握できれば、住宅ローン控除やふるさと納税の寄附金控除など必要な場面に応じて、どこを見るべきかがわかります。住民税決定通知書の構成は、以下の6つの欄です。
- 所得金額
- 所得控除額
- 課税標準額
- 合計年税額(所得割額・均等割額)
- 納付税額
それぞれの欄に記載されている内容を詳しく解説します。
所得金額欄の見方
給与所得等に係る特別徴収の場合の通知書の所得金額欄に記載されている項目は、おもに以下のとおりです。
- 給与収入
- 給与所得
- その他の所得計
- 主たる給与以外の合算所得区分
- 総所得金額①
「給与収入」は年収に該当する金額です。「給与所得」は給与収入から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得以外に所得がある場合は、「その他の所得計」に金額が記載されています。その場合は「主たる給与以外の合算所得区分」を見ると、該当項目に印が付いています。
「総所得金額①」には給与所得とその他の所得計を合算した金額が載っています。
個人事業主やフリーランスの方に届く市民税・県民税税額決定通知書は、所得欄に記載されている項目が異なる場合があります。
- 事業所得(または営業等所得)
- 不動産所得
- その他雑所得
- 山林所得
- 分離短期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得
- 株式等の譲渡
- 上場株式等の配当等
- 先物取引
給与所得、事業所得、不動産所得、その他雑所得は「総所得金額合計」などとして合計して記載されることもあります。
所得控除欄の見方
所得控除欄には、所得から控除される以下の項目とそれぞれの控除金額が書かれています。
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 雑損控除
- 障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除など
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 所得控除合計②
所得控除とは、所得金額から差し引くことで税金を軽減できる仕組みとなっており、納税者個人の事情に対する考慮や最低生活費の保障、その他社会政策上の要請によるものなど、納税者の税負担の調整を行うために設けられています。
たとえば、健康保険や厚生年金の保険料を支払っている場合は「社会保険料控除」、控除対象となる配偶者がいるときは「配偶者控除」に金額の記載があり、それぞれ控除されます。
各控除金額は、源泉徴収票や確定申告の内容と一致します。各控除金額を合計した金額が「所得控除合計②」になります。
ちなみに給与所得控除は、所得控除と名前が似ていますが、全く別物です。給与所得控除は会社員などの給与所得者が、1年間の給与収入に応じて一定額を概算の必要経費として控除される制度です。
課税標準額欄の見方
課税標準額欄に記載されるのは、おもに以下のような項目です。
- 課税総所得金額③
- 山林所得
- 分離短期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得
- 株式等の譲渡
- 上場株式等の配当
- 先物取引
課税標準額とは税金の計算の基礎となるもので、課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。所得の種類に応じて税率が異なるため、所得の種類に応じてそれぞれ計算します。
「課税総所得金額③」は所得欄「総所得金額①」から所得控除欄「所得控除合計②」をマイナスした金額です。
摘要欄の見方
税額から直接控除されるなど個別的な理由がある場合は、摘要欄にその詳細が記されます。ふるさと納税による寄附金控除や住宅ローン控除を受けている方などは、摘要欄をしっかり確認しておきましょう。
たとえば、ふるさと納税の寄附金控除は、以下のように書かれています。
寄附金控除:市民税〇〇円 県民税〇〇円
ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税の寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、市民税と県民税の合計額と一致しています。
住宅ローン控除を受けている場合に、一部の方は通知書に記載があることがあります。住宅ローン控除は基本的に所得税から差し引かれ、所得税から引ききれない場合のみ住民税で調整される仕組みです。そのため、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除額がある人は摘要欄にその差額が記されているため、確認しておきましょう。
税額欄の見方
税額欄には以下の項目が並んでいます。
- 市民税・税額控除前所得割額④
- 市民税・税額控除額⑤
- 市民税・所得割額⑥
- 市民税・均等割額⑦
- 県民税・税額控除前所得割額④
- 県民税・税額控除額⑤
- 県民税・所得割額⑥
- 県民税・均等割額⑦
- 森林環境税額⑧
- 特別徴収税額⑨
- 控除不足額⑩
- 既充当・既委託納付額⑪
- 既納付額⑫
- 差引納付額(⑨-⑫-⑩,⑪)
- 変更前税額⑬
- 増減額(⑨-⑬)
- 変更月
税額控除前所得割額④は、課税所得(課税標準の合計額)に税率をかけたものです。税率は市町村民税が6%、道府県民税が4%になります。
税額控除額⑤は市町村民税と道府県民税をあわせた金額が、摘要欄の税額控除額の合計と一致します。税額の計算は、税額控除前所得割額④-税額控除額⑤=所得割額⑥となります。
均等割額⑦は、所得に関わらず一律の金額が記載されています。内訳は市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円の合計4,000円です。
森林環境税額⑧は2024年度から課税されている国税で、税額は一律1,000円となっています。
控除不足額⑩、既充当・既委託納付額⑪、既納付額⑫がすべて0円になっている場合は、特別徴収税額⑨が1年間の税額です。
減免申請などを行い税額が変わった場合は、変更前税額⑬に以前の税額が書かれています。増減額(⑨-⑬)と変更月を確認することで、いつ・いくら変わったのかがわかります。
納付額欄の見方
納付額欄に書かれているのは、6月から翌年5月まで月々の納付額です。ここに書かれている金額に基づき、毎月の給与から天引きされます。
特別徴収の場合は基本的には1年分を12で割って出していますが、端数が出る場合は6月分で調整されます。そのため6月分だけ納付額が違う場合があります。
住民税決定通知書が手元にない

手元にない場合は、最初から届いていないか、あるいは紛失した可能性が高いです。
それぞれの場合の対処法について詳しく解説します。
住民税決定通知書が届かない場合
手元に届いていない場合は、以下のような理由が考えられます。
- 引っ越したのに住所変更をしていない
- 勤務先の手続きに不備があった
- 確定申告をしていない
- 所得が一定以下などの理由で課税対象になっていない
まずは引っ越したのに住所変更をしていないケースです。書類の送付先は会社員の場合は勤務先、個人事業主やフリーランスの場合は自宅へ送付されます。公的書類は住民票をもとに送付されるのが基本です。
そのため自治体に転居届を出していない場合は、前の住所に届いてしまっている可能性があります。あるいは宛先不明として自治体に返送されているケースも考えられます。
二つ目は、勤務先の手続きに不備があったケースです。給与支払報告書の提出が遅れているなど、手続き上の不備が原因で、通知書が発行できていない場合があります。
続いてはフリーランスの方が、確定申告を忘れているケースです。住民税は確定申告の内容を税務署と連携することにより算出されます。一定の所得があるのに申告できていない方は、すみやかに申告を済ませてください。
最後は、そもそも課税対象になっていないケースです。収入が一定以下の方、生活保護を受けている方などは非課税となるため、書類自体が送られてきません。
上記のいずれの理由にも該当しない場合は、勤務先等へ直接確認したほうがいいかもしれません。特別徴収の場合は勤務先に、普通徴収の場合はお住まいの自治体の担当窓口に直接問い合わせましょう。
相手方が確かに渡したということであれば、受け取ったあとに紛失している可能性が高いです。紛失した場合は、次の項目を参考にしてください。
住民税決定通知書を紛失した場合は再発行できない
紛失してしまった場合は、再発行できるのかが気になるポイントですよね。しかし残念ながら、原則として通知書が再発行されることはありません。
住民税決定通知書は、納税義務が発生したことを通知する重要な証明書類です。一度しか発行されないため、手元に届いたら大切に保管しましょう。
しかし紛失してしまった場合も、慌てる必要はありません。住宅ローンの手続きやふるさと納税の控除額の確認は、他の書類でも代用することができます。どのような書類であれば問題ないのか、次の項目で見ていきましょう。
住民税決定通知書以外で課税内容を確認する方法

もし通知書を紛失してしまっても、他の方法で内容を把握することができます。
- 住民税課税証明書を取得する
- マイナポータルで確認する
住宅ローンの手続きなど、所得や課税内容を公式に証明する場合は、住民税課税証明書でも問題ないケースが多いです。自分で確認するだけの用途であれば、マイナポータルを閲覧することもできます。
住民税課税証明書を取得する
住民税課税証明書は、1年分の所得や控除の状況を証明する公的な書類です。
住民税決定通知書に記載されている項目はすべて網羅されています。そのため、住宅ローンの手続きやふるさと納税の寄附金控除のチェックなど、幅広い用途で活用できるでしょう。
取得方法は、窓口交付・郵送・コンビニエンスストアの交付サービスの3種類です。いずれの場合も手数料がかかります。自治体によって異なりますが、1通200円から300円程度かかる場合が多いです。本人、同居親族が取得でき、代理人に委任状を預けて取得してもらうこともできます。
窓口交付の場合は、自治体の窓口に行って交付請求書と手数料を支払います。郵送の場合は交付請求書を印刷・記入し返信用封筒を添えて送付すれば、後日送られてくる流れです。コンビニエンスストアの交付サービスは、マイナンバーカードを持っている方のみ利用できます。
マイナポータルで確認する
マイナポータルでも住民税の課税内容を確認できます。マイナポータルとは、マイナンバーカードを使って行政手続きをオンラインで行えるサービスです。
利用するためには、マイナンバーカードとスマートフォンが必要です。
マイナポータルにログインし、トップページから「わたしの情報」をクリックすると、所得税と個人住民税の情報がわかります。所得額や住民税額、そもそも課税対象か否かということも確認することができます。
手数料がかからず気軽に閲覧できるため、自分で見直す際は最適な方法です。
まとめ

住民税決定通知書は、前年の所得に基づいて算出された住民税額を知らせるための書類です。税額に加えて、前年の所得などの重要な情報が記載されています。
住宅ローンの手続きでは、金融機関が申込者の返済能力を審査する目的で、提出を求めることがあります。もし紛失してしまった場合は再発行できませんが、住民税課税証明書でも問題ないケースが多いので覚えておくとよいでしょう。
とはいえ、直前に必要書類が見つからないと、誰でも慌ててしまいます。あらかじめ金融機関に聞いて、余裕を持って必要書類を揃えておくと安心です。

認定経営革新等支援機関、M&A支援機関。青山学院大学大学院法学研究科修了。オーナー企業の相続・事業承継や資産形成、その他、遺言・民事信託等を活用した相続対策の企画立案など、おもに法人・相続領域の税務・コンサルタント業務に約20年従事。その他資金調達ならびに創業融資の支援を得意とする。







