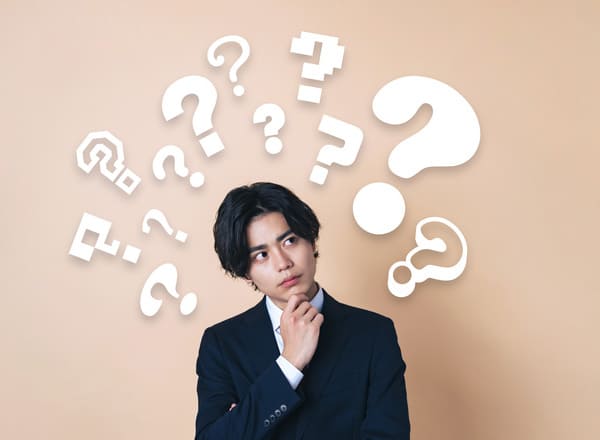年末調整の書き方!
必要書類や注意点、確定申告が必要なケースも紹介
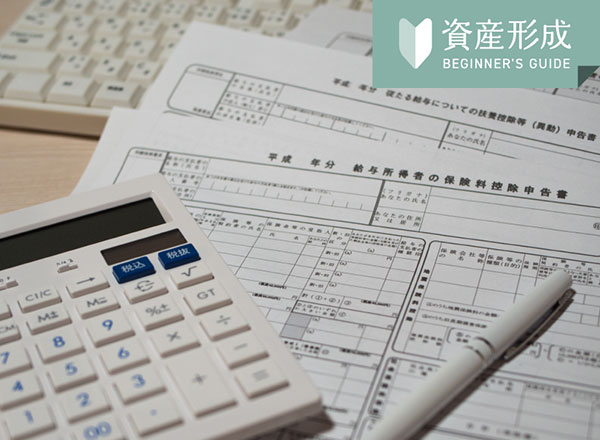
会社員やアルバイトとして働いていると、毎年12月ごろに年末調整の書類提出を求められます。年末調整は、1年間に納めた所得税を正しく精算するための重要な手続きです。本記事では、年末調整の基本的な仕組みから必要な書類、書き方を紹介します。あわせて確定申告との違いについても解説するため、自身に必要な手続きを確認してみてください。
年末調整は何をする手続き?

年末調整とは、会社が従業員に代わって1年間の所得税額を正しく計算し、すでに給与から天引きされている税額との差額を精算する手続きです。毎月の給与から差し引かれている所得税は概算額であるため、年末に各種控除を反映させて最終的な税額を確定させる必要があります。
その結果、税金を払い過ぎている場合は還付され、不足している場合は追加で徴収されます。
年末調整の目的と仕組み
年末調整の目的は、給与所得者の所得税額を正確な金額に調整することです。
給与支給時に天引きされる所得税は、扶養状況や各種保険料などが十分に反映されていない場合があります。そこで年末に、扶養控除や生命保険料控除、基礎控除などを申告し、それらを反映した年間の所得税額を確定させます。
年末調整の対象となる所得者
年末調整の対象となるのは、原則として会社に雇用され、給与の支払いを受けている人です。正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は、年末調整の対象となります。
一方で、副業による所得がある人や、2か所以上から給与を受け取っている人などは、年末調整だけでは手続きが完結せず、確定申告が必要となるケースもあります。
年末調整で提出が必要な書類
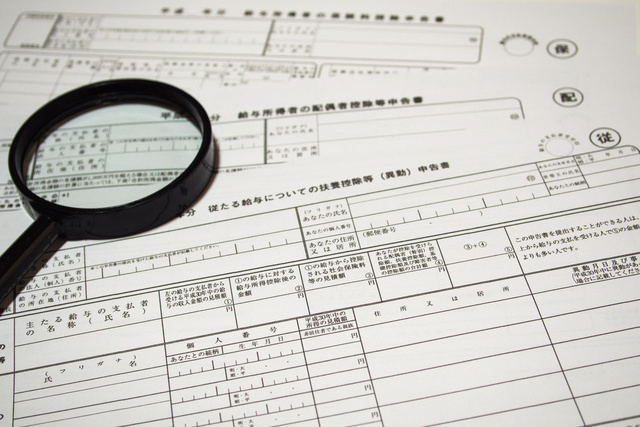
年末調整を正しく行うためには、会社から配布される各種書類に記入し、必要に応じて証明書を提出することが必要です。これらの書類をもとに、各種控除の適用や最終的な税額が判断されます。記入漏れや提出忘れがあると、本来受けられるはずの控除が適用されず、税金を多く支払ってしまう可能性があるため注意しましょう。
会社から配布される主な書類
年末調整の時期になると、会社から複数の申告書が配布されます。代表的な書類として、「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」があります。これらの書類には、扶養家族の情報や自身の収入見込み、加入している保険の内容などを記入します。
記載内容は所得税額の計算に直接反映されるため、記入漏れや誤りがないよう、正確に記入することが大切です。
年末調整に添付・提出する証明書
申告書に記載した内容を証明するため、各種控除証明書の提出が求められる場合があります。生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書、社会保険料控除に関する証明書などは、あらかじめ用意しておきましょう。
これらの証明書を提出できない場合、原則として当該控除は適用されないため注意が必要です。
年末調整の書き方と記入のポイント

年末調整では、複数の申告書に必要事項を記入しますが、記載内容そのものはそれほど難しくありません。重要なのは、どの書類に何を記入するのかを正しく理解し、記入ミスや漏れを防ぐことです。
ここでは、各申告書の基本的な書き方に加え、控除欄を記入する際の注意点や、税金が計算される流れについて解説します。
各申告書の基本的な書き方
年末調整で記入する主な申告書は、以下の3種類です。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書
- 保険料控除申告書
いずれの申告書にも、氏名や住所、マイナンバー、扶養家族に関する情報などを記入します。扶養控除等(異動)申告書では、その年の最初に提出した内容から変更がないかを確認し、異動があった場合は正しく反映させることが重要です。
また、配偶者や扶養親族の収入見込み額については、年間収入を基準に記入しましょう。
控除欄を記入する際の注意点
控除欄には、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などを記入します。ここで注意したいのは、各種控除証明書に記載されている金額をそのまま転記することです。自己判断で計算した金額を記入すると、控除額を誤ってしまう可能性があります。
また、控除の対象となるかどうかは、保険の種類や契約内容によって異なります。不明点がある場合は、証明書の記載内容や会社からの案内を確認したうえで記入するようにしましょう。
源泉徴収や税金計算の流れ
毎月の給与から天引きされている所得税は源泉徴収と呼ばれ、あくまで概算の金額です。年末調整では、年間の給与総額から給与所得控除を差し引き、さらに各種控除を反映させて課税所得を算出します。その課税所得に所得税率を適用し、1年間の所得税額を確定させます。
その結果、すでに源泉徴収された税額との差額が、還付または追加徴収として調整されます。
年末調整でよくある注意点
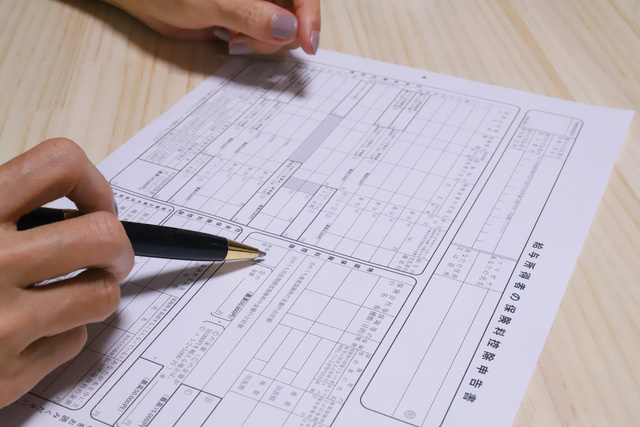
年末調整は会社が手続きを行いますが、申告内容に誤りや漏れがあると、正しい税額が計算されません。ここでは、特に間違いやすい項目や、見落としがちなポイントを解説します。
提出漏れ・記入漏れを確認する
年末調整でとくに多いトラブルの一つが、申告書や証明書の提出漏れ、記入漏れです。たとえば、保険料控除証明書を添付し忘れると、本来受けられるはずの控除が適用されません。
提出前には、すべての申告書に記入欄の空白がないか、押印や署名が必要な箇所に漏れがないかを必ず確認しましょう。
勤務状況や所得の変化がある場合
年の途中で転職した場合や複数の会社から給与を受け取っている場合は、特に注意が必要です。前職の源泉徴収票を提出しないと、年末調整で正しい所得計算ができません。また、副業による収入や不動産収入がある場合は、年末調整では対応できず、確定申告が必要となるケースがあります。
自身の勤務状況や所得の変化を把握したうえで、年末調整だけで手続きが完結するかどうかを確認しましょう。
年末調整と確定申告の違い
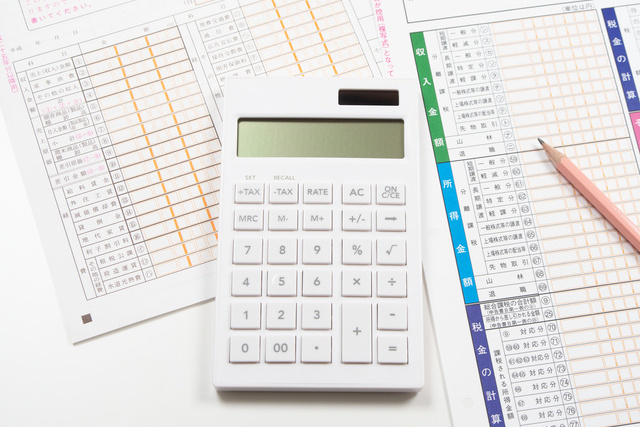
年末調整と確定申告はいずれも、所得税を正しく計算・精算するための手続きですが、対象者や手続きを行う主体が異なります。年末調整は会社が従業員に代わって行う手続きであるのに対し、確定申告は個人が自ら税務署へ申告する手続きです。
自身がどちらの手続きに該当するのかを理解したうえで、必要な対応を行いましょう。
確定申告が必要になるケース
給与所得者であっても、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要になります。たとえば、2か所以上から給与を受け取っている場合や、副業による所得が一定額を超える場合です。また、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない場合)を受けたい場合も、確定申告を行う必要があります。
さらに、年の途中で退職し、年末調整を受けていない人は、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。
年末調整だけで完結するケース
一方、1社からのみ給与を受け取っており、扶養状況や保険料などを年末調整で正しく申告している場合は、原則として確定申告を行う必要はありません。生命保険料控除や配偶者控除など、年末調整で対応できる控除のみであれば、会社での手続きだけで所得税の精算が完結します。
まとめ
年末調整は、会社員やパート・アルバイトが1年間の所得税を正しく精算するための手続きです。必要な書類をそろえ、各申告書を正確に記入することで、税金の払い過ぎや控除漏れを防ぐことができます。
一方で、年末調整では対応できない所得や控除がある場合は、確定申告が必要になることがあります。自身の働き方や収入状況を把握し、年末調整と確定申告を正しく使い分けることが、税金の払い過ぎや未納を防ぐために重要といえるでしょう。

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。