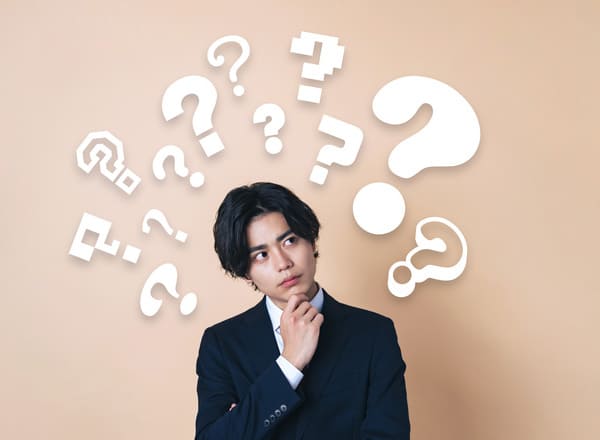退職金にかかる税金はどれくらい?
仕組みや払い方、計算方法を紹介

退職金は所得の1つになるため、税金が課税されます。税額を差し引かれた金額が実際にもらえる退職金となるため、税金の仕組みや計算方法を理解しておくことが大切です。この記事では、退職金にかかる税金の仕組みや計算方法について、事例を紹介しながら解説します。
退職金にかかる税金の仕組みと計算方法

退職金に課税されるのは所得税と住民税です。まずは所得税と住民税について、仕組みと計算方法を解説します。
所得税
1年間の収入を給与所得や事業所得、雑所得といった10種類の所得に分類して、それぞれで所得税を計算します。所得税の課税方法は、合算して計算する総合課税、他の種類の所得と別で計算する分離課税の2つです。
仕組み
退職金は10種類ある所得のなかの退職所得に該当しますが、分離課税となるため他の所得とは別で計算します。勤務先から受け取る退職手当などの所得や、社会保険制度などにより退職時に支払われる一時金が退職所得です。
また、生命保険や信託会社から支払われる一時金も退職所得に含まれます。退職所得の金額や勤続年数によって所得税と復興特別所得税(2037年まで)が計算され、これらの合計額が納税する税金です。
計算方法
所得税の計算をする前に課税退職所得金額を算出します。課税対象の退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が、課税退職所得金額です。
課税退職所得金額の計算方法
● 課税退職所得金額=(退職金の総額ー退職所得控除額)÷2
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
ただし、勤続年数の1年未満の端数は、繰り上げて年単位で計算します。
課税退職所得金額に所得税率をかけて、税額控除を差し引いた金額が所得税額です。復興特別所得税は所得税額の2.1%となります。
退職金の所得税額と復興特別所得税の計算方法
● 退職金の所得税額=課税退職所得金額×所得税率-控除額
● 復興特別所得税=退職金の所得税額×2.1%
● 退職金の所得税の総額=退職金の所得税額+復興特別所得税
所得税率と控除額は所得金額によって次の表の該当する数値となります。

出典:国税庁「退職金と税」
住民税
住民税は地方税の1つで、都道府県と市区町村に納める税金です。ここからは、住民税の仕組みと計算方法について解説します。
仕組み
住民税は納税者全員が均等に負担する均等割と、前年の総所得金額に対して計算される所得割の2種類です。退職金に課税される住民税は分離課税となるため、給与所得など他の所得とは切り離して計算します。退職金の住民税の計算と納税は勤務先の企業が手続きをするため、自分で税金を支払う必要はありません。
計算方法
住民税は課税退職所得金額に税率をかけて算出します。課税退職所得金額は退職金の総額から退職所得控除額を差し引く計算で、所得税と同じです。住民税の所得割の税率は都道府県民税の4%と市区町村民税の6%を足した、10%になります。
住民税の計算方法
● 課税退職所得金額=(退職金の総額ー退職所得控除額)÷2
● 住民税=課税退職所得金額×税率10%
退職金の金額と税金の計算事例

ここからは、勤続年数と退職金額の事例をもとに、税金の計算をシミュレーションして解説します。
ケース①勤続15年・退職金1,000万円
勤続15年・退職金1,000万円の所得税は10万4,652円です。住民税は20万円となるため、所得税と合計して退職金にかかる税金は総額34万4,652円となります。
所得税の計算
● 退職所得控除額=40万円×15年=600万円
● 課税退職所得金額=(1,000万円ー600万円)÷2=200万円
● 退職金の所得税=200万円×税率10%ー控除額9万7,500円=10万2,500円
● 復興特別所得税=10万2,500円×2.1%=2,152円(1円未満の端数は切り捨て)
● 退職金の所得税の総額=10万2,500円+2,152円=10万4,652円
住民税の計算
● 課税退職所得金額=200万円(所得税と同じ)
● 住民税=200万円×税率10%=20万円
ケース②勤続30年・退職金2,000万円
勤続30年・退職金2,000万円の所得税は、15万5,702円です。住民税は25万円となるため、所得税と合計して退職金にかかる税金は総額40万5,702円となります。
所得税の計算
● 退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20年)=1,500万円
● 課税退職所得金額=(2,000万円ー1,500万円)÷2=250万円
● 退職金の所得税=250万円×税率10%ー控除額9万7,500円=15万2,500円
● 復興特別所得税=15万2,500円×2.1%=3,202円(1円未満の端数は切り捨て)
● 退職金の所得税の総額=15万2,500円+3,202円=15万5,702円
住民税の計算
● 課税退職所得金額=250万円(所得税と同じ)
● 住民税=250万円×税率10%=25万円
退職金の受給方法と税金の払い方

退職金の受給方法は一時金と年金の2つで、それぞれ税金の払い方が異なります。受給方法はどちらか一方だけでなく組み合わせることも可能なため、よく理解してから利用しましょう。
一時金のみで受給する
退職金を一時金として一括で受け取る方法です。一時金の場合、退職所得として分離課税で所得税を計算します。
退職所得は退職所得控除が適用されるため、勤続年数が長いほど税制優遇される制度です。一時金で受給すると、退職金に対する税金を抑えて収入を最大化できます。
年金のみで受給する
退職金を分割して、年金として受け取る方法です。年金の場合、雑所得として総合課税で所得税を計算します。雑所得は老後にもらう公的年金の収入と合算して計算するため、他の所得がある場合は雑所得の合計額での計算が必要です。公的年金の受給額や他の収入によって、一時金より年金で受け取る所得税が高くなるため注意しましょう。
一時金と年金を組み合わせる
一時金と年金を組み合わせて受給すると、それぞれのメリットを活用できます。一時金では退職所得として、年金では雑所得として、それぞれの税金の払い方を組み合わせる方法です。
退職所得控除額を下回る金額を一時金として、残りを年金で受け取ると、所得税の節税になります。退職金でもらえる金額の相場だけでなく、税金で支払う額を抑えて手元に残る分が多くなるよう受け取り方法を計算してみましょう。
まとめ
退職金にかかる税金は所得税と住民税の2種類あり、控除や税率の計算が複雑になります。それぞれの仕組みや計算方法を理解したうえで試算することが大切です。退職金にかかる税金を試算して、手元に残る金額や受給方法を検討するための参考にしてみてください。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。