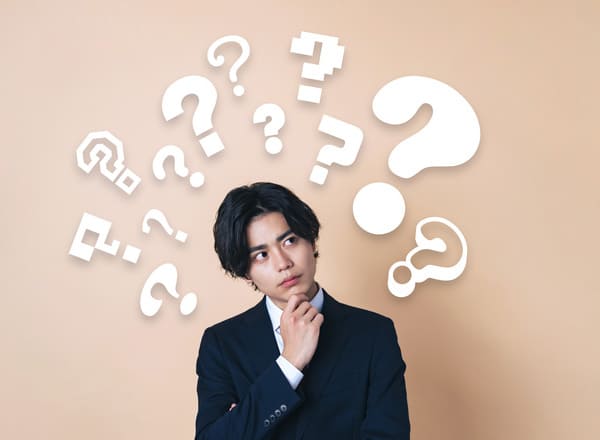遺産相続で税金はいくらから発生する?
判断する方法と必要な対応を紹介

自分や家族が定年退職をすると、相続について気になり始める頃ではないでしょうか。実際に遺産相続が発生した場合、いくらから税金がかかるのか関心を抱く人もいるでしょう。この記事で、相続税が発生する基準や必要な対応などについて解説します。
遺産相続でいくらから税金が発生する?

まずは、遺産相続で税金が発生する基準について解説します。
遺産総額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で判断
遺産相続では、相続財産に対して課税されます。ただし、相続税がかかるのは、基礎控除額を超えた場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続税による課税件数の割合
相続税による課税割合は、以下のとおりです。
課税割合の推移
| 年分 | 課税割合 |
| 2021年 | 9.3% |
| 2020年 | 8.8% |
| 2019年 | 8.3% |
| 2018年 | 8.5% |
| 2017年 | 8.3% |
出典:国税庁「令和3年分相続税の申告事績の概要」
基礎控除を適用できることもあり、相続税の課税割合は10%未満となっています。
具体的に税金はいくらから発生するのか
基礎控除額は、相続税が発生する判断基準となる重要なポイントです。基礎控除額の計算式に具体的な数値をあてはめ、実際にいくらから税金が発生するのか、確認していきましょう。
法定相続人3人なら4,800万円超が基準
基礎控除額は、法定相続人の数をあてはめると求められます。法定相続人の数が3人であれば基礎控除額は4,800万円となり、4,800万円を超えると相続税が発生します。
法定相続人の数が5人までの基礎控除額は以下のとおりです。
法定相続人の数と基礎控除額
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
法定相続人の数が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円加算されます。実際に法定相続人の数をあてはめて計算してみるとよいでしょう。
法定相続人の範囲と法定相続分
法定相続人とは、法律で定められている相続人を指します。お世話になった隣人や友人も相続人になれますが、法定相続人にはなれません。法定相続人と法定相続分(法律で定められた分割割合)は次の表のとおりです。
法定相続人と法定相続分
| 相続順序 | 法定相続人と相続分 | 配偶者の相続分 |
| 第一順位 | 子:1/2 | 1/2 |
| 第二順位 | 父母:1/3 | 2/3 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹:1/4 | 3/4 |
出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人は順位の高いものから適用され、親族との関係性で分割割合が決まっています。配偶者と子が法定相続人であれば、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。子がいなければ父母、父母がいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続財産に含まれるもの
相続財産とは、相続で相続人が引き継ぐ「亡くなった人(被相続人)の財産」のことで、プラス財産だけでなく、マイナス財産も含まれます。基本的に、被相続人が所有していた全ての権利義務が相続財産の範囲です。具体的には、現金や預貯金、不動産、車、家財道具、有価証券、借金などが該当します。
一方、相続財産に含まれないものとして、年金の受給権や祭祀(さいし)財産(墓地・墓石・仏壇など)などがあります。
また、生命保険の死亡保険金については、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、相続税の課税対象外となります。
基礎控除額を超えても税金が発生しないケース
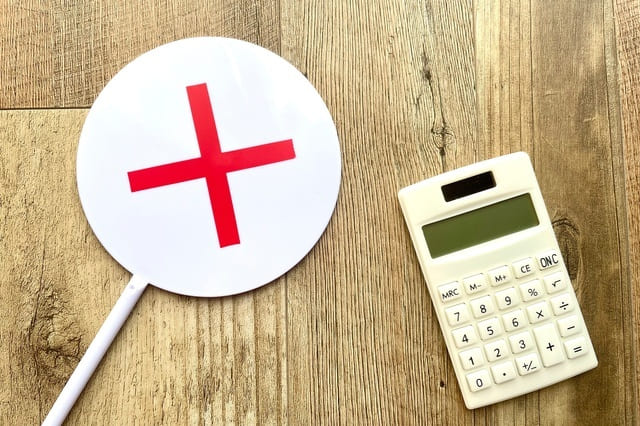
基礎控除額を超えると、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税にはさまざまな控除制度や特例があり、上手に活用することで節税を図れます。ここからは、よく活用される控除や特例について解説します。
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い方までは相続税がかからない制度です。
少なくとも、配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。また、1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分までは非課税となります。
たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。仮に遺産総額が1兆円、配偶者が法定相続分の5,000億円の遺産を相続しても、配偶者に税金は発生しません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地について、評価額を減額できる制度です。宅地は居住用・事業用・貸付事業用に分かれ、要件を満たすと評価額の減額により節税効果を得られます。
小規模宅地等の特例
| 宅地の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等 | 330m2 | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400m2 | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200m2 | 50% |
出典:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
たとえば、特定居住用宅地等に該当する2,000万円(面積200m2)の土地を相続する場合、相続税評価額は400万円(2,000万円ー2,000万円×80%)になります。
なお、配偶者控除と小規模宅地等といった特例を適用する際は、相続税がゼロになる場合でも相続税の申告が必要です。
そのほかの相続税に関する控除・特例
配偶者控除や小規模宅地等以外にも、次のような制度が税額に影響します。
相続税に関する控除・特例
| 未成年者控除 | 18歳未満の法定相続人がいる場合に受けられる控除 |
| 障害者控除 | 障害者の法定相続人がいる場合に受けられる控除 |
| 相次相続控除 | 10年間に2回以上の相続で相続税を課せられている場合に、負担を軽減するための控除 |
| 暦年課税の贈与税額控除 | 一定の暦年課税の贈与財産は相続財産に含まれる。その際に納付した贈与税額を相続税額から控除される制度 |
| 相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度で納付した贈与税額は相続税額から控除される制度 |
相続税が発生しそうな場合の対応策

相続税が課税されない金額であっても、相続に向けての準備が必要です。ここからは、相続税が発生しそうな場合の対応策に関して紹介します。
相続財産の洗い出しと評価
まずは相続財産の洗い出しと評価を行い、財産目録を作成しましょう。遺産総額が1億円でも預貯金のみと自宅のみの場合とでは、相続税の発生する可能性が異なります。
預貯金1億円の評価額は1億円ですが、不動産1億円の評価額は1億円ではありません。資産の種類によって評価方法が決まっており、不動産の場合は取引価格を基準とする公示価格の80%程度になるのが一般的です。
税金が発生するかどうかは資産の種類と評価額によって異なるため、財産目録を作成することから始めるとよいでしょう。
金融機関や専門家への相談
相続は相続税が発生するかどうかだけでなく、被相続人が亡くなってからさまざまな手続きが必要となります。相続税が発生するしないに関わらずセミナーや相談会に参加したり、相続に強い金融機関や専門家に相談したりしておくと安心です。
自分で基礎控除の金額や財産の合計を算出したとしても、状況に合わせた相続対策が必要になります。スムーズに相続を進めるためにも、早めに情報を収集しましょう。
相続税の納付期限は10ヶ月以内
相続税の申告と納付の期限は、相続が開始されたことを知った日から10ヶ月以内となっています。亡くなってから葬儀の準備・実施、所得税の準確定申告などすべきことが多いため、決して十分な期間があるとはいえません。
よって、相続税について知識を身につけてから手続きを行う時間の余裕はない可能性が高いでしょう。心配な場合は専門家に相談し、相続を進めるのがおすすめです。
まとめ
遺産相続の税金は、基礎控除額を超えた場合にかかることがほとんどです。一方、基礎控除額を超えても税金がかからないこともあるため、控除制度や特例をしっかり確認しておきましょう。不安な場合は、相続に詳しい税理士や遺産整理業務に力を入れる金融機関への相談を検討してみてください。

2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。