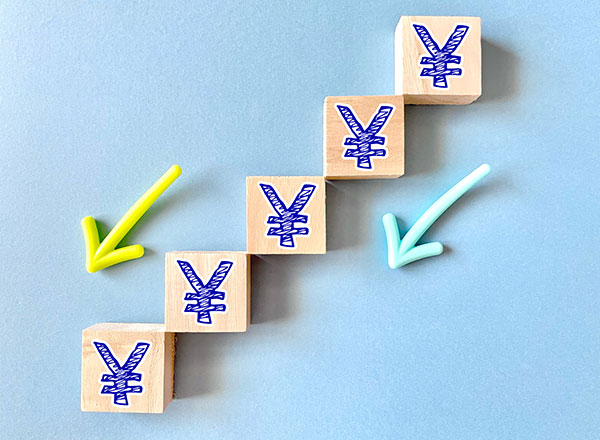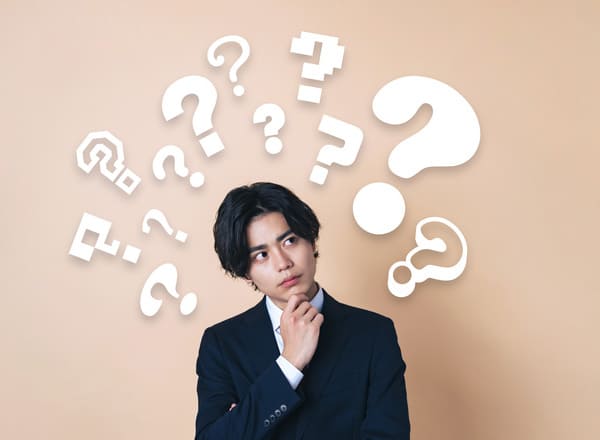預金の利息の計算方法を知ろう!
種類別にシミュレーションしながら解説

普通預金や定期預金は、誰でも一度は利用したことがあるのではないでしょうか。普通預金であれば、日常的に使っていることでしょう。しかし、利息の計算方法については知らないかもしれません。そこでこの記事では、預金の利息の計算方法について、利息の仕組みとともに、詳しく解説していきます。
利息とは?単利と複利の違い

利息の計算方法を理解するために、利息の基本的な特徴と計算式、単利と複利の違いについて解説します。金融商品を選択する際にも役立ちますので、確認しておきましょう。
利息とは?
預金の利息は、お金を預けることで得られる対価です。預けたお金を元本といい、元本に対して一定の割合(金利)で計算された金額が支払われます。
金利は、一般的に年利(年率)、税引き前で表示されます。たとえば、年利が0.1%の場合は元本に対して年間0.1%分の利息を受け取れ、その際に税金が差し引かれます。基本的には、次の計算式で利息を求めます。
| 利息 = 元本 × 金利 × 期間 |
実際には単利と複利、変動金利と固定金利など、金利の種類によって利息の計算方法は異なります。また、普通預金と定期預金のように、商品の種類によっても特徴に違いが見られます。
単利と複利の違い
利息を計算する際には、単利と複利の違いを理解しておくことが重要です。単利は常に元本に対して利息が計算されるのに対して、複利は元本にその都度、利息を上乗せして合計し、「元本+利息」に対して利率をかけます。100万円を年利2%で3年間預けた場合を考えてみましょう。
単利の計算方法
- 1年目:1,000,000円 × 2% × 1年 = 20,000円
- 2年目:1,000,000円 × 2% × 1年 = 20,000円
- 3年目:1,000,000円 × 2% × 1年 = 20,000円
- 3年後の総額:1,060,000円(税引前)
複利の計算方法
- 1年目:1,000,000円 × 2% × 1年 = 20,000円
- 2年目:1,020,000円 × 2% × 1年 = 20,400円
- 3年目:1,040,400円 × 2% × 1年 = 20,808円
- 3年後の総額:1,061,208円(税引前)
単利の場合、毎年元本に対する利息が支払われます。複利の場合は、翌年に利息分を含めて計算するため、利息が利息を生むことになります。元本が小さくても、長期間の運用となると、複利効果は大きくなっていくのです。
利息にかかる税金
預金の利息は、源泉分離課税として利息を受け取る際に自動的に税金が差し引かれ、納税が完了する仕組みです。預金利息に対する税率は20.315%で、その内訳は所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%となっています。
たとえば、5,000,000円を年利0.5%で1年間預けた場合は、以下のようになります。
利息にかかる税金
- 税引き前利息:5,000,000円 × 0.5% = 25,000円
- 税金:25,000円 × 20.315% ≒ 5,078円
- 税引後受取額:25,000円 - 5,078円 = 19,922円
預金利息を考える際には、税引き後の金額で検討することが重要です。
利息の計算方法とシミュレーション
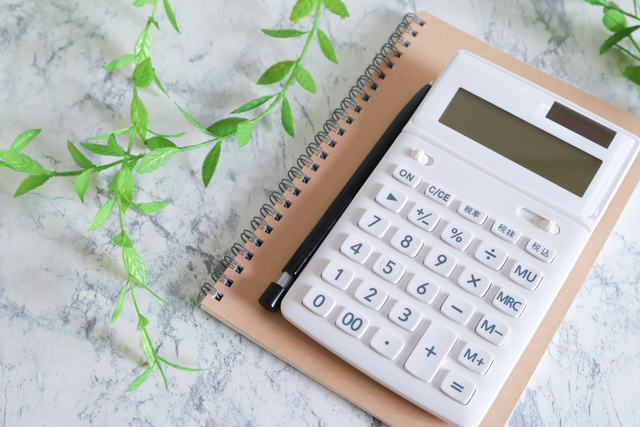
ここでは、金融商品ごとに利息を算出します。普通預金(単利)、定期預金(複利)、外貨建て定期預金(複利)の違いを見ていきましょう。なお、わかりやすくするために、税金を考慮せず、すべて税引前の金額で確認しています。
普通預金(単利)
普通預金の場合、いつでも引き出せることもあり、一般的には単利となります。毎日の残高に対して利息が計算され、半年ごとに支払われます。100万円を年利0.01%で1年間預けた場合のシミュレーションは、以下のとおりです。
普通預金(単利)のシミュレーション
- 前半6ヶ月の利息:1,000,000円 ×0.01% ÷ 182/365日 ≒ 49.86円
- 後半6ヶ月の利息:1,000,000円 ×0.01% ÷ 183/365日 ≒ 50.13円
- 1年間の総利息(税引前):99.99円
ただし、実際には金融機関によって端数処理などの計算方法は異なります。また、普通預金の場合は預金の出し入れをするため、実際にはもう少し複雑な計算になります。
定期預金(複利)
次に、定期預金のケースで計算してみましょう。定期預金は商品によって単利と複利があります。ここでは、複利で、100万円を年利0.05%で1年間預けた場合で計算します。
定期預金(複利)のシミュレーション
- 前半6ヶ月の利息:1,000,000円 × 0.05% × 182/365日 ≒ 249.315円
- 後半6ヶ月の利息:(1,000,000円 + 249.315円) × 0.05% × 183/365日 ≒ 250.747円
- 1年間の総利息(税引前):500.062円
定期預金は満期になるまで受け取れません。期間中は税引前の利息が翌年の元本に上乗せされるため、元本を増やしたり、金利が上がったりすれば複利効果は大きくなります。また、預入期間を長くすれば、元本や金利が同じでも、複利効果に期待できます。
外貨建て定期預金(複利)
次に、外貨建て定期預金(複利)の利息を計算してみましょう。外貨建ては為替相場の影響を受けるため、円建てよりもリスクは高くなります。ここでは、円建て定期預金より利率が高い1万ドルを年利3%(半年複利)で1年間預けた場合で、預入時、満期時ともに1ドル150円として計算します。
外貨建ての場合、預入時に円をドルに換え、受取時にドルを円に換えます。
外貨建て定期預金(複利)のシミュレーション
- 預入時のドル換算額: 1,000,000円 ÷ 150円 ≒ 6,667ドル
- 前半6ヶ月の利息:6,667ドル × 3% × 182/365日 ≒ 1ドル
- 後半6ヶ月の利息:(6,667ドル + 1ドル) × 3% × 183/365日 ≒ 1ドル
- 1年間の総利息(税引前):約2ドル
実際には、税金が差し引かれてから円に換算します。外貨建て定期預金は、為替変動リスクがあるものの、年利の高さをメリットとして活用するのが一般的です。
預金の比較とシミュレーション

外貨建て定期預金を検討する場合、為替変動リスクを考慮する必要があります。ここでは、為替相場の変動でどのように影響するか、具体例とともに見ていきましょう。
100万円を1年間預けた場合
普通預金と円定期預金は、為替の影響を受けないため、円高・円安で変わりません。一方、高い金利が魅力の外貨定期預金ですが、為替レートの変動により受取額に影響を与えます。
ここでは分かりやすく1ドル100円で預け入れ、1ドル95円の円高になったケースと1ドル105円の円安になったケースをまとめたものが、下記の表です。
100万円を1年間預けた場合のシミュレーション
| 預金種類 | 金利 | 円高の場合 | 円安の場合 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.01% | 1,000,099円 | 1,000,099円 |
| 円定期預金 | 0.05% | 1,000,500円 | 1,000,500円 |
| 外貨定期預金(ドル) | 3.00% | 978,713円 | 1,081,736円 |
預入時よりも円安になれば、円建てよりも金利が高いこともあり、受け取れる利息は大きくなる一方、円高になってしまうと当初の預入金額100万円よりも少なくなります。
500万円を3年間預けた場合
500万円を3年間預けた場合をシミュレーションしてみましょう。元本が500万円と増え、預入期間も長くなることで、高金利のメリットをさらに受けられます。なお、利息は1年ごとに付くものとします。
500万円を3年間預けた場合のシミュレーション
| 預金種類 | 金利 | 円高の場合 | 円安の場合 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.01% | 5,001,500円 | 5,001,500円 |
| 円定期預金 | 0.05% | 5,007,503円 | 5,007,503円 |
| 外貨定期預金(ドル) | 3.00% | 5,190,420円 | 5,736,780円 |
先ほどと同様に、1ドル100円で預け入れ、1ドル95円の円高になったケースと1ドル105円の円安になったケースです。今回は円高でも500万円を超えていますが、さらに円高が進めば、元本割れになってしまう可能性はあります。
このように、円建ては為替リスクがないため、安定した運用が可能です。一方、外貨建て定期預金は為替変動の影響を大きく受け、円に転換するまで運用成果は確定しません。
まとめ
預金の利息には単利と複利があり、商品によって計算方法は異なります。複利の商品であれば、利息に利息が付くため、運用効果は高くなります。また、外貨建て預金は、高金利で魅力的ですが、為替変動リスクを伴います。
預金商品を選ぶ際には、これらの特徴や自分の目的を考慮して判断することが大切です。

2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。