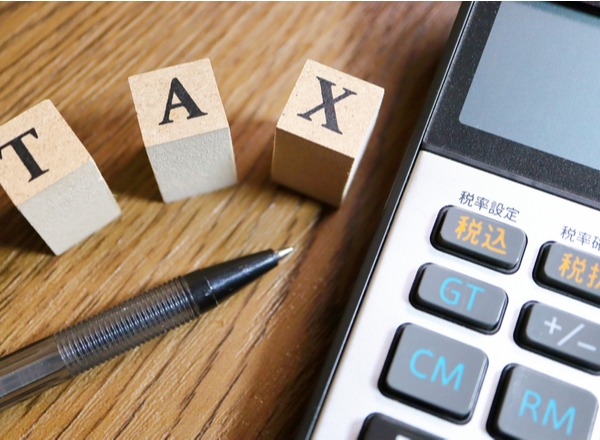円安はいつまで続く?
2026年の為替相場の注目点と資産づくりの考え方

2022年以降の円安がいつまで続くのか、多くの人が気にしています。2026年に向けて為替相場が変動する可能性もあり、家計や資産形成への影響も無視できません。本記事では、円安が長引く背景と今後の注目点を整理し、変動に強い資産づくりの考え方をわかりやすく解説します。
円安が続くといわれる主な要因

「円安はいつまで続くのか」を考えるには、まず現在の円安を押し上げている要因を理解することが欠かせません。ここでは、2026年に向けて重要となる視点を整理します。
日米金利差が縮まらない可能性
現在の円安を最も強く後押ししているのは、日米の金利差です。米国は高金利を維持している一方、日本は長期にわたり金融緩和を続けています。ドルを保有するメリットが大きく、円が売られやすい状況が続いているのです。
今後、米国で利下げが進むと円高方向に動く可能性もあります。利下げのペースが緩やかで、日本の政策金利が大幅に引き上げられない場合、金利差は縮まりません。円安がいつまでも続くシナリオも十分あり得ます。
日本の物価・賃金動向
物価が上昇しても賃金が追いつかなければ、日銀は急激な利上げに踏み切りにくくなります。2026年に向けて賃金が安定的に上がらなければ、日本だけ低金利が続き、相対的に円が弱くなる構図は変わりません。
地政学リスクや世界経済の不透明感
国際情勢の不安定さは、安全資産としてのドル買いにつながりやすく、相対的に円が売られやすくなります。中東情勢や大国間の対立、世界経済の弱含みなどが長期化すると、いつまでも円安が続きやすい要因となります。
2026年までの為替相場のポイント

2026年へ向けて為替を読み解くには、直近の動きを整理しつつ、今後の注目材料を押さえることが重要です。ここでは、相場を左右する主要なポイントを解説します。
2024~2025年の相場動向と今後の注目材料
アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)は、2024年9月に0.5%、11月と12月にはそれぞれ0.25%の利下げを実施しました。その後いったん停止したものの、2025年9月には9ヶ月ぶりに0.25%の利下げを再開し、今後の動向が市場の関心を集めています。
一方、日本では日銀が慎重な姿勢を維持しており、大幅な利上げには踏み切っていません。そのため日米金利差は徐々に縮小しているものの、依然としてドルが優位な状態が続いています。
2026年に向けて注目すべき材料としては、米国の利下げがどの程度続くのか、日本の利上げ開始のタイミング、インフレ指標や景気の強弱などが挙げられます。これら次第で円高・円安いずれの展開も想定され、為替は転換点に差し掛かっているといえます。
2026年に円安・円高へ動く可能性がある要因
2026年の為替相場は、以下のような要因で大きく振れやすい局面が続くと考えられます。
長期金利の動向
米国が長期金利を高く維持すれば円安方向に、日本が長期金利を引き上げれば円高要因となります。
世界的な金融緩和の加速
世界の主要国が同時に利下げに動けば、金利差が縮まり、円が買われやすくなる可能性があります。
景気後退リスク
米国景気が大きく減速すればドルが売られ、相対的に円高に向かう可能性があります。逆に、景気が良ければドル買いが続き、円安が長引くことも考えられます。
円安のメリット・デメリット
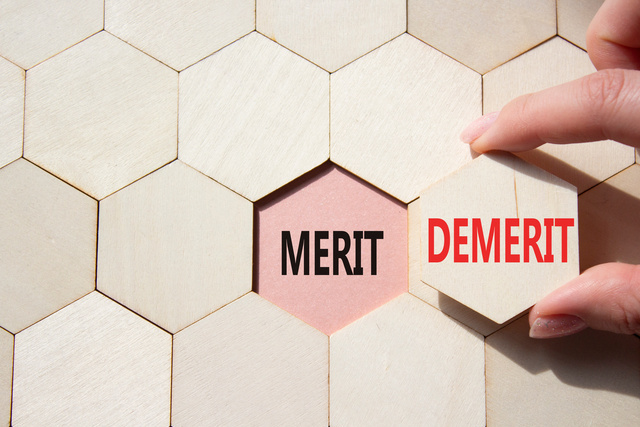
円安には、家計や投資におけるプラス面とマイナス面があります。円安のメリットとデメリットを整理しておきましょう。
円安のメリット
円安が続く局面では、輸出企業の収益が押し上げられるという大きな利点があります。海外で得た利益を円に換算し直すと増加するため、自動車や機械など日本の基幹産業にとっては追い風となり、株価全体を支える力にもなります。
ドルや外貨建て資産を保有している人にとっては、円安が続くほど評価額が増え、長期投資の面でも恩恵を感じやすいという特徴があります。
円安のデメリット
円安になると、輸入品やエネルギー価格が上昇し、生活費が押し上げられます。食料品費・電気代・ガソリン代などが幅広く値上がりし、家計の負担が増えます。
中小企業は輸入コストの高騰を価格に転嫁しにくく、利益が減りやすい傾向があります。その結果、賃金の伸びが鈍くなり、家計にも回り回って影響が及びます。円安は経済全体に複合的な影響をもたらすため、長期化するほど生活防衛の視点が重要になります。
円安局面で注目される投資先

円安はいつまで続くかわかりません。円安の局面では、相場の影響を受けにくい投資先を理解しておくことが安心につながります。ここでは代表的な選択肢を整理します。
外貨建て資産
円安局面では、ドルや外貨建て商品は保有しているだけで円換算額が増える可能性があります。外貨預金や外貨MMFなどは比較的シンプルに始められますが、為替が逆に動くと損失が出てしまいます。短期で売買するより、資産の一部として長期的に保有する方がリスクを抑えられます。
外国株式・海外ETF
外国株式や海外ETFは、為替と株価の両方の動きを取り込める点が特徴です。とくに米国株は過去の成長実績が安定しており、円安が続く局面では円換算のリターンが増える効果もあります。
ただし、為替が円高に振れた場合には評価額が下がるため、投資割合を調整することが重要です。
国内株式
円安の恩恵を受けやすい国内株式もあります。輸出関連企業は利益が伸びやすく、インバウンド関連も訪日客の増加を背景に業績が堅調になりやすい傾向があります。日本企業の競争力や構造的な需要に支えられた銘柄は、長期投資の選択肢として有力です。
長期投資で注意したいリスクと分散の考え方
為替は短期的に大きく動くため、円安を当てにした集中投資はリスクが高くなります。複数の資産に分散し、株式・債券・外貨のバランスを調整しながら長期で積み立てることで、相場変動の影響を平準化できます。また、一定期間ごとに割合を見直すリバランスを行うことで、リスクを適切に保つことが可能です。
円安局面で家計ができる対策

円安がいつまでも続くと、家計へのダメージも大きくなります。ただし、日々の工夫と将来を見据えた資産づくりによって負担を抑えられます。ここでは、今日から始められる実践的な対策を解説します。
生活コスト上昇への備え
円安の影響が最初に表れるのは、食料品やエネルギーなど生活必需品の価格です。まずは固定費や日常の支出を見直すことが重要となります。電気代の節約、買い物の頻度の調整、まとめ買いのしすぎ防止など、小さな積み重ねが大きな節約につながります。
輸入価格上昇に左右されにくい資産づくり
家計の安定を考えるうえで、価格の変動を受けにくい資産を確保しておくことは大きな安心材料になります。たとえば、国債やその他国内債券、価格変動の小さい投資信託などは生活費のクッションとして機能します。さらに、外貨資産を適度に取り入れることで、円安時の備えとなります。
無理のない外貨積立や長期投資の検討ポイント
為替を予測して短期売買を行う方法は、リスクが高くなってしまいます。毎月一定額を積み立てる外貨積立や、投資信託などによる長期投資が現実的です。積立方式であれば高い時も安い時も自動的に購入するため、為替の影響が平均化されます。
積立額や投資割合は生活費に支障のない範囲に抑え、年1回程度は家計全体と投資比率を見直すと、無理なく続けやすくなります。
まとめ
円安は金利差や世界情勢など多くの要因が影響しており、いつまでも続く可能性があります。為替相場に左右されないよう、生活費の見直しや分散投資など、家計を守る基本を整えることが大切です。円安を嘆くより、長期的に安定して続けられる資産づくりを意識しましょう。

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。