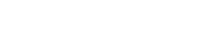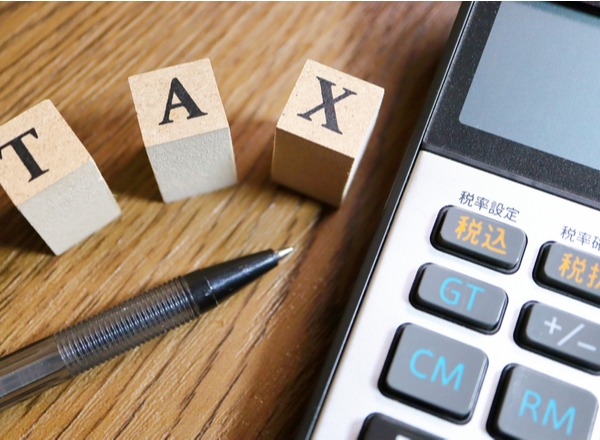ボーナスの平均手取り額は?
年代や業種による違いをわかりやすく解説

「ボーナスの平均手取りってどれくらい?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。自分の年代や業種のボーナスが平均と比べて高いのか低いのか、気になる人も少なくないでしょう。本記事ではボーナスの手取り額の計算方法や、年代・業種・地域ごとの平均支給額を紹介します。
ボーナスの手取りを計算する方法

ボーナスにも給与と同じく、支給額と手取り額があります。まずは、ボーナスの手取りを計算する方法を紹介します。
支給額と手取りの違い
支給額から社会保険料と所得税が差し引かれたものが、ボーナスの手取り額です。控除の割合は、収入や地域によって異なります。一般的には、支給額の6〜8割程度が手取りになることが多いとされています。
ボーナスから引かれる社会保険料と税金
ボーナスから引かれる社会保険料と税金は、以下のとおりです。
ボーナスから引かれる社会保険料と税金
【社会保険料】
・社会保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・介護保険料(40歳以上の方)
【税金】
・所得税
このように、さまざまな保険料がボーナスから差し引かれます。40代になると介護保険料が引かれることも念頭に置いておきましょう。
一方で、税金は所得税のみが引かれます。住民税は引かれないので、ぜひ覚えておきましょう。
ボーナスの手取りの計算方法
ボーナスの手取りは、以下の計算方法で求められます。
・ボーナスの手取り額=総支給額ー(社会保険料+所得税)
転職した場合は保険や税率が変わる可能性があるため、再計算することをおすすめします。
ボーナスの手取り額シミュレーション

ここからは、さまざまなパターンでの手取り額シミュレーションを紹介します。
まずは、ボーナスの総支給額が50万円の場合の手取り額を確認していきましょう。
| 年齢 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り額 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 73,275円 | 69,709円 | 357,016円 |
| 40歳~64歳 | 77,250円 | 69,060円 | 353,690円 |
| 65歳以上 | 73,275円 | 69,709円 | 357,016円 |
続いて、ボーナス総支給額60万円の場合の手取りシミュレーションを紹介します。
| 年齢 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り額 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 87,930円 | 83,651円 | 428,419円 |
| 40歳~64歳 | 92,700円 | 82,872円 | 424,428円 |
| 65歳以上 | 87,930円 | 83,651円 | 428,419円 |
続いて、ボーナス総支給額70万円の場合の手取りシミュレーションを紹介します。
| 年齢 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り額 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 102,585円 | 97,593円 | 499,822円 |
| 40歳~64歳 | 108,150円 | 96,684円 | 495,166円 |
| 65歳以上 | 102,585円 | 97,593円 | 499,822円 |
このように、総支給額が多くなるほど、差し引かれる社会保険料も多くなるのが特徴です。
また、40〜64歳は介護保険料が引かれるため、30代・65歳以上よりも手取りが少なくなるのが一般的です。
ボーナスの平均支給額データ

ここからは、ボーナスの平均支給額を確認していきましょう。
年代別・業種別・夏と冬のボーナスの比較を行い、前年比の推移も紹介します。
年代別のボーナスの平均支給額
e-Stat政府統計の総合窓口による、年代別のボーナスの平均年間支給額は以下のとおりです。
| 年代 | 年間ボーナス平均支給額 |
|---|---|
| ~19歳 | 156,900円 |
| 20~24歳 | 396,800円 |
| 25~29歳 | 686,200円 |
| 30~34歳 | 830,700円 |
| 35~39歳 | 991,000円 |
| 40~44歳 | 1,110,000円 |
| 45~49歳 | 1,186,400円 |
| 50~54歳 | 1,237,100円 |
| 55~59歳 | 1,267,700円 |
| 60~64歳 | 787,200円 |
| 65~69歳 | 398,700円 |
| 70歳以上 | 249,900円 |
参考元:e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査(1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額)」
30代、40代からボーナス支給額が高くなり、55~59歳でピークを迎えます。
ただし、同じ年代であっても転職後の初回ボーナスの金額は低くなることが予想されます。
【業種別】夏と冬のボーナスの平均支給額
厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」によると、業種別のボーナス平均支給額は以下のとおりです。
| 業種 | ボーナス平均支給額(夏季) | ボーナス平均支給額(冬季) |
|---|---|---|
| 調査産業計 | 414,515円 | 413,277円 |
| 鉱業・採石業等 | 558,769円 | 612,066円 |
| 建設業 | 543,670円 | 540,595円 |
| 製造業 | 547,928円 | 558,186円 |
| 電気・ガス業 | 881,533円 | 943,474円 |
| 情報通信業 | 739,621円 | 707,303円 |
| 運輸業・郵便業 | 395,736円 | 398,540円 |
| 卸売業・小売業 | 382,412円 | 373,565円 |
| 金融業・保険業 | 703,753円 | 641,032円 |
| 不動産・物品賃貸業 | 588,824円 | 551,281円 |
| 学術研究等 | 645,387円 | 588,937円 |
| 飲食サービス業等 | 75,897円 | 83,199円 |
| 生活関連サービス等 | 186,504円 | 184,277円 |
| 教育・学習支援業 | 567,828円 | 589,333円 |
| 医療・福祉 | 282,874円 | 308,846円 |
| 複合サービス事業 | 429,741円 | 455,496円 |
| その他のサービス業 | 241,311円 | 236,048円 |
参考元:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等≪特別集計≫令和6年夏季賞与(一人平均)」「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等≪特別集計≫令和6年年末賞与(一人平均)」
業種別に見ると、電気・ガス業が最も高く、飲食サービスが最も低いことがわかります。
また、夏季・冬季のボーナス平均支給額は、企業や業種によって異なります。
ボーナスの前年比の推移
2025年夏季ボーナスは、前年と比較して約8割の業種がプラスになりました。
一方で、前年より悪化している業種もあり、業種・企業によって差が出ているのが現状です。
令和2年~令和6年夏季までの推移を以下の表で確認しましょう。
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏季ボーナス | -1.0 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | 4.2 |
| 夏季ボーナス | -3.4 | 0.3 | 3.7 | 0.9 | 4.5 |
出典元:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等≪特別集計≫令和6年年末賞与(一人平均)」
都道府県別のボーナス平均支給額

ここからは、都道府県別のボーナス平均年間支給額を紹介します。
都道府県別のボーナス平均支給額
政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 都道府県別」を参考に、都道府県ごとのボーナス平均支給額をランキング形式で紹介します。
| 順位 | 都道府県名 | ボーナス 平均支給額 |
順位 | 都道府県名 | ボーナス 平均支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,232,200円 | 25 | 香川県 | 807,500円 |
| 2 | 神奈川県 | 1,106,300円 | 26 | 山梨県 | 794,700円 |
| 3 | 愛知県 | 1,065,900円 | 27 | 岡山県 | 791,200円 |
| 4 | 大阪府 | 1,040,900円 | 28 | 奈良県 | 783,300円 |
| 5 | 兵庫県 | 940,800円 | 29 | 新潟県 | 770,400円 |
| 6 | 静岡県 | 920,800円 | 30 | 熊本県 | 765,500円 |
| 7 | 滋賀県 | 917,100円 | 31 | 大分県 | 758,600円 |
| 8 | 京都府 | 909,300円 | 32 | 島根県 | 757,200円 |
| 9 | 茨城県 | 906,400円 | 33 | 岐阜県 | 754,100円 |
| 10 | 長野県 | 901,800円 | 34 | 愛媛県 | 752,300円 |
| 11 | 広島県 | 895,600円 | 35 | 山形県 | 733,300円 |
| 12 | 三重県 | 890,400円 | 36 | 佐賀県 | 727,100円 |
| 13 | 山口県 | 886,500円 | 37 | 北海道 | 722,500円 |
| 14 | 福岡県 | 871,600円 | 38 | 鹿児島県 | 722,300円 |
| 15 | 石川県 | 866,100円 | 39 | 岩手県 | 717,500円 |
| 16 | 埼玉県 | 859,100円 | 40 | 長崎県 | 715,100円 |
| 17 | 群馬県 | 848,500円 | 41 | 福島県 | 705,800円 |
| 18 | 徳島県 | 839,700円 | 42 | 高知県 | 678,200円 |
| 19 | 福井県 | 835,700円 | 43 | 秋田県 | 662,800円 |
| 20 | 宮城県 | 829,200円 | 44 | 宮崎県 | 653,800円 |
| 21 | 栃木県 | 825,300円 | 45 | 青森県 | 642,800円 |
| 22 | 千葉県 | 820,900円 | 46 | 鳥取県 | 592,900円 |
| 23 | 和歌山県 | 812,100円 | 47 | 沖縄県 | 535,400円 |
| 24 | 富山県 | 811,300円 |
参考元:e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査(sanko1(参考表)都道府県別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(47都道府県一覧))」
第1位は東京都の1,232,200円、最下位は沖縄県の535,400円となっており、約70万円の差があることがわかりました。
四国各県のボーナス平均支給額
四国各県のボーナス平均支給額は、以下のとおりです。
| 愛媛県 | 752,300円 |
|---|---|
| 高知県 | 678,200円 |
| 徳島県 | 839,700円 |
| 香川県 | 807,500円 |
まとめ
ボーナスの手取り額は、社会保険料や税金が控除されるため、額面よりも少なくなります。年代や業種、地域によって支給額には大きな差があり、自身のボーナスが平均と比べてどの位置にあるのかを知ることは、今後のキャリアや生活設計を考えるうえでも参考になります。この記事をきっかけに、自身のボーナスの内容を見直してみてはいかがでしょうか。

大手生命保険の営業を5年間経験し、FP2級を取得。現在は金融ライターとして資産運用、保険、節税に関する記事を執筆。200記事以上を手掛け、読者に信頼される情報提供を目指す。金融業界の知識と実務経験を活かし、わかりやすく実践的な内容を提供。
関連リンク

この記事が気にいったら
シェアしよう