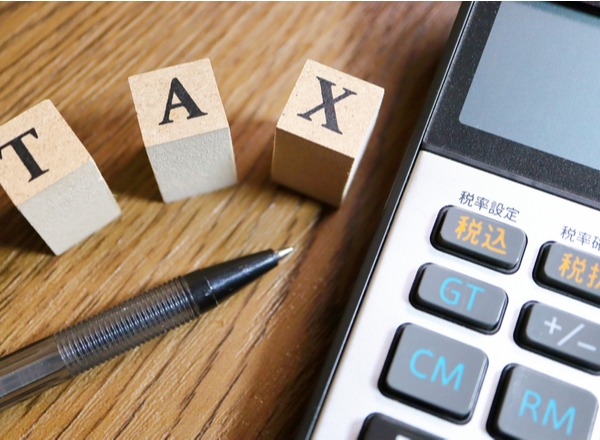スタグフレーションとは?
起こる要因や生活への影響、対策方法を知って備えよう

新型コロナウイルス拡大による経済への影響や世界情勢の変化によって、景気や物価の変動が起きています。2022年(令和4年)に入ってから生活必需品の値上がりが相次ぎ、スタグフレーションという現象を無視できない状況です。この記事ではスタグフレーションとは何か、要因や生活への影響、対策方法について解説します。
スタグフレーションとは

スタグフレーションは、インフレーションの物価上昇とデフレーションの景気停滞が同時に起きている状況を指します。Stangnation(景気停滞)とInflation(物価上昇)を組み合わせた造語です。
経済用語にはさまざまな単語があり、複雑に感じやすいです。まずは、スタグフレーションに関連する経済の現象に触れながら説明します。
物価の変動と経済
モノやサービスの値段が物価であり、経済の状況を示す重要な指標が消費者物価指数です。経済が活発になるとお金の循環が活性化されて、消費者物価指数は上昇します。逆に、経済が停滞してお金の循環が滞ると、消費者物価指数は下降するのです。
消費者物価指数は経済の状況を数値化できるため、中央銀行の金融政策や政府の財政政策に活用されます。政策によって物価の上昇や下降を促すことで、経済の変動を保ったり小さくしたりするのです。
インフレーション
物価が継続的に上昇している状況が、インフレーションです。企業が価格を上げても消費者が積極的にモノやサービスを購入するため、売上が上昇します。企業の利益が増えると従業員の給料が上がり、より積極的に消費活動が行われるのです。インフレーションによってお金の循環が活発になり、経済が発展します。
経済の停滞や物価の下落が続いている状況では、インフレーションに向かう政策が行われるのです。インフレーションは経済を発展させる効果がありますが、過剰な物価上昇はお金の価値を下げてしまうため、注意が必要になります。
デフレーション
物価が継続的に下落している状況が、デフレーションです。モノやサービスが売れずに企業の売上が下がります。企業の業績が悪化すると従業員の給料は下がり、消費活動が消極的になるのです。
経済はデフレーションによってお金の循環が滞り、停滞します。給料が下がるとより安いモノやサービスが求められて、企業は価格を下げるのです。
このように物価の下落が加速する悪循環を、デフレスパイラルといいます。物価が下がるとお金の価値が上がるため現金を貯蓄していると恩恵を受けられますが、借入があると返済が大変です。
物価上昇と景気停滞
スタグフレーションになると、景気が停滞しているにもかかわらず物価が上昇するため、給料は増えずに支出が増えて家計が苦しくなります。デフレーションでは物価上昇のための政策によって、市場の通貨流通量を増やすことが解決策です。しかし、スタグフレーションでは物価が上昇すると状況が悪化するので、同じ政策では解決できない点が大きな問題となります。
スタグフレーションが起きる要因

インフレーションやデフレーションは、物価の変動や消費活動の変化によって起きる現象です。ここからは、スタグフレーションが起きる要因について説明します。
オイルショック
経済の状況にかかわらず生活必需品の供給不足が起きると、物価が上昇します。
過去に日本で起きたオイルショックは、1970年代の第4次中東戦争の影響による石油価格の引き上げと供給制限が原因でした。石油はガソリンなどの原料だけでなく、プラスチック製品などに使われます。経済が停滞しているなかで、輸送費の高騰や生活必需品の品薄などにより物価が上昇して、スタグフレーションが起きたのです。
イギリスのEU離脱
諸外国でスタグフレーションが起きたのは、2016年(平成28年)のイギリスでした。EU離脱が決定した時点からポンドの価値が下がり、ポンド安となって輸入品などの物価が上昇しました。さらにイギリス国内での所得が減少していき、物価の上昇と景気停滞が同時に起きてスタグフレーションとなったのです。
円安による輸入価格の上昇
日本では円安ドル高になると、輸入する食糧や生活必需品の価格が上昇します。モノやサービスの供給を輸入に頼っていると、円安の影響を強く受けて物価が上昇するのです。
国内の景気が停滞しているときに円安による物価上昇が起きると、スタグフレーションの状況となります。2022年(令和4年)に入ってからアメリカの利上げに伴う円安の影響で物価が上昇し、スタグフレーションに陥る可能性が高くなっているのです。
スタグフレーションが生活に与える影響と対策

物価上昇と景気停滞によるスタグフレーションが生活に与える影響と、その対策について説明します。
生活費の上昇で家計が圧迫される
スタグフレーションが起きると給料が増えず支出のみが増えるため、家計が圧迫されます。同じ生活水準を保っていても手元に残るお金が少なくなり、節約したり我慢したりすることが増えるのです。すぐに生活に支障が出るほどの影響がなかったとしても、日々のストレスが増えたり欠乏感を感じやすくなったりします。
スタグフレーションの影響が、個人の生活の充実度や幸福度にまで波及する可能性が考えられるでしょう。
将来の見通しが立てにくい
スタグフレーションが起きた要因によりますが、その状況がいつまで続くか見通しが立てにくくなります。新型コロナウイルス拡大による経済の停滞やロシアとウクライナの情勢などは、将来の動向が見通しにくい事例です。要因となっていることがいつまで続くか見通しがつかないと、スタグフレーションから抜け出せる時期が不透明になります。
資産を分散する
スタグフレーションの状況では物価が上昇しお金の価値が下がるため、現金以外に資産を分散することが効果的です。不動産などの現物資産はデフレーションやインフレーションに強く、物価の影響を受けにくい特徴があります。不動産は不景気でモノが売れにくいなかでも、生活に不可欠なため価格が下がりにくいです。
また、不景気の状況で価格が上がりやすい金などの場合、スタグフレーションの状況でも安全に資産を保てます。
外貨で資産を持つ
日本円だけでなく米ドルなどの外貨で資産を持つことが、スタグフレーションの対策として効果的です。資産を日本円のみで持っていると、円安ドル高などの状況で価値が下がってしまいます。日本円と米ドルで資産があると、どちらかの価値が下がっても一方の価値は上がるため、リスクが分散されるのです。
外貨で資産を持つ方法は、外貨建ての積立保険や投資商品、外貨預金、FXなどがあります。
まとめ
スタグフレーションは物価の上昇と景気停滞が同時に起きる現象で、生活にも影響を与えます。日本だけでなく諸外国を含めた世界の情勢を視野に入れて、経済の状況を見ておくことが大切です。資産を分散するなどの対策を考えて、事前に備えておきましょう。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。