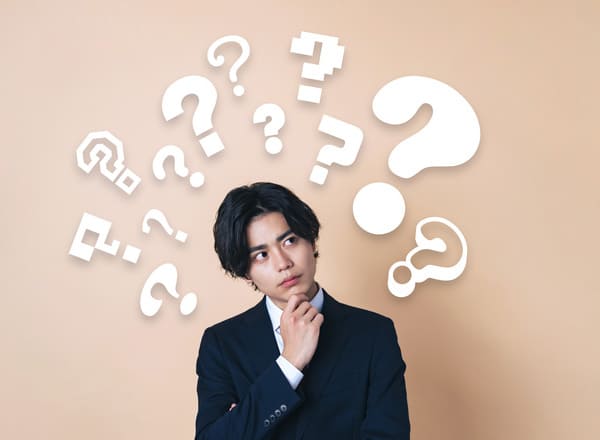退職後の手続きの順番を解説!
申請方法や必要書類などを事前に確認しよう
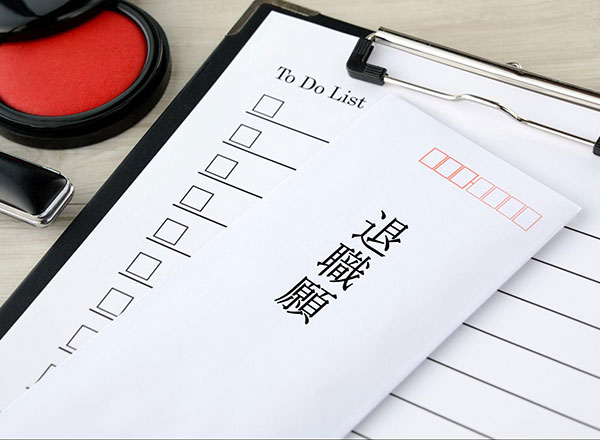
退職後の手続きはいくつもあり、期限が決まっていてしくみも複雑です。スムーズに手続きを進めるためには、全体を把握しておく必要があります。この記事では、いつ・何を・どこで行うかがわかるよう、退職後の手続きの順番や必要書類などをまとめますので、ぜひ参考にしてみてください。
退職後は5つの手続きを順番に行う

退職に伴い、転職活動や業務の引き継ぎなどで忙しいなか、退職後の手続きも同時進行で行う必要があります。ポイントを押さえて、無理なくスムーズに手続きを進めていきましょう。
退職後の手続きは「順番通り」に
退職後の手続きはいくつかに分かれており、それぞれ提出期限や必要書類が異なるため、どの順番で行うかが大切です。離職票がなければ失業保険の手続きを始められないように、ある手続きが完了していないと次のステップへ進めないケースもあります。
期限を過ぎてしまうと保険料の増額や給付の遅れといったリスクがあるため、提出期限を意識して順番通りに手続きを進めましょう。
退職後の手続きは5つ
退職後に行う代表的な手続きは以下の5つです。方法や手続き先がそれぞれ異なるため、まずは5つの手続きについて全体像を把握しましょう。
①年金の切り替え
退職前の職場で厚生年金に加入していた場合、14日以内に国民年金へ移行します。
ただし、退職後に間をあけずに再就職先が決まっている場合は、新しい会社での手続きとなるため、国民年金への切り替えは不要です。第3号被保険者となる場合は、配偶者の勤務先を通しての手続きが必要となります。
国民年金基金「会社を退職したときの国民年金の手続き」
②健康保険の切り替え
退職後に加入する健康保険には、3つの選択肢があります。保険料や条件を比較し、自分に合う方法を選びましょう。手続きは20日以内を目安に行います。
【退職後の健康保険】
- 任意継続
- 国民健康保険
- 家族の健康保険(被扶養者)
③雇用保険の申請
退職後に転職活動を行う場合や職業訓練を受ける予定の方は、離職票が届いた時点で雇用保険の基本手当(失業給付)の受給申請を行います。再就職先がすぐ決まっている場合は、基本手当を受給しないケースもあります。
④住民税の支払い
在職中に給与天引き(特別徴収)されていた住民税は、多くの場合、退職後は普通徴収に切り替わります。一括払いのほか、年4回の分割払いも選択可能です。基本的に、退職月の翌月10日までに支払います。
⑤所得税の確定申告
通常、12月31日時点で在職している従業員については、在職している会社で年末調整を受けられます。しかし、年の途中で退職し、年内に再就職しない場合は自身での確定申告が必要となります。期限は翌年3月15日前後です。
退職後の手続きの流れ
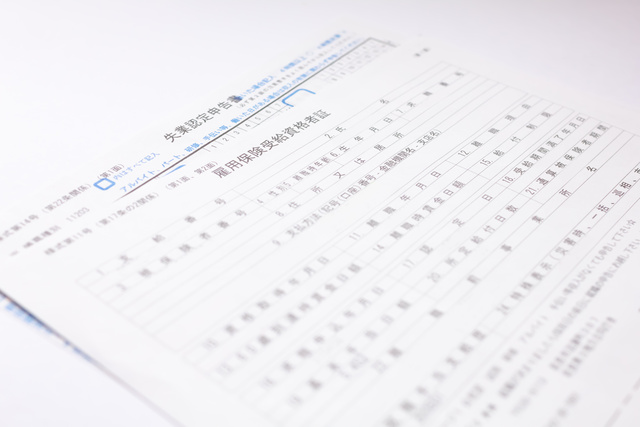
では実際に、退職後はどのような書類が必要で、何をいつまでに行えばいいのでしょうか。順番通りスムーズに進められるよう、手続きの方法を時系列でまとめます。
退職直後:会社から受け取る書類の確認
退職にあたり、会社からいくつかの書類を受け取ります。のちの手続きに必要な重要書類となるため、確実に確認しましょう。
【退職後に受け取る書類】
- 離職票…失業保険の申請に必須
- 源泉徴収票…確定申告や再就職先での年末調整に必要
職場に返却するもの
退職時、健康保険被保険者証や貸与されているもの(社員証・名刺・制服・業務端末など)を必ず返却します。返却すべきものについて事前に会社へ確認しておくと、のちのトラブルを防げます。
退職後~14日以内:年金の切り替え
退職後に転職先が決まっておらず、家族の扶養に入る予定がない場合は、14日以内に市区町村役所にて国民年金への加入手続きを行います。
【必要書類】
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 退職日がわかる書類(離職票、退職証明書など)
退職後~20日以内:健康保険の切り替え
加入する健康保険が決まったら、退職から20日を目安に切り替え手続きをします。加入予定の健康保険により、手続き先が異なりますので注意しましょう。
| 任意継続 | 退職前の健康保険組合へ申請する |
| 国民健康保険 | 市区町村役所に申請する (離職票または退職証明書が必要) |
| 家族の健康保険 (被扶養者) |
配偶者など扶養する家族の勤務先に申請する |
離職票が届き次第:雇用保険の申請
雇用保険の基本手当を受ける方は、管轄のハローワークで求職の申し込みが必要です。退職後1~2週間ほどで、会社から自宅へ離職票が送られてきます。離職票が届き次第、ハローワークで求職の申し込みと失業保険の給付手続きを行います。
【必要書類】
- 離職票
- 本人確認書類
- 写真(マイナンバーカードの提示で省略可)
- 印鑑
- 通帳またはキャッシュカード
退職月の翌月:住民税の支払い確認
住民税は、退職と同時に給与天引きがなくなり普通徴収に切り替わります。退職後は「一括で支払う」か「普通徴収(分割で納付)」にするか、職場の担当者と事前に決めておきましょう。
その後は、自治体から自宅へ納付書が送られてきたら、期限までに住民税を支払います。
(年内に再就職しない場合)翌年3月:確定申告
退職後、年内に就職が決まらなかった人、あるいは年末調整を受けられない人は、確定申告を自分で行います。医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合も、申告が必要です。控除を活用すれば所得税が還付される可能性もあるため、期限までにしっかりと申告しましょう。
管轄の税務署で無料相談を行っているので、申告方法がわからず不安な方は、窓口での相談がおすすめです。
【用意しておく書類】
- 源泉徴収票(退職時に会社から必ず受け取る)
- 医療費・生命保険料の控除証明書など
退職後のケース別の注意点

退職後の状況によって必要な手続きやタイミングが異なり、さらに手続きが不要な場合もあります。それぞれのケース別に注意点をまとめました。
就職先が決まっている
新たな就職先で手続きを進めるため、退職後の年金や健康保険の切り替えは不要です。住民税に関しては、転職先で引き続き特別徴収されることも多いので、退職前に総務担当者へ相談しましょう。
再就職まで期間が空く
再就職までに空いた期間は、個人で年金や健康保険に加入する必要があるため、必ず手続きをします。雇用保険の受給する場合は、離職票を受け取ったらすぐにハローワークでの申請が必要です。年の途中に退職し、12月31日時点で無職の場合は、確定申告も忘れずに行いましょう。
無職の状態が続く
国民健康保険や国民年金への加入が必須です。失業保険の給付条件を満たす場合は、離職票の受け取り後ハローワークで申請しましょう。また、住民税や所得税の納付スケジュールを把握し、資金計画を立てておくと安心です。年の途中に退職し、翌年以降も再就職の予定がない場合は、忘れずに確定申告を行います。
まとめ
退職後は5つの手続きが基本です。期限や必要書類を事前に把握し、あらかじめスケジュールを立てておくと安心です。順番通りに手続きを済ませると、今後のキャリアや生活がスムーズに進みます。退職の時期が近づいてきたら、早めの計画と行動を心がけましょう。

12年間の医療事務勤務を経てフリーライターとして活動。資産形成や家計管理をテーマに、専門用語をかみ砕いたわかりやすい金融記事を執筆。NISAとiDeCoを活用した資産運用経験は7年目。整理収納アドバイザーとしての知見も活かし「お金と暮らしを整え、心にゆとりを生み出す」情報を発信している。