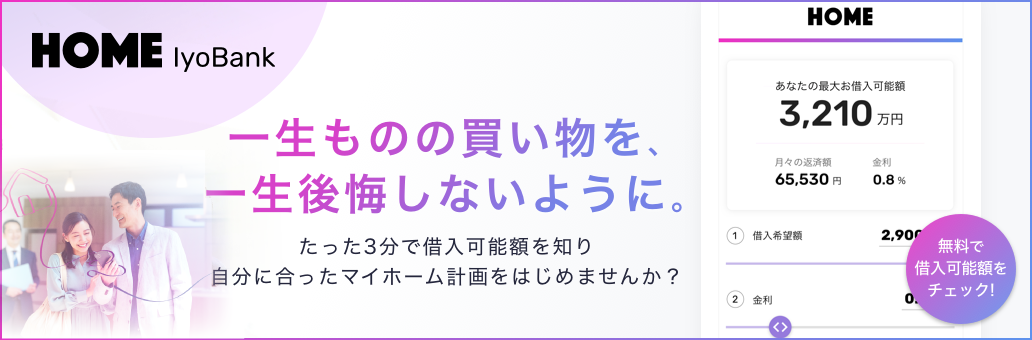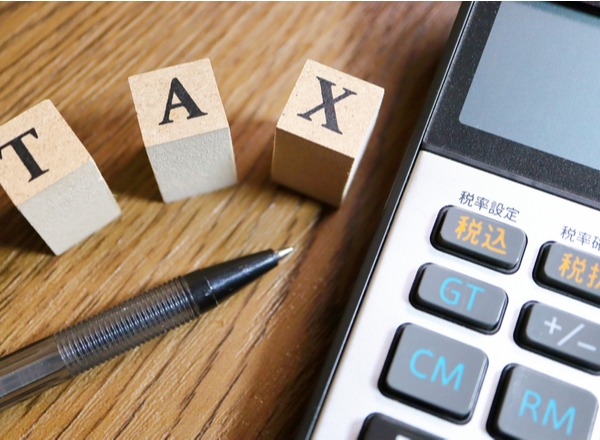2022年住宅ローン控除改正
制度の概要から今後の減税の行方を徹底解説

住宅購入の際には住宅ローンを組むことが多いです。近年は返済方法や金利の選び方だけでなく、住宅ローン控除の活用が注目されています。税制改正に伴ってさまざまな制度が改正されるため、最新情報を知ることが大切です。この記事では、2022年(令和4年)の住宅ローン控除改正と今後の行方について説明します。
住宅ローン控除の制度の概要

制度について聞いたことはあっても、住宅購入を検討するまで詳しい内容は知らないことが多いでしょう。まずは、住宅ローン控除の制度の概要を説明します。
所得税や住民税が控除される
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される制度です。住宅ローン控除は正式名称で「住宅借入金等特別控除」といいます。
会社員の場合は毎月の給与から所得税と住民税が控除されるため、税額まで意識せずに納税していることが多いです。住宅ローン控除が適用されれば、1年間で納めた所得税や住民税に対して上限40万円までお金が戻ってきます。例えば、1年間の所得税が60万円の場合は住宅ローン控除の上限で40万円戻ってくるので、実際の納税額は20万円になります。
制度が適用される基準
住宅ローン控除を利用するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。以下は、新築を購入して2021年(令和3年)末までに入居する場合の基準です。
本人が居住する住宅であること
住宅の取得から入居までが、6ヶ月以内であることが条件です。本人が亡くなった場合は、同日まで継続して居住していることが条件となります。投資用や親族が居住する住宅には適用されません。
控除を受ける本人の年間所得が3,000万円以下
住宅ローン控除を受ける年分の年間所得が3,000万円を超えると、適用されません。3,000万円未満となる年には適用できます。
住宅の床面積が50平方メートル以上
判断基準は、登記簿に記載の床面積です。また、床面積の2分の1以上を居住用とする必要があります。床面積が50平方メートルというのは、一般的な住宅の間取りで2LDKくらいに相当します。両親と子ども1~2人で住むのに適している広さになります。同じ建物に店舗と住宅が併設される場合は、床面積の割合に注意が必要です。
住宅ローンの借入期間が10年以上
9年以下の短期間のローンには、適用されません。住宅購入が目的のローンでは30年や35年などを返済期間にするのが一般的なため、10年以上となることが多いです。勤務先からの借入金の場合、利率によっては住宅ローン控除の対象とならないため確認が必要となります。
その他の特例などの適用を受けていない
以下のようなその他の特例が適用されていると、対象になりません。住宅ローン控除とは別で、特例を受けるかどうかの確認が必要です。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例 など
2022年の改正がいつから適用されるか解説

税制改正により、住宅ローン控除の条件と控除される税額の改正が行われます。ここからは、改正される内容といつから適用されるかを解説します。
制度の適用期間が延長
従来は2021年(令和3年)の年末までの入居が対象でしたが、4年間延長され2025年(令和7年)の年末が入居期限になります。この延長によって、2022年(令和4年)以降も住宅ローン控除の利用が可能です。
控除期間が最大13年間に延長
2021年(令和3年)までは控除期間が10年間だったのに対し、2022年(令和4年)からは最大13年間に延長となります。ただし、中古住宅の場合は従来どおり10年間です。
控除率が縮小される
2021年(令和3年)までは控除率が1%だったのに対し、2022年(令和4年)からは0.7%となります。この変更によって、同じ住宅ローン残高でも控除される税額が下がるのです。控除の対象となるローン残高の上限金額(以下、「借入限度額」といいます)が3,000万円の場合、最大で3,000万円の0.7%である21万円が控除額となります。毎年21万円の控除を受けると、13年間で273万円の減税です。
減税のメリットを高める方法

住宅ローン控除は基準を満たせば適用を受けられますが、より減税額を大きくするための条件があります。ここからは、住宅の種類によって異なる点を説明します。
新築と中古で減税額が違う
中古住宅の借入限度額は3,000万円と一律で、新築住宅は3,000万円から最大で5,000万円となります。住宅ローン控除が適用される住宅ローンには借入限度額が設けられており、これを超える金額は控除の対象外です。
借入限度額が3,000万円の場合、年末の住宅ローン残高が4,000万円あったとしても、控除の対象は3,000万円となります。また、中古住宅で住宅ローン控除を適用するためには、新築住宅の基準に加えて築年数や耐震基準などの基準を満たすことが必要です。新築住宅の方が、中古住宅より大きな減税額が期待できます。
住宅の省エネ性能を高くする
借入限度額の上限は、省エネ性能により4段階に分類されています。借入限度額がもっとも高いのは、長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円です。次にゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH水準省エネ住宅)で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円、その他の住宅で3,000万円となります。
新築住宅は省エネ性能を高くするほど借入限度額が高くなり、住宅ローン控除による減税額が大きくなります。ただし、省エネ性能が高いと建築費も高くなるため、減税目的だけでなく建築費の総額やローンの返済計画についても考えることが大切となります。
住宅ローン控除の注意点と今後の行方

制度としては、2025年(令和7年)の年末まで延長となりました。ここからは、制度を利用するうえでの注意点と、今後について解説します。
住宅ローンの繰上げ返済に注意
繰上げ返済によって住宅ローンの返済期間が10年を下回った場合、住宅ローン控除が適用されなくなります。繰上げ返済は毎月の返済とは別で一定額をまとめて返済することで、期間短縮型と返済額軽減型があります。期間短縮型は、毎月の返済額を変えずに返済完了日を前倒しにする方法です。繰上げ返済するタイミングと金額によっては、返済期間が10年未満になる場合があるため注意しましょう。
確定申告に備えて事前の情報収集が重要
住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に確定申告が必要です。初めての確定申告では、申告書の記載方法を調べたり必要な書類を用意したりすることに時間を要する場合があります。直前になって準備を始めると間に合わない可能性もあるため、前もって情報収集しておきましょう。
会社員が確定申告するのは、初年度だけです。2年目以降は以下の2つを勤務先に提出することで、確定申告が不要になります。
・税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」
・金融機関での「残高証明書」
省エネ性能が必須となる
2024年(令和6年)以降は、一定の省エネ性能を満たさないと適用対象外となります。これは、「令和4年度税制改正の大綱」に記載されている内容です。住宅ローン控除を適用したくても条件に当てはまらない場合があるので、事前に確認しておきましょう。
住宅ローンの借入限度額が引き下げられる
2024年(令和6年)以降は、借入限度額が引き下げられます。長期優良住宅・低炭素住宅で4,500万円、次にゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH水準省エネ住宅)で3,500万円、省エネ基準適合住宅で3,000万円です。2022年(令和4年)の改正からも変更となるため、住宅購入の時期が変わると借入限度額が下がります。借入限度額によって控除される税額が大きく変わりますので、購入時期を検討する材料に追加しておきましょう。
まとめ
住宅の購入では、住宅ローンだけでなく土地探しや間取り決め、引っ越しの準備、家具家電の買い替えなど考えることが多いです。最新情報を確認したり将来の計画を立てたりと、事前に十分な時間を作って備えておきましょう。

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。